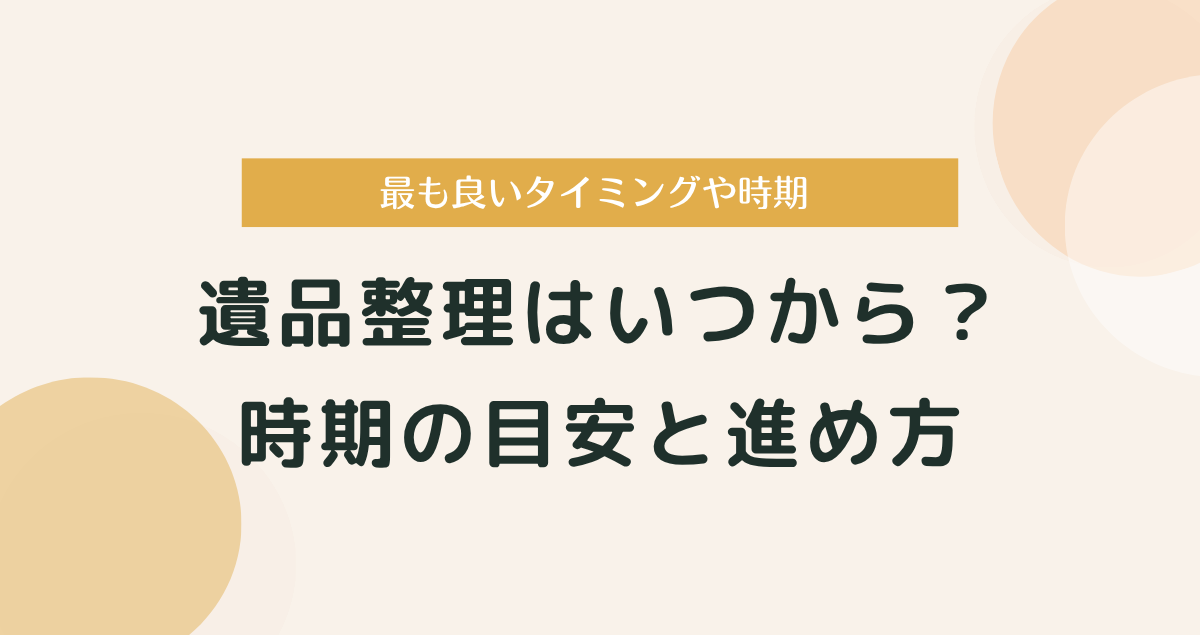遺品整理は、一般的に「四十九日法要の後」から始めるのが安心です。
葬儀直後は心身の負担が大きいため、無理に進めると後悔することもあります。
この記事では、遺品整理を始める時期の目安や、状況別の進め方を初心者にも分かりやすく解説します。
目次
遺品整理はいつから始める?最も良いタイミングや時期は?

【基本】四十九日法要の後が一般的
最も選ばれているのは「四十九日法要」の後です。
葬儀後すぐは感情が不安定で、片づけに手がつけられないことも。四十九日を過ぎる頃には少しずつ心に余裕が生まれ、遺品の整理に向き合える方が多いです。
また、気持ちの整理がつき始める頃であり、法要を区切りに家族間の話し合いも進みやすくなります。
葬儀後は各種手続きも同時に必要になるため、全体像を押さえておくとスムーズです。
賃貸・持ち家・遠方実家での違い
遺品整理を始める時期は、住まいの状況によっても変わります。
- 持ち家の場合:時間に余裕があるため、心の整理を優先できる
- 賃貸・施設の場合:退去期限に備えて早めの片づけが求められる
- 遠方の実家など:長期休暇に合わせて計画的に進めるのもおすすめ
急いで整理すべきケースと後回しでも良いケース
- 早急な対応が必要:賃貸の退去期限が迫っている、相続放棄の検討中など
- 計画的に進められる:持ち家で時間的余裕がある、大量の遺品がある
遺品整理をスムーズに進めるステップ

ステップ1:無理のないスケジュールを立てる
たとえば「週末2時間×4週」など、無理のない範囲で区切るのがポイントです。一気に終わらせようとすると疲弊して続きません。
時間配分の目安:
- 1K・1DK:1〜2日
- 2LDK:3〜5日
- 一戸建て:1〜2週間
ステップ2:家族・親族との話し合いでトラブル防止
事前に整理方針や役割分担を決めることで、後悔のない遺品整理ができます。
- 整理の方針:形見分け優先か処分重視か
- 役割分担:書類は長男、写真は長女など
- 共有手段:LINEグループや表計算など
ステップ3:遺品を「残す・譲る・処分・保留」に分類
遺品整理は、まず「分類」から始めるのがスムーズです。
分類の目安は次の4つです。
- 残す:思い出の品や今後も保管したい物
- 譲る:形見分けとして親族や友人に渡す物
- 処分:不要になった日用品や破損品
- 保留:判断に迷う物は一時的に箱に入れて後日検討
「保留ボックス」を用意し、数週間後に再確認すると後悔の少ない整理ができます。
ステップ4:貴重品・重要書類を先に確保
遺品の中には、相続や手続きに関わる重要書類があります。
- 通帳やキャッシュカード
- 不動産の権利証・登記簿謄本
- 生命保険・年金の書類
- 有価証券・株主優待関連書類
これらは相続期限を意識して早めに確保しましょう。
ステップ5:思い出の品は時間をかけて選別
写真や手紙、趣味の品など感情に関わる遺品は、整理が進みにくい部分です。
心に余裕があるタイミングで、以下の方法を取り入れると進めやすくなります。
- 迷うものは一旦「保留ボックス」へ
- 写真はスマホで撮影し、デジタル保存してから処分する
- 複数人で見ながら話し合うと気持ちの整理が進む
ステップ6:大型家具・大量処分は無理せず業者活用
一戸建てや長年の荷物が多い場合、家族だけでの片付けは体力的にも精神的にも負担が大きくなります。
そんなときは、専門業者を活用しましょう。
- トラック積み放題プランなどを利用すると効率的
- 買取と処分を同時に対応できる業者を選ぶとコスト削減になる
- 見積もりは必ず2〜3社比較するのが安心
ステップ7:整理後は記録を残して心の整理も
整理が完了したら、記録を残しておくことで次のメリットがあります。
- 写真や動画に残すことで思い出を共有できる
- 相続や形見分けの記録にも活用できる
- 次回の整理や生前整理の参考になる
最後は、ゆっくりと故人との思い出を振り返る時間を取りましょう。
整理を通じて心の整理ができることも、遺品整理の大切な意味の一つです。
遺品整理を始める前に知っておきたい基礎知識
遺品と遺産の違い
| 種類 | 内容の例 | 区分 |
|---|---|---|
| 遺産 | 預貯金、不動産、有価証券など | 相続対象となる財産 |
| 遺品 | 衣類、家具、写真、日用品など | 故人の生活用品・思い出の品 |
ポイント:遺品整理を始める前に、遺産との違いを理解しておくと相続トラブルを防げます。
形見分けと遺品整理の違い
- 形見分け:親しい人に故人の愛用品を贈る儀礼的行為
- 遺品整理:不要品の処分や保管を含む実務的な片づけ作業
※高額な宝飾品や骨董品は相続税の対象になる場合があるため、贈与前に確認を。
よくある質問(FAQ)
Q1:遺品整理は四十九日前に始めてもいい?
早く着手しても差し支えありませんが、喪中は心身の負担が大きくなりがちです。
まずは貴重品(通帳・印鑑・保険証券・遺言書など)だけを優先的に確認・保管し、衣類や家具などの本格的な整理は法要後に家族の心身が落ち着いてから進めると安心です。
写真や手紙は判断に時間がかかるため、後述の「保留」の運用がおすすめです。
Q2:賃貸の場合はいつまでに片づけるべき?
原則として退去期限(解約日)までに原状回復を含む片づけを完了させる必要があります。
遅延すると家賃や原状回復費の追加負担が発生することがあります。
相続人が複数いる場合は、早めに連絡・役割分担・費用負担の合意を取り、可能であれば賃貸借契約と退去日を大家・管理会社に確認しておきましょう。
Q3:思い出の品が多くて処分できない場合は?
迷う品はすぐに結論を出さず、「保留ボックス」や専用スペースに一時保管しましょう。
期限を数週間~1か月に設定し、心が落ち着いたタイミングで再確認→残す/撮影して手放す/譲るのいずれかを決めます。
写真はデジタル化して保存するとスペースと迷いの両方を軽減できます。
Q4:価値があるかわからない物はどうする?
箱書きのある茶道具・掛軸・絵画・古銭・宝飾品などは、独断で処分せず専門家の査定を受けましょう。
複数社に依頼して相見積もりを取り、来歴(購入時期・領収書・鑑定書)があれば一緒に提示すると評価が安定します。
価値が不明な雑多な品は、写真を撮ってリスト化すると相談がスムーズです。
まとめ|遺品整理は「少しずつ、自分のペースで」
- 始める時期は四十九日後が一般的
- 家族で話し合い、無理のないスケジュールを
- 残す・譲る・処分・保留に分けて進める
- 体力的・精神的に負担を感じたら、業者や相談窓口も活用を
遺品整理は故人と向き合う大切な時間です。焦らず、あなたのペースで進めてください。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。