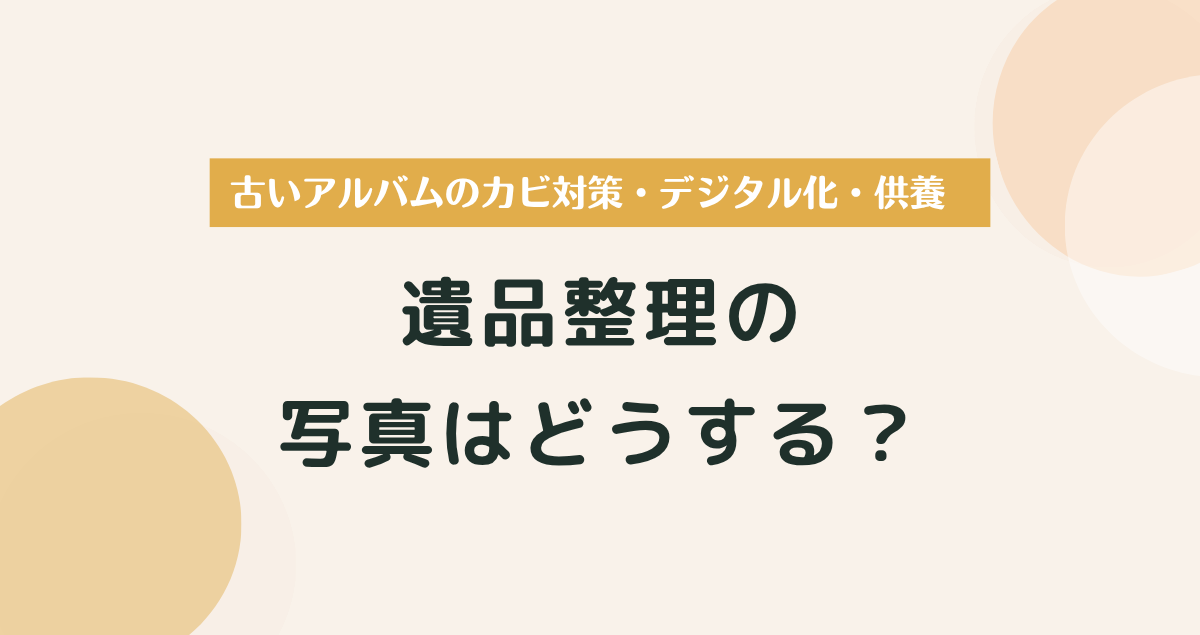故人の写真や古いアルバムは、家族にとってかけがえのない思い出です。しかし、量が多かったりカビや劣化が気になったりして、どこから手をつけていいか迷う方も少なくありません。
この記事では、遺品整理における写真・アルバムの整理方法を5ステップで解説します。古いアルバムのカビ対策、デジタル化、処分や供養まで、心の整理も意識しながら進められる方法をまとめました。
目次
遺品整理の写真はいつ・どう整理する?

遺品写真の整理は、片付け以上に心の整理を兼ねた大切な時間です。無理に急ぐ必要はなく、気持ちに区切りをつけやすいタイミングで進めることが大切です。
遺品写真整理は心の整理とタイミングが大切
遺品写真を整理することは、故人の思い出と向き合い、感謝や悲しみの感情を整理する大切な時間です。
整理を始めるタイミングは、心に余裕が生まれる頃が理想です。
- 四十九日や一周忌など、法要の節目
- お盆やお正月など、家族が自然に集まる時期
- 気持ちに少し余裕ができたとき
遺品写真の残す・処分の判断基準と仕分け方法

集めた写真は、残す・処分・保留の3つに分けると整理しやすくなります。感情的な負担が大きいので、ゆっくり休憩を挟みながら進めましょう。
残す写真と処分する写真の基準
残す写真と処分する写真の基準を決めることで、作業がスムーズになります。
- 残す写真:故人の笑顔、家族全員の集合写真、思い出深い記録
- 処分写真:ピンボケ、重複、誰が写っているかわからない写真
迷った写真は3つの箱に分類
判断に迷う写真は、無理に決めずに一時保留するのがコツです。
- 残す:確実に残したい写真
- 処分:不要と判断した写真
- 保留:後日改めて見直して判断する写真
迷ったときは、家族や親戚に確認しながら決めるのも安心です。
大切な写真をずっと綺麗に残す、デジタル化の手順

大切な写真は、デジタル化と正しい保管を組み合わせることで、長期的に安心して残せます。
デジタル化の主な方法と比較
| 方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 参考リンク |
|---|---|---|---|---|
| スマホアプリ (例:Googleフォトスキャン) |
スマホのカメラで撮影し、歪み補正して保存 | 無料・簡単・どこでもできる | 大量写真は時間がかかる | Googleフォトスキャン |
| 家庭用スキャナー (例:EPSON/Canon) |
フラットスキャナーで1枚ずつ高画質スキャン | 細部まで鮮明・色補正が可能 | 機器購入や設置が必要 | EPSON公式 |
| 専門業者に依頼 (例:思い出レスキュー) |
写真・ビデオのダビング、デジタル化、データ保存・復元サービス | 高品質・短期間・DVD納品対応 | 費用が発生する(1冊数千円〜) | 富士フイルム公式 |
デジタル化は、劣化の心配がなく、思い出をより安全かつ便利に残すために有効です。
写真の処分・供養・代行サービスの活用法

不要になった写真も、感謝の気持ちを込めて丁寧に処分することが大切です。供養や代行サービスを活用すると、心理的な負担も軽くなります。
家庭でできる処分方法
家庭での処分でも、少しの工夫で安心感が増します。
- 写真は封筒や紙袋に入れて可燃ごみに出す
- 顔写真はシュレッダーをかけると安心
- 大量の場合は数回に分けて処分する
供養やお焚き上げの方法
「そのまま捨てるのは気が引ける」という方には供養が適しています。
- 寺院や神社での合同供養
- 郵送型のお焚き上げサービス(1箱3,000〜5,000円程度)
- 供養証明書が発行される場合もあり安心
代行サービスの選び方
写真整理や供養を代行してくれる業者もあります。選ぶ際は以下を意識します。
- 遺品整理や写真供養の実績があるか
- 個人情報や写真の取り扱いに関するセキュリティ対策
- 料金体系やサービス内容が明確であること
家族と無理なく進めるためのコツと心のケア

遺品写真整理は、家族と協力して進めることで負担が軽くなり、思い出の共有にもつながります。
小さな目標で進めると継続しやすい
作業を細かく区切ると、無理なく継続できます。
- 「今日はアルバム1冊だけ」と小さな目標にする
- 週に1〜2回、2〜3時間程度の作業を目安にする
- 作業後に家族で思い出話を共有する
感情があふれたら休憩する
整理中に感情的になった場合は、無理せず休みましょう。
- 気持ちを家族や友人に話す
- 必要に応じて遺品整理業者やカウンセラーに相談
- 作業を一旦中断し、心が落ち着いてから再開する
よくある質問|遺品の写真整理で悩みやすいポイント
Q1. 写真にカビが生えてしまった場合、どうすればいい?
無理に拭き取らず、まずは風通しの良い場所で乾燥させましょう。湿った状態で触ると画像面が剥がれる恐れがあります。カビが広範囲に及ぶ場合は、専門の写真修復業者に相談するのが安全です。
Q2. 故人が写っている写真を処分するのは失礼になりませんか?
感謝の気持ちを込めて丁寧に処分すれば問題ありません。お焚き上げや供養を通じて心を込めてお別れする方法もあります。
Q3. デジタル化した後、原本は残すべき?
思い出として残したい一部の写真(結婚式・家族写真など)は原本を残すのがおすすめです。データ保存のみの場合は、クラウドや外付けHDDなど複数箇所にバックアップしておきましょう。
Q4. 写真データはどこに保存するのが安全?
Googleフォト(公式サイト)やiCloudなどのクラウド保存のほか、外付けHDDやUSBメモリへの二重保存がおすすめです。災害時にも安心です。
Q5. 家族で意見が合わないときは?
写真の扱いは感情が絡むため、無理に決めず「保留」ボックスを作って後日改めて話し合うのが円満です。
まとめ|故人の写真整理は“心の整理”と向き合う時間
故人の写真整理は、単なる片付けではなく、家族の思い出と心を整える大切なプロセスです。カビ対策やデジタル化、供養を取り入れることで、安心して思い出を残せます。
無理せず、少しずつ、自分のペースで進めてみてください。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。