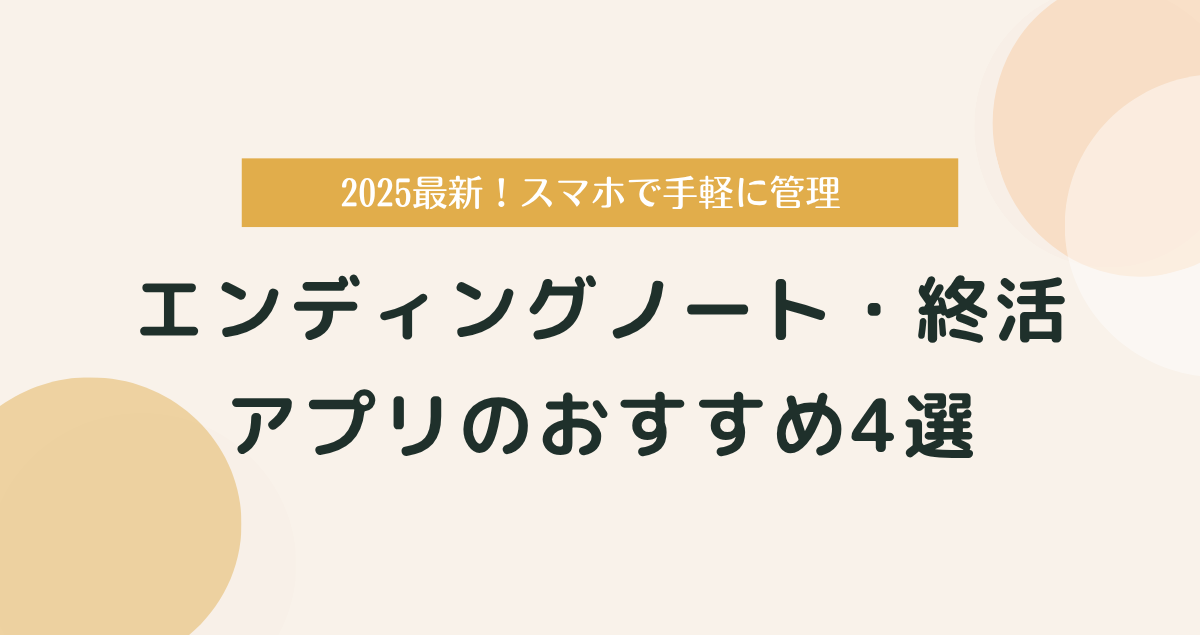「スマホやSNS、ネットバンクやクラウドに保存された“デジタル資産”——どう残し、どう伝えるか悩んでいませんか?」
そんな課題を解決するのが、スマホで使える無料のエンディングノートアプリです。
この記事では、
- 今すぐ使える終活アプリ4選の比較
- アプリと紙の使い分け方
- デジタル遺品を残すためのステップ
をわかりやすく紹介。
若い人にも関係ある“今こそ始めたい終活”の第一歩を、シンプルに解説します。
目次
エンディングノートのアプリと紙の使い分け方は?

アプリのエンディングノートの特徴
いつでもどこでも、最新に保てる
- 外出先・スキマ時間に入力でき、医療情報・連絡先・パスワードなどをすぐ更新。
- 変更箇所が履歴で残るので、「いつ誰が何を直したか」が分かる。
家族と安全に共有できる
- 閲覧権限を家族ごとに設定し、必要な人に必要な範囲だけ見せられる。
- 緊急連絡先や持病など、いざという時にすぐ見つかる。
情報を“まとめて”扱える
- 写真・PDF・通帳メモを添付でき、検索で一発。
- 誕生日や通院日のリマインドで、見直し漏れを防止。
セキュリティ面の安心
- アプリ側の暗号化・2段階認証で、紙より安全なケースも。
- 端末の紛失時はリモートロック/ワイプで被害を最小化。
アプリの注意点
- アカウントの引き継ぎ方法(家族にどう渡すか)を決めておく。
- 端末ロック・バックアップ・2段階認証の初期設定は必須。
- サービス終了リスクに備え、重要ページはPDF書き出しして保管。
紙のエンディングノートの特徴
手書きの温度と説得力
- 家族への手紙・想い・エピソードは、手書きだと読み手に届きやすい。
- 将来読み返すほど、字の温もりが記録の価値になる。
デジタルに不慣れな家族と共有しやすい
- スマホが苦手な親世代でも、開けば読める。
- 取扱説明が不要で、共有のハードルが低い。
長期保管に強い
- 形式が変わっても読み継げる(アプリやOSの仕様変更の影響なし)。
- 重要ページは原本として残し、必要に応じてコピー配布ができる。
紙の注意点
- 更新が手間(書き直し・差し替えが必要)。
- 紛失・盗難・水害や火災などの物理リスクがある。
- 保管場所・合鍵・開封条件など、アクセス設計を決めておく。
迷ったらコレ!エンディングノート用途別の早見表
| 用途 | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 頻繁に変わる情報(パスワード・連絡先・医療情報) | アプリ | 更新・履歴管理が簡単 |
| 気持ち・家族への手紙・写真のコメント | 紙 | 手書きの温度が伝わる |
| 緊急時に家族へ即共有したい情報 | アプリ | 閲覧権限/通知が使える |
| 長く残したい“原本” | 紙 | 形式に依存せず読み継げる |
| 資産一覧・契約更新の控え | アプリ+紙 | アプリで最新管理、紙で要点サマリ |
エンディングノートって本当に必要?若い人にも関係ある理由
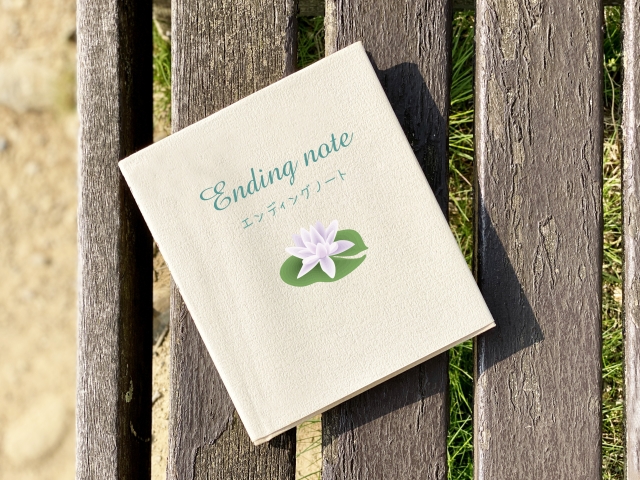
エンディングノートは、将来のもしもに備えて、家族や大切な人が困らないようにするための記録ノートです。高齢者だけでなく、若い世代にも関係のある“いま必要な備え”として注目が集まっています。
特に、スマホやSNS、ネット口座などの「デジタル遺品」は、家族が処理に困る大きな負担の一つ。
紙のノートに書き残すだけでなく、アプリを活用した「新しい終活のカタチ」が広がっています。
エンディングノートに何を書く?最初に書くべき6つの項目
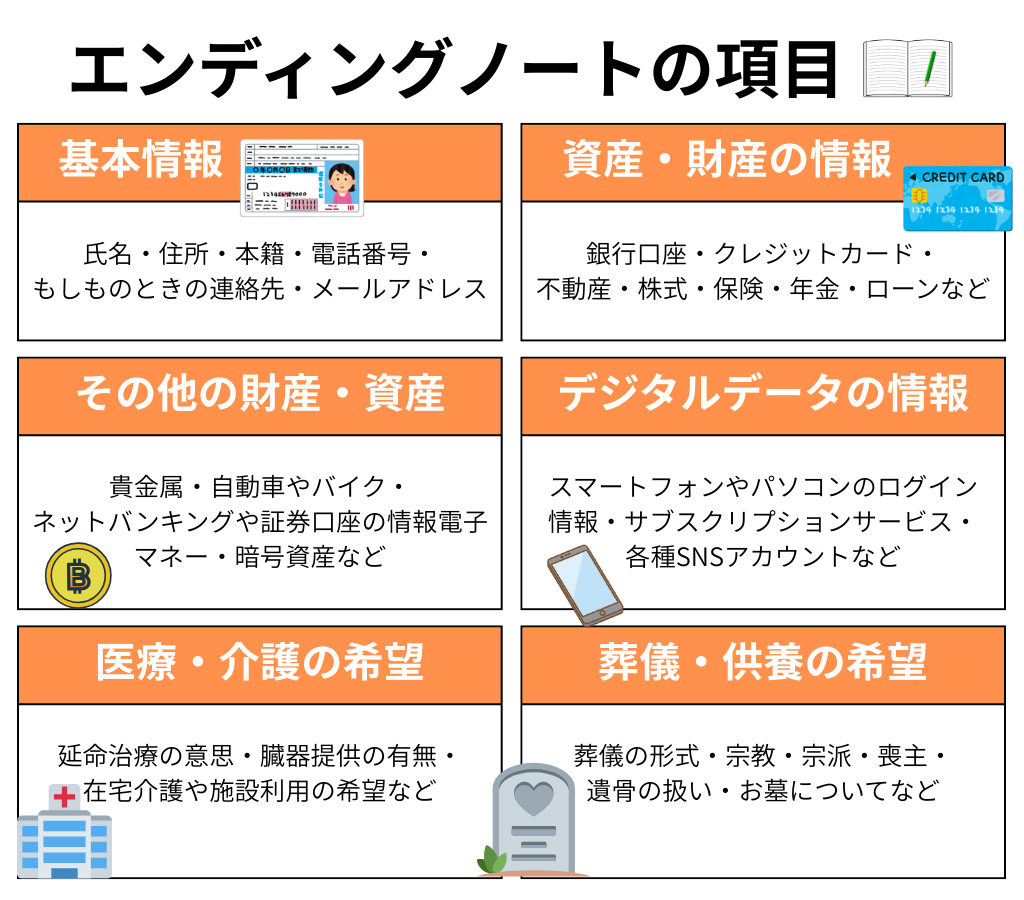
エンディングノートはすべて完璧に書く必要はありません。まずは次のような最低限の項目から始めてみましょう。
- 氏名、生年月日、連絡先などの基本情報
- 緊急時に連絡してほしい人の名前・電話番号
- 医療や介護についての希望(延命治療、臓器提供など)
- スマホ・パソコンのロック解除方法、保管場所
- SNSアカウントと利用状況
- 銀行口座や電子マネーの情報
無料で使えるエンディングノート・終活アプリ4選|特徴比較つき
「エンディングノートを書きたいけれど、紙に書くのはちょっと面倒…」「スマホやパソコンで手軽に管理できたらいいのに」——そんな方におすすめなのが、アプリです。
近年は、操作が簡単で見やすく、家族とも共有しやすいデジタル型エンディングノートが増えてきました。ここでは、デジタル派に人気の終活アプリを厳選してご紹介します。
1. わが家ノート(提供:三菱UFJ信託銀行)

わが家ノートは無料で利用できる終活アプリです。
エンディングノート作成や健康管理、見守り機能など、多彩な機能を搭載されています。
家族との情報共有が可能で、安心して終活を進められます。
主な機能:
- エンディングノート作成
- 健康管理(歩行速度や脳トレスコア、血圧の変化など)
- 見守り機能(ログイン状況を監視し、異常があれば家族に通知)
2. つなぐノート

つなぐノートは、家族と一緒に作るライフノートアプリです。
財産、健康、ID・パスワード、将来の希望など、重要な情報を一元管理することができます。
情報の共有タイミングを設定でき、必要な時に家族に伝えることが可能です。
主な機能:
- ライフノート作成(資産や医療情報、家族への想いなどを記録)
- 共有タイミング設定(タイミングを選んで家族に共有)
3. SOU-SOU(ソウソウ)

SouSouはエンディングノート機能に加え、デジタル手紙機能やメモリアルページを搭載した終活アプリです。
時間を超えて想いを伝えることができる、新しい形の終活アプリとなっています。
主な機能:
- エンディングノート作成
- デジタル手紙機能(指定した相手に、特定のタイミングでメッセージを送信)
- メモリアルページ(家族や友人が故人へのメッセージや写真を投稿できる追悼ページ)
4. わたしの未来 終活準備ノート

わたしの未来-終活準備ノートは、終活の情報収集とエンディングノート作成を一つのアプリで実現しています。
日記や健康管理にも活用でき、日常生活に取り入れやすいのが特徴です。
主な機能:
- エンディングノート作成
- 終活情報の提供(終活に関する記事や情報を定期的に配信)
- 日記・健康管理(毎日の気分や歩数などを記録)
| アプリ名 | 主な特徴 | 家族共有 | 特長的な機能 |
|---|---|---|---|
| わが家ノート | 健康管理・見守り | ◯ | ログイン監視通知 |
| つなぐノート | ライフノート+暗号化 | ◯ | 共有タイミング設定 |
| SOU-SOU | メモリアル・手紙 | ◯ | 時間指定メッセージ |
| わたしの未来 | 終活情報+日記 | × | ニュース連携・記録機能 |
アプリを使うメリットは?
- スマホで完結できるから、日常に取り入れやすい
- 家族や信頼できる人とスムーズに共有できる
- 紙のノートと違い、更新・修正がカンタン
- 写真やメッセージなど、感情を込めた記録も残せる
おすすめの終活・エンディングノートの使い方
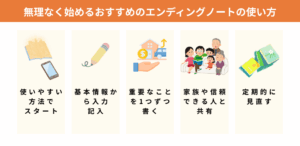
最初から完璧を目指す必要はありません。以下のステップに沿って、少しずつ始めてみましょう。
ステップ1|使いやすい方法を選ぶ(アプリ or 紙)
ライフスタイルに合わせて選びましょう。手軽さ重視ならアプリがおすすめ。
アプリに抵抗がある方や手書きでじっくり向き合いたい方には、紙のテンプレートもおすすめです。
- 基本情報・医療・SNSなど最小限+αの構成からスタート
- 各ページに例文・書き方のヒント付きのテンプレートがおすすめ
ステップ2|基本情報から入力・記入
名前や連絡先など、書きやすいところからスタート。慣れてきたらパスワード情報も。
ステップ3|重要なことを1つずつ書く
医療の希望、SNSの取り扱い、資産情報など、自分が「大事」と思うことから始めましょう。
終活を始めるときに大切なのは「完璧を目指さないこと」です。
- 通帳や保険証券をひとまとめにする
- パスワードをノートやアプリに控える
- 医療の希望(延命治療など)をメモしておく
どれか1つでも行動に移せたら、それは立派な第一歩です。
ステップ4|家族や信頼できる人と共有
アプリなら共有設定、紙なら保管場所や誰に伝えるかを決めておくと安心です。
いざというときに「誰に相談すればいいのか」「どこに何があるのか」がわかるだけで、家族の不安は大きく減ります。
ステップ5|定期的に見直す
年に1回のタイミング(誕生日など)を決めておくと、情報更新が習慣化します。
よくある質問(FAQ)
Q. スマホに保存するのは安全ですか?
→アプリによっては高度な暗号化や2段階認証が導入されており、紙より安全なケースもあります。パスワードやロック解除方法がしっかり設定されていれば、デジタルでも十分安心して管理できます。
Q. アプリと紙、両方使ってもいいの?
→もちろんOKです。たとえば基本情報やパスワード管理はアプリ、気持ちや家族への手紙は紙のノートにといった使い分けが効果的です。利便性と温かみの両立が可能です。
Q. 親にも勧めたいけど、どう伝えれば?
→「突然倒れたときに家族が困らないように」「災害や認知症に備えて」といった“家族を守る理由”を丁寧に伝えるのがポイントです。スマホが使えない方には、紙のテンプレートを一緒に書いてみるのも良い方法です。
まとめ|今のうちにエンディングノートを始めよう
エンディングノートはもはや年配の人だけのものではありません。誰でも今日から始められる終活の第一歩。
まずは1つのアプリやテンプレートから、あなたに合った方法で記録をスタートしてみてください。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。