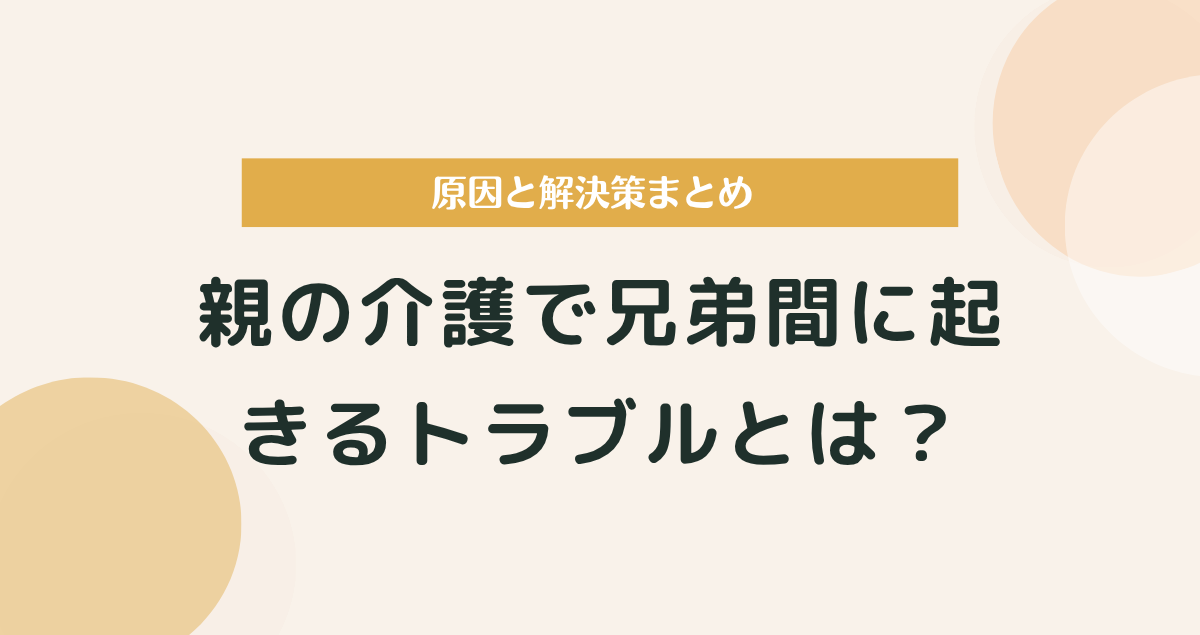親の介護が必要になったとき、本来は支え合うはずの兄弟姉妹の間で、思わぬトラブルが起きてしまうことがあります。
「なぜ自分だけが介護しているのか」「費用をめぐって不公平に感じる」——そんなモヤモヤが積み重なり、関係がこじれてしまうケースも少なくありません。
この記事では、親の介護にまつわる兄弟間トラブルの典型例や原因、そしてトラブルを避けるためにできる工夫や考え方をわかりやすく紹介します。
目次
親の介護で起きやすい兄弟間トラブル5つのパターン

介護の現場では、兄弟姉妹間のすれ違いや誤解から深刻なトラブルが発生することがあります。ここでは、実際に起こりやすい問題とその背景を具体的に見ていきましょう。
1. 介護負担が一方に集中するケース
よくある状況
- 長男・長女だけが介護を担っている
- 実家に近い兄弟にすべて任せきり
- 仕事を辞めて介護に専念する人がいる一方で、他の兄弟は何もしない
トラブルの実例
「私は仕事を辞めて母の介護をしているのに、県外の兄は月に1回電話をかけるだけ。それなのに母は『お兄ちゃんが忙しいのに電話をくれて』と喜んでいる。不公平すぎる」(50代女性)
2. 金銭的な分担と相続問題
よくある状況
- 介護費用の負担割合が不透明
- 相続時に「介護した分を考慮してほしい」と主張
- 親の預貯金の管理をめぐって疑心暗鬼に
トラブルの実例
「父の施設費用を私だけが負担していたのに、相続は法定相続分通り。『介護は長男の義務』と言われ、納得できない」(60代男性)
3. 介護方針をめぐる意見の対立
親の介護方法について兄弟間で意見が分かれることがよくあります。それぞれの価値観や経験の違いから、最善だと思う方法が異なるためです。
よくある状況
- 在宅介護 vs 施設介護の方針対立
- 医療・治療方針への意見の違い
- 介護サービスの利用に対する考え方の相違
4. 親の財産管理への不信
親の認知症進行や体調悪化に伴い、誰かが財産管理を代行する必要が生じます。しかし、その透明性が保たれないと、兄弟間で疑心暗鬼が生まれがちです。
よくある状況
- 通帳やカードの管理者への疑念
- 無断で財産を使っているのではという疑い
- 相続対策に関する情報格差
5. コミュニケーション不足による誤解
介護の状況や各自の事情について十分な情報共有ができていないと、互いの努力が見えずに不満が蓄積されていきます。
よくある状況
- 介護状況の共有不足
- 兄弟間での情報の偏り
- 感謝の気持ちが伝わらない
トラブルの背景にある根本的な3つの原因

介護をめぐるトラブルの多くは、以下の3つの根本原因に集約されます。
原因1:事前準備と話し合いの不足
親が急に倒れたり、認知症を発症したりと、予期せぬ形で介護が始まることは少なくありません。準備期間がないまま介護がスタートすると、誰が何をするかが決まらず、混乱とトラブルを招きます。
具体的な準備不足例
- 親の希望を聞いていない
- 兄弟の生活状況を把握していない
- 介護にかかる費用の想定ができていない
- 緊急時の連絡体制が整っていない
原因2:お互いの生活状況や事情への理解不足
兄弟といっても、それぞれの生活環境や家族の事情は大きく異なります。この違いへの想像力や配慮がないと、深刻なすれ違いが生じます。
理解不足が生む誤解の例
- 「時間があるはず」という思い込み
- 「お金に余裕があるはず」という憶測
- 「親の面倒を見るのは当然」という価値観の押し付け
原因3:感情的な対立とコミュニケーションの悪化
介護は長期間にわたるため、小さな不満も積み重なると大きなトラブルに発展します。特に疲労やストレスがたまると、冷静な話し合いが困難になります。
兄弟間トラブルを未然に防ぐための5つのステップ

問題が起きてからでは遅すぎます。ここでは、今からできる準備と話し合いのコツ、そして兄弟間の協力体制を築くためのステップを解説します。
ステップ1:親の希望・経済状況を”見える化”する
介護方針や資産状況を事前に共有しておくことで、曖昧さや疑念を減らすことができます。
確認すべき項目
- 在宅介護 vs 施設介護の希望
- 年金額・預貯金の概算
- 保険の加入状況
- かかりつけ医・持病の情報
- 延命治療に関する希望
話し合いのタイミング
親が元気なうちに、お盆や正月などの家族が集まる機会を活用しましょう。「将来のことを考えて」という前置きで、自然に話題にできます。
ステップ2:兄弟で役割と費用を明確に分担する
事前に「誰がどの程度関わるか」「費用はどうするか」を明確に話し合っておくことが重要です。
分担方法の例
- 地理的条件による分担:近居の兄弟が日常対応、遠方の兄弟が金銭負担
- 時間による分担:平日・休日・夜間などの時間帯別分担
- 専門性による分担:医療関係者の兄弟が健康管理、事務系の兄弟が手続き担当
ステップ3:定期的な情報共有システムを構築する
効果的な共有方法
- LINE グループでの日常報告
- 月1回の兄弟会議(オンライン可)
- 介護日記の共有
- 医師の説明には可能な限り全員参加
ステップ4:外部サービスの積極活用を検討する
兄弟だけで抱え込まず、プロの力を借りることで負担軽減とトラブル予防につながります。
活用できるサービス
- ケアマネージャーによる介護計画作成
- デイサービス・ショートステイ
- 訪問介護・訪問看護
- 見守りサービス
- 家事代行サービス
ステップ5:「ありがとう」の言葉を意識的に伝える
介護に携わる兄弟への感謝の気持ちを言葉にすることで、関係性の悪化を防げます。
ケーススタディ:協力しながら介護を乗り切った兄弟の実例
実際に兄弟で連携して介護に向き合った家庭の事例をご紹介します。うまくいった背景や工夫から、読者自身が取り入れられるヒントを見つけてみましょう。
A家の場合:兄が現地対応、妹が金銭負担
家族構成
- 母親(85歳、要介護2)
- 長男(58歳、実家から車で30分)
- 長女(55歳、新幹線で3時間の距離)
分担内容
- 兄:実家近くに住み、病院や買い物などの実働を担当
- 妹:遠方在住のため、施設費用や訪問介護の支出を補助
成功のポイント
- 事前に「距離による公平な分担」という考え方で合意
- 妹が月1回は帰省し、兄の負担軽減に努める
- 金銭負担の詳細を家計簿アプリで透明化
B家の場合:三兄弟で完全ローテーション制
家族構成
- 父親(82歳、要介護1)
- 長男(60歳)、次男(58歳)、三男(55歳)すべて県外在住
分担内容
- 3人兄弟で1ヶ月交代で実家に帰省し、在宅介護を分担
- 交通費・休業手当も3等分にし、不公平感を防止
成功のポイント
- 全員が平等に時間と費用を負担するルール
- 引き継ぎノートで介護状況を詳細に共有
- 月末には3人でオンライン会議を実施
もしトラブルが起きてしまったら?解決のための3つのアプローチ

アプローチ1:第三者を交えた話し合い
感情的になりがちな兄弟だけでは解決が困難な場合、以下の第三者に相談することを検討しましょう。
- ケアマネージャー:介護の専門家として客観的な助言
- 地域包括支援センター:無料相談窓口として気軽に利用可能
- 家族会・介護者の会:同じ悩みを持つ人たちとの情報交換
アプローチ2:法的な解決手段の活用
成年後見制度
親の判断能力が低下している場合、成年後見制度を利用して財産管理の透明性を確保できます。
家庭裁判所の調停
相続や財産分割で合意できない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。
アプローチ3:関係修復のための時間をとる
一時的に距離を置くことも、長期的な関係修復には有効です。介護は長期戦なので、一時の感情で関係を完全に断つのではなく、冷却期間を設けることも大切です。
介護に向けた準備状況チェックリスト
事前に備えておくことで、介護が始まったときに慌てず、兄弟間のトラブルを未然に防げます。以下のチェック項目を活用して、今の準備状況を振り返ってみましょう。
基本情報の整理
- □ 親の介護方針(在宅/施設)が兄弟間で共有されているか
- □ 親の資産状況(年金・預貯金)を把握できているか
- □ 緊急連絡先や主治医など基本情報が整理されているか
- □ 保険証・お薬手帳の保管場所を把握しているか
家族間のコミュニケーション
- □ 兄弟それぞれの生活状況を理解しているか
- □ 介護に関する話し合いの機会を設けているか
- □ 兄弟間の連絡手段が整備されているか
- □ 親の希望を直接聞く機会を作っているか
費用と制度の準備
- □ 今後の介護費用について概算しているか
- □ 介護保険制度について基本的な知識があるか
- □ 外部サービスの活用について情報収集できているか
- □ 費用分担の考え方について兄弟で話し合っているか
緊急時の備え
- □ 緊急時の連絡体制ができているか
- □ 近所や友人など親の支援ネットワークを把握しているか
- □ 介護が始まった場合の仕事との両立方法を考えているか
チェック結果の評価
- 12項目以上チェック:よく準備できています
- 8〜11項目チェック:基本的な準備はできていますが、さらなる話し合いを
- 7項目以下チェック:今すぐ家族での話し合いを始めましょう
よくある質問(FAQ)
Q1. 親の介護を自分だけがしているのに、兄弟が何もしません。どうすればいいですか?
まずは感情的になる前に、現状を“見える化”することが大切です。介護にかかる時間・費用・心身の負担を具体的に共有し、兄弟に現状を理解してもらいましょう。
それでも解決が難しい場合は、ケアマネージャーや地域包括支援センターなど第三者を交えた話し合いを検討するのがおすすめです。
Q2. 親の介護費用を自分だけが負担している場合、相続で考慮されますか?
介護に要した費用や時間は、原則として法定相続分に自動的に反映されません。
ただし、家庭裁判所の調停などで「特別寄与料」として考慮される可能性があります。
そのため、領収書や支出記録を残しておくことが重要です。
Q3. 親が介護を嫌がって話し合いが進みません。どうすればいいですか?
「介護」という言葉に抵抗を感じる高齢者は多いです。
「将来の安心のため」や「万が一の備え」といった前向きな言葉に置き換えて話を切り出すのが効果的です。
また、話し合いの場は兄弟全員がそろう機会(お盆や年末年始など)を選ぶとスムーズです。
Q4. 遠方に住んでいて介護に参加できない場合、どう協力すればいいですか?
距離がある場合は、金銭的支援や事務手続きのサポートなど、“できる範囲での分担”を意識しましょう。
交通費の補助や介護サービス費用の一部負担も立派な協力です。
オンラインでの情報共有や定期的なビデオ通話も有効です。
Q5. 兄弟間の関係が悪化してしまった場合、修復する方法はありますか?
一時的に距離を置く(冷却期間を設ける)ことも大切です。
感情が落ち着いたら、第三者を交えた再話し合いを検討しましょう。
互いの努力や事情を言葉で伝えることで、誤解が解けるケースも多くあります。
まとめ:今だからこそ、兄弟で「話し合う時間」を持とう
介護は突然始まることが多く、準備不足が兄弟間の摩擦を生みます。親の意向を確認し、兄弟それぞれの状況を理解したうえで、少しずつでも話し合いを進めていくことが、最も効果的なトラブル予防策です。
今すぐできる3つのアクション
- 家族LINE グループの作成:日常的な連絡手段を確保する
- 次の帰省時の話し合い予約:具体的な日時を決めて話し合いの場を設ける
- 地域包括支援センターへの相談:専門家の意見を聞いて現状を整理する
感情的になる前に、冷静に「どう関わるか」「どこまで協力できるか」を話し合うことで、家族の絆を守ることにもつながります。
親の介護は誰にでも訪れる可能性がある人生の課題です。兄弟間のトラブルを避けて、みんなで支え合える関係を築くために、小さな一歩からでも今できる準備を始めてみてください。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。