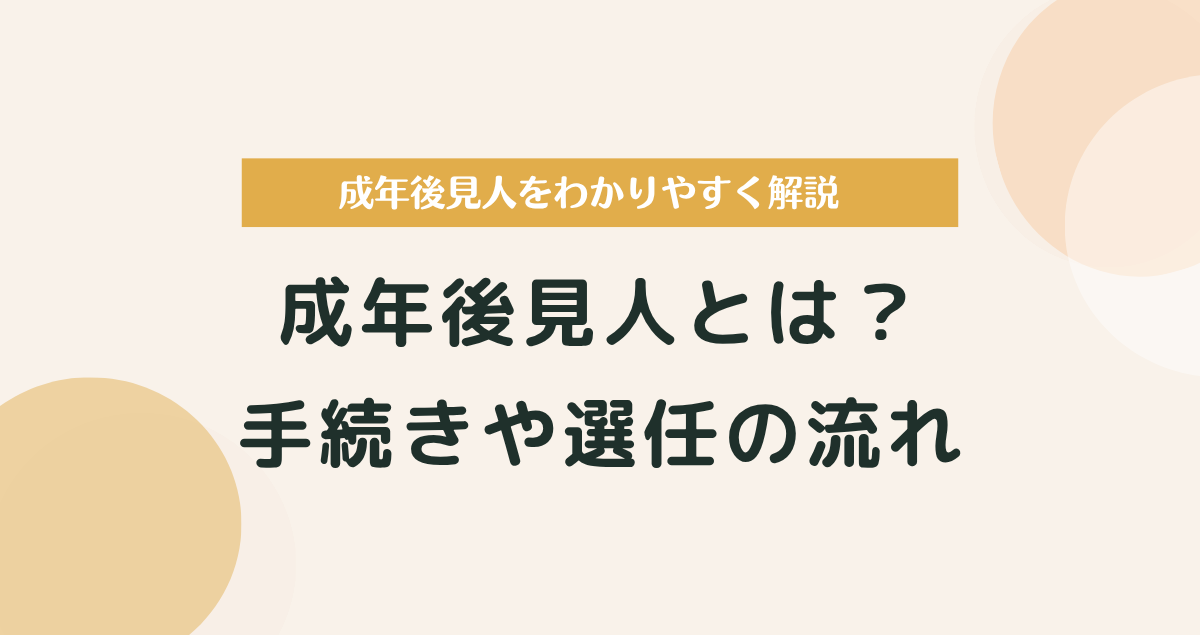親の物忘れが激しくなったり、家族が認知症と診断されたりすると、契約や財産管理の不安が大きくなります。
そんなときに本人を法律的に守る仕組みが成年後見制度です。
本記事では、制度の全体像、手続きの流れ、必要書類と費用、後見人の選び方と役割をわかりやすく解説します。
目次
成年後見制度とは?
まずは成年後見制度の基本を押さえましょう。どんなときに利用でき、どんな種類があるのかを理解しておくことが大切です。
成年後見制度は、判断能力が不十分になった人を支えるための法律上の仕組みです。
家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や契約をサポートし、本人の生活を守ります。
2つの種類
法定後見制度: すでに判断能力が低下している場合に家庭裁判所が後見人を選任します。
任意後見制度: 判断能力があるうちに信頼できる人と契約し、将来に備える制度です。
利用の流れ(申立て〜開始まで)
成年後見制度を実際に利用するには、家庭裁判所への申立てから始まります。ここでは手続きのステップを順番に整理します。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い、審理を経て後見人が選任されます。
標準的には3〜4か月程度、鑑定が必要な場合は半年程度を見込みます。

- 事前準備(1〜2週間)
本人の状況を確認し、成年後見制度を利用すべきか家族で話し合います。
必要書類のリストアップや、弁護士・司法書士など専門家に相談する準備を行います。 - 書類収集(2〜4週間)
戸籍謄本や住民票を役所で取得し、医師に診断書を依頼します。
預金通帳、不動産登記簿、保険証券などを集めて財産目録を作成します。 - 家庭裁判所へ申立て(即日)
家庭裁判所に申立書類を提出し、収入印紙・郵便切手などの費用を納付します。
この日から正式に手続きが開始されます。 - 審理(2〜3か月)
裁判所が本人や申立人に面接を行い、必要に応じて精神鑑定を実施します。
候補者の適格性調査も行われます。 - 後見人決定(1〜2週間)
家庭裁判所が後見人を選任し、審判書が送達されます。
選任内容は後見登記され、公的に効力が発生します。 - 後見開始(すぐ)
後見人は財産目録を裁判所に提出し、以降は本人の財産・生活を支援します。
毎年1回、財産管理状況を家庭裁判所に報告する義務があります。
成年後見制度が必要になるケース

では、どんな状況になったときに成年後見制度を検討すべきなのでしょうか。利用が必要となる典型的なケースを紹介します。
認知症で金銭管理ができなくなった高齢者
知的障害のある子どもが成人した後の財産管理
精神障害で契約判断が難しいケース
脳疾患の後遺症で意思疎通が困難な場合
必要書類と準備のポイント
申立ての際には多くの書類を揃える必要があります。特に診断書や財産目録などは不備があると受理されないため、事前準備が重要です。
| 書類名 | 内容 | 発行元 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 申立書 | 制度利用の理由を記載 | 家庭裁判所 | 裁判所ごとに様式が異なる |
| 戸籍謄本 | 本人・申立人の身分確認 | 市区町村役所 | 3か月以内発行のもの |
| 診断書 | 判断能力の有無を記載 | 医療機関 | 家庭裁判所指定の様式必須 |
| 財産目録 | 預金・不動産・保険など | 家族または専門家 | 証憑資料を添付 |
必要書類:法定後見制度とは(手続の流れ、費用)
費用と期間の目安
成年後見制度の利用には、申立てや診断書作成などで費用が発生します。ここでは大まかな目安を表で整理しました。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円 | 申立て手数料 |
| 郵便切手 | 数千円 | 裁判所により異なる |
| 診断書作成費用 | 5,000〜10,000円 | 医療機関により異なる |
| 鑑定費用(必要時) | 5万〜10万円 | 裁判所が鑑定を命じた場合 |
| 専門家報酬(任意) | 10万〜30万円 | 弁護士・司法書士などに依頼した場合 |
継続的にかかる費用
- 親族後見人:無報酬が一般的
- 専門職後見人:月額2〜6万円程度(財産規模により変動)
後見人の役割と責任
後見人には財産や生活に関わる重要な責任があります。就任後の業務内容を理解しておくことで、準備や役割分担がしやすくなります。
財産管理: 預貯金・不動産・年金受給・納税
身上監護: 医療や介護契約の代理
報告義務: 年1回の財産報告を家庭裁判所に提出
よくある質問(FAQ)
最後に、成年後見制度を検討する方からよく寄せられる疑問に答えます。
Q. 後見人は誰が決める?
A. 家庭裁判所が決定します。
候補を記載できますが、最終判断は裁判所です。
Q. 解任は可能?
A. 財産の不適切管理や義務違反があれば申立てで可能です。
Q. 任意後見と家族信託の違いは?
A. 任意後見は代理行為として契約を行います。
家族信託は財産の名義を移して管理する制度です。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が低下した人の生活と財産を守る制度です。
手続きには3〜4か月程度、費用は数万円〜十数万円が目安です。
書類準備と専門家相談がスムーズな進行の鍵となります。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。