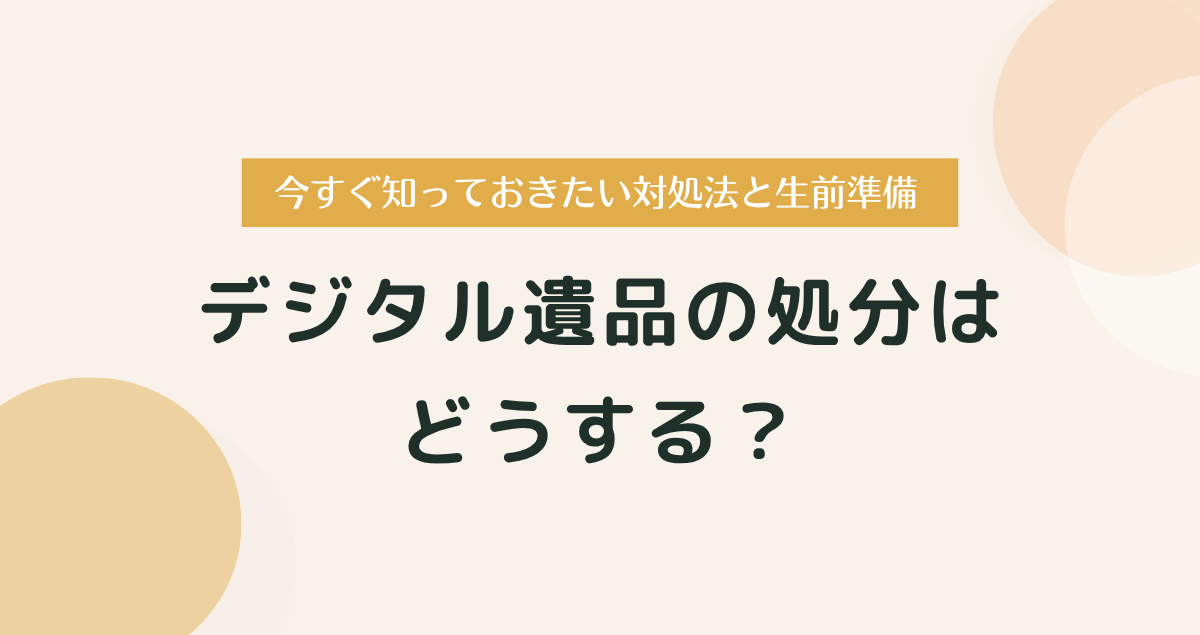スマホ、SNS、クラウド、ネット銀行――私たちの生活はあらゆる情報で「デジタル化」されています。もしその持ち主が亡くなったら、残された家族は何をどう処分すればよいのでしょうか?
この記事では、いま増えている「デジタル遺品」の正しい処分方法と、生前に準備しておくべきポイントを詳しく解説します。
放置による課金トラブルや情報漏洩を防ぐためにも、ぜひ最後までお読みください。
目次
デジタル遺品とは?

デジタル遺品とは、パソコンやスマホなどの端末に加え、次のような「オンライン情報」も含まれます。
- SNSアカウント(Facebook、Instagram、LINE、Xなど)
- クラウド保存された写真や動画
- ネット銀行、暗号資産、オンラインポイント
- 定期購入やサブスクリプションサービス
こうしたデジタル情報は、故人が亡くなった後も「遺された財産・記録」として重要な意味を持ちます。
【危険】放置すると月額数万円の損失も!3つの深刻なトラブル
- 情報漏洩:スマホやPC内のデータが不正アクセスされる危険性
- 課金の継続:Netflix(月額1,980円)、Adobe Creative Suite(月額6,480円)、複数のサブスクで月額2〜5万円が自動更新され続けるケースも
- 家族の混乱:どのアカウントをどう扱えばよいのかが不明で対応に苦慮する
実際の事例:故人のクレジットカードに紐付いていた15個のサブスクリプションが半年間継続され、総額約18万円の損失が発生したケースもあります。
【5ステップ】デジタル遺品の正しい処分手順

ステップ1:アカウントの確認・整理
まずは、故人が利用していたサービスやSNSアカウントを洗い出しましょう。
- ログインIDやメールアドレス
- パスワード(またはヒント情報)
- 登録携帯番号や連携アプリ
探し方のコツ:
- メール:「登録」「確認」「請求」で検索
- ブラウザ:保存されたパスワードを確認
- スマホ:「設定」→「パスワード」から確認
ステップ2:ログインできない場合の対処法【各サービス別詳細手順】
以下に主要サービスごとの対処法を記載します。
Apple(iCloud・iPhone端末)
必要書類:
- 死亡証明書(戸籍謄本等)
- 家族関係を証明する書類
- 申請者の本人確認書類
申請方法: Apple Accountの故人アカウント管理連絡先を追加する方法
Google(Gmail/ドライブ)
必要書類:
- 死亡証明書
- 相続関係の証明書
- 本人確認書類
申請方法: Google アカウント無効化ツール
ステップ3:デバイスの初期化・適正な廃棄方法
初期化前の確認事項:
- 写真・動画のバックアップ
- 連絡先の確保
- 重要メモの保存
初期化手順:
- iPhone:設定 → 一般 → リセット → すべて消去
- Android:設定 → システム → リセット → 工場出荷状態に戻す
- PC:データ完全消去ソフトの使用を推奨
ステップ4:有料サービス・サブスクの解約
確認すべき主なサブスク:
- Netflix、Amazon Prime、Spotify、Adobeなど
- 日経電子版などのニュースサービス
調べ方:
- クレジットカードの明細を確認
- メールで「請求」「決済完了」などで検索
▼あわせて読みたい
ステップ5:最終確認と記録保存
- 削除済みアカウント一覧を作成
- 申請受付番号を控える
- 家族と情報共有
処分は自力?専門業者?選び方の基準

自力で処理する場合のメリット・デメリット
- 費用がかからない
- プライバシーを守れる
- しかし手続きに時間がかかる
専門業者に依頼する場合の費用相場
基本料金:30,000〜100,000円程度。オプション対応で追加料金がかかる場合もあります。
▼あわせて読みたい
よくある質問(FAQ)
Q1. デジタル遺品はいつ処分すればいいですか?
デジタル遺品の処分に「すぐ」という決まりはありません。
まずは故人のスマホやパソコンの中身を確認し、家族にとって必要なデータがないかを見極めてからにしましょう。
特に、写真・連絡先・クラウド上の文書などは、思い出として残しておくケースも多いです。焦らず、整理と確認を優先するのがポイントです。
Q2. パスワードがわからないときはどうすればいいですか?
AppleやGoogleなどの主要サービスでは、故人の死亡証明書や相続関係を証明する書類を提出することで、アカウント管理者の変更や削除が可能です。
ログインできない場合は、各社の「アカウント復旧」や「追悼アカウント」ページから手続きを行いましょう。
詳しい手順は本文中の「ステップ2:ログインできない場合の対処法」を参照してください。
Q3. 有料サービスやサブスクの解約はどう進めればいいですか?
まずは、クレジットカードの利用明細やメール受信履歴から、定期課金されているサービスを確認します。
Netflix、Spotify、Adobeなどのほか、新聞・雑誌なども対象になる場合があります。
利用停止の手続きが完了するまで請求が続くことがあるため、早めの確認と解約申請が大切です。
Q4. デジタル遺品の整理を専門業者に頼むべきケースは?
次のような場合は、専門業者への依頼を検討しましょう。
- パスワードがわからずデータにアクセスできない
- PCやスマホが複数あり、データ量が多い
- 暗号資産やネット銀行の残高など、相続に関わる情報がある
費用の目安は30,000〜100,000円前後。自力で難しいと感じたときは、「情報漏洩を防ぐための安全な処理」をしてくれる専門業者に相談するのがおすすめです。
まとめ|デジタル遺品の処分は”放置しない”が正解
デジタル遺品の処分は、情報漏洩や課金被害を防ぐために不可欠です。
処分対象を明確にし、各サービスで適切な手続きを踏むことが重要です。スマホやSNSを使っているすべての人にとって、今からの準備が大切です。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。