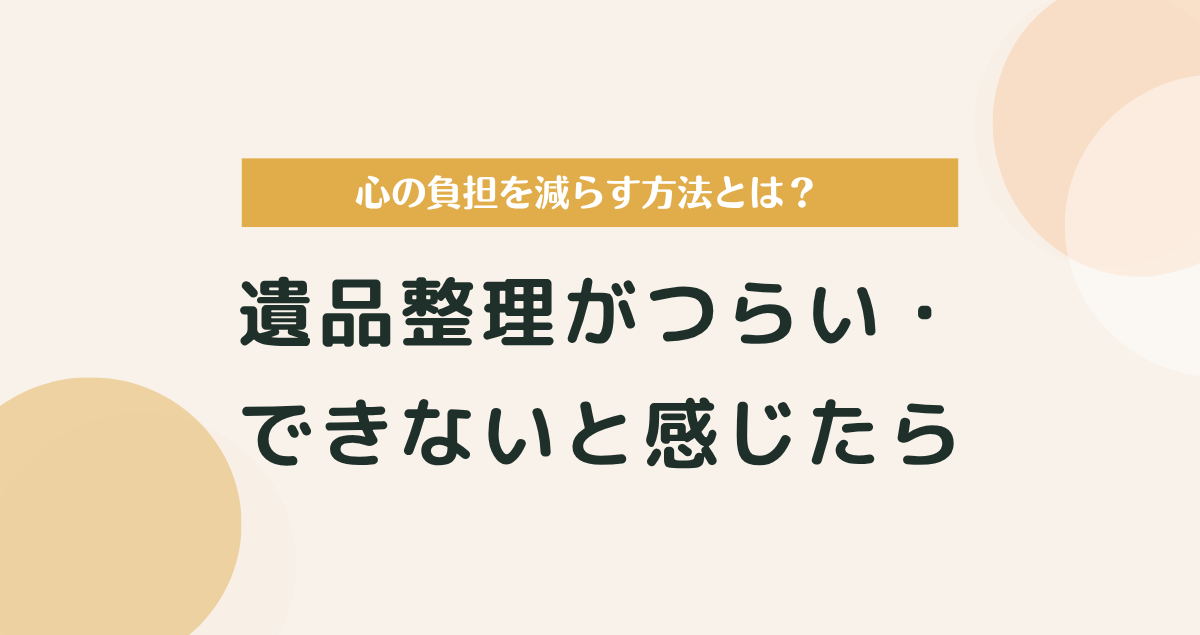「遺品整理をしなければいけないのに、手がつけられない」「片付けるたびに涙が出てしまう」——そんな想いを抱えていませんか?
遺品整理は、心と体の両方に大きな負担がかかる作業です。
本記事では、遺品整理を「つらい」「できない」と感じている方に向けて、その原因とストレスを減らす解決策を丁寧に解説します。
目次
なぜ遺品整理は「つらい」「できない」と感じるのか

遺品整理は単なる片付けとは異なり、感情・体力・人間関係すべてに影響を及ぼす大きなタスクです。ここでは、どのような点が「つらさ」「疲れ」につながるのかを4つの観点から整理します。
精神的なつらさ(故人との思い出・喪失感)
遺品に触れるたびに、故人との思い出が蘇るのは自然なことです。
- 写真や衣類、本など、ひとつひとつが思い出と結びついている
- 「捨てる=忘れるようで罪悪感がある」と感じる
この「手放すこと」と「故人を大切に思う気持ち」の間で葛藤し、感情的に大きな負担を抱えてしまいます。
罪悪感を感じるのは自然なことです。物を手放すことと、故人への愛情は別物だということを覚えておいてください。
肉体的な疲れ(大量の荷物・重労働)
遺品整理は想像以上に重労働です。
- 家具や家電の運搬
- 大量の仕分け・ゴミの分別・搬出作業
特に高齢の親の遺品整理などでは、物量が多く一人で対応しきれないケースもあります。
時間的・経済的プレッシャー
故人の住まいの退去期限や相続・名義変更の関係で、遺品整理に時間制限がある場合もあります。
- 「◯日までに片付けなければならない」
- 「費用がかかるため早く終わらせたい」
焦りがつらさに拍車をかけてしまいます。
家族との意見の相違によるストレス
遺品整理において「残すもの/処分するもの」の判断で家族と意見が食い違うことはよくあります。
- 「これは絶対に残したい」
- 「いや、もう必要ない」
こうした衝突が、精神的なストレスをより深刻にします。
遺品整理のつらさを軽減するための4つの具体的対策

つらい・つかれると感じるとき、心身を守るための選択肢は確かに存在します。ここでは、すぐに実践できる4つの方法を紹介します。
① 一人で抱え込まず、信頼できる人に相談する
つらさの正体が「孤独感」であることも多くあります。
- 兄弟や親戚、親しい友人に「一緒に整理してほしい」と声をかける
- 感情を言葉にするだけでも心が軽くなる
「話すこと」が最初の一歩になります。
② 「手放す・残す」の判断基準を決めておく
迷いが増えると疲れやすくなります。あらかじめ次のような基準を作るのがおすすめです。
使用頻度による判断
- 1年以内に使用:残す
- 3年以上未使用:手放す検討
- 使用頻度不明:保留ボックスへ
思い入れによる判断
- 故人との特別な思い出がある:写真撮影後に手放すか検討
- 故人がよく使っていた実用品:家族で相談
- 装飾品や趣味の品:一つずつ丁寧に判断
保存のしやすさによる判断
- 場所を取らない:残しやすい
- 劣化しやすい:デジタル化を検討
- 維持費用がかかる:現実的に判断
「3ヶ月以内に使っていない物は手放す」など具体的なルールを決めると、選別もスムーズです。
写真や手紙など思い出の品を手放すのがつらいときは、下記の記事を参考にデジタル上に残してから手放す方法もおすすめです。
③ 気持ちが不安定なときは無理をしない
つらいときは「休む」ことも大切な選択です。
- 気持ちが沈んでいる日は作業しない
- 思い出の品は、時期をずらして触れる
気分に波があるのは自然なこと。焦らず進めていきましょう。
疲れたときの対処法チェックリスト
- 深呼吸を3回する
- 15分程度の散歩をする
- 温かい飲み物を飲む
- 信頼できる人に電話をする
- 今日は作業を終了する
④ 専門家(遺品整理士・生前整理アドバイザー)に相談する
第三者の視点が入ることで、負担が一気に軽くなることもあります。
- 仕分けの代行や不要品の処分
- 供養の手配や不動産整理まで対応
「全部やらなくていい」という安心感が得られます。
専門業者の費用相場
- 1K・1DK:3万円〜8万円
- 2DK・2LDK:7万円〜20万円
- 3DK・3LDK:15万円〜40万円
- 4LDK以上:20万円〜60万円
無料で利用できるサービス
- 自治体の高齢者支援窓口での相談
- 遺品整理士認定協会の電話相談
- NPO法人の情報提供サービス
段階的なアプローチ:時間軸で考える遺品整理

今日できること(30分程度)
最初の30分でやること
- 故人の部屋を見て、全体の物量を把握する
- 明らかなゴミ(期限切れの食品など)を3つ処分する
- 「残すもの」「処分するもの」「保留」の3つの箱を用意する
- 家族や親戚に「一緒に整理してほしい」と連絡する
- 今日の気持ちを日記やメモに書き出す
今週できること
- 衣類を「残す」「寄付する」「処分する」に分ける
- 書籍や雑誌の仕分けを行う
- 大型家具・家電の処分方法を調べる
- 地域の粗大ゴミ回収日を確認する
- 遺品整理業者3社に見積もりを依頼する
今月できること
- 重要書類(保険証券、通帳など)を整理する
- 写真をデジタル化する
- 家族で形見分けの話し合いをする
- 不動産の名義変更手続きを開始する
- 供養が必要な品物の手配をする
遺品整理と並行して必要な手続きをまとめた家族が亡くなったらやることリストも確認しておくと安心です。
ストレスを少しでも減らすために「知っておきたいこと」

「今は動けない」と感じている方へ向けて、知識として備えておくべきポイントをまとめました。
遺品整理のタイミングに正解はない
「いつまでにやらなければならない」という明確な決まりはありません。
- 賃貸退去などの事情がない限り、無理に期限を決める必要はない
- 「気持ちが整ってから始める」でも問題ありません
人によって進むペースが違うことを尊重しましょう。
悲しみの段階と遺品整理のタイミング
グリーフケアの観点から、悲しみには以下の段階があります:
- 否認・無感覚の段階:まだ現実を受け入れられない
- 怒り・抗議の段階:「なぜこんなことに」という気持ち
- 取引・願望の段階:「もしも」という思いが強い
- 抑うつ・絶望の段階:深い悲しみに包まれる
- 受容・再生の段階:現実を受け入れて前に進む
遺品整理を始めるのに適しているのは、4段階目後半から5段階目です。無理に早く始める必要はありません。
相続・不動産・供養との関係
遺品整理は、相続や供養とも深く関わっています。
- 「不要な物を処分すれば終わり」ではない
- 遺産分割協議、仏具・遺骨の扱いなどが発生するケースも
こうした手続きについては、行政や司法書士への相談も視野に入れておくと安心です。
相談できる公的・民間のサポート一覧
困ったときには、次のような支援機関があります。
- 地方自治体の福祉課や高齢者支援窓口
- 遺品整理士認定協会
- NPO法人の整理支援サービス
- 終活・相続の専門家(FP・行政書士など)
「誰に聞けばいいかわからない」と思ったら、LINEで相談できるサービスも活用できます。
よくある質問(FAQ)
Q1: 遺品整理を始めるタイミングがわからない
A1: 明確な決まりはありません。気持ちの整理がついてから始めても大丈夫です。賃貸の退去期限など具体的な事情がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。
Q2: 家族と意見が合わない時はどうすればいい?
A2: まず、それぞれの思いを聞き合う時間を作りましょう。感情的になりやすい場合は、第三者(専門家や親戚)に立ち会ってもらうのも効果的です。
Q3: 費用を抑えて遺品整理をしたい
A3: 自治体の支援制度、NPOの無料相談、リサイクル業者の活用などを検討してください。全てを業者に頼まず、できる部分は自分たちで行うことでコストを抑えられます。
Q4: 思い出の品を処分するのがつらい
A4: 全部残す必要はありません。写真に撮って記録に残したり、一部だけを厳選して保管したりする方法があります。「物を手放すこと」と「故人を忘れること」は別です。
Q5: 一人で遺品整理をするのが不安
A5: 一人でやる必要はありません。家族、友人、専門家、いずれかの力を借りてください。話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になります。
遺品整理を始める前の準備リスト
- 心の準備ができているか確認する
- 手伝ってくれる人を1人以上見つける
- 作業道具を準備する(軍手、マスク、段ボール箱、ゴミ袋など)
- 地域のゴミ分別ルールを確認する
- 重要書類の保管場所を決める
- 写真やビデオの保管方法を決める
- 時間に余裕をもったスケジュールを組む
- 疲れた時の対処法を決めておく
まとめ|「つらい」と感じるあなたへ伝えたいこと
遺品整理が「つらい」「つかれる」のは、あなただけではありません。その理由には、精神的負担・物理的疲労・家族間の衝突・情報の複雑さなど、いくつもの側面があります。
まずは「全部自分でやらなければいけない」という思い込みを手放すこと。そして、信頼できる人やツールの力を借りながら、少しずつ進めていくことが大切です。
今日から始められる小さな一歩
- 誰かに「つらい」気持ちを話してみる
- 故人の部屋を見て、全体像を把握する
- 明らかなゴミを3つだけ処分する
- 「今は休んでもいい」と自分に言い聞かせる
小さな達成感を積み重ねることで、きっと前に進むことができます。あなたのペースで、無理をしないで進めてください。故人もきっと、あなたが笑顔でいることを一番に願っているはずです。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。