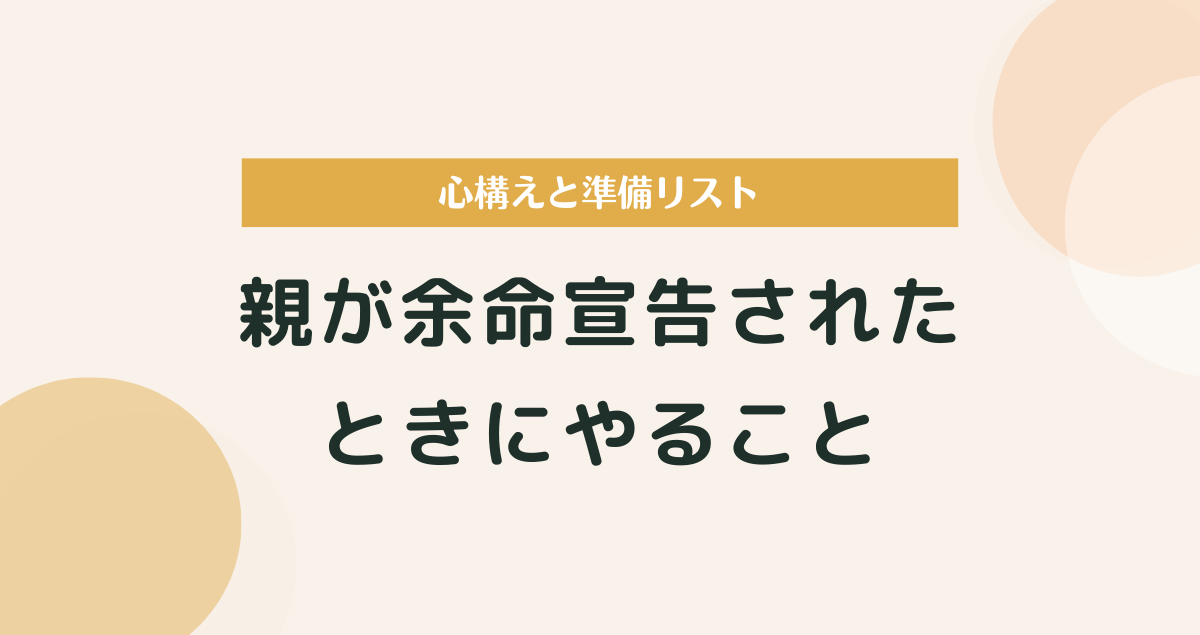親が余命を宣告されたとき、心の整理がつかず「何から始めればよいのか分からない」と悩む方は少なくありません。
ショックや不安の中でも、できることから一つずつ進めることで、残された時間をより大切に過ごせます。
この記事では、親が余命宣告を受けたときに家族ができることを、医療・生活・法的・心のケアの観点から整理して解説します。
親の余命宣告を受けたときの最初の心構え

余命宣告を受けると、動揺や混乱の中で「どう振る舞えばよいのか分からない」と感じる人も多いでしょう。
最初に大切なのは、心の準備を整えることです。
感情を抑え込むのではなく受け止め、次に進むための視点を持つことが支えになります。
ショックを受けるのは自然なこと
余命宣告は家族にとって非常に重い現実です。
動揺や悲しみ、時には怒りや罪悪感を感じるのも当然であり、自分を責める必要はありません。
完璧を求めすぎず、まずはその気持ちを受け入れることから始めましょう。
焦らず「今できること」を一つずつ
突然の宣告に動揺しても、時間は限られています。
すべてを一度にやろうとせず、優先すべきことを整理し、今日できることから少しずつ取り組む姿勢が大切です。
親の余命宣告後にやること【準備リスト】

余命宣告の後は、日々の生活や将来に向けた準備が急務となります。
焦る必要はありませんが、段階的に「今すぐやること」「数週間で進めること」「長期的に準備すること」を整理すると行動に移しやすくなります。
【緊急】1週間以内にできること
余命宣告を受けて最初の1週間は、医師との情報整理や本人の希望確認など、優先度の高いことから取り組む必要があります。
ここで方向性を決めておくと、その後の準備がスムーズになります。
① 医師からの説明を整理し、治療方針を家族で確認
診断内容や余命の目安、今後の治療の選択肢について、医師にしっかり確認しましょう。
病状の詳しい説明、治療選択肢のメリット・デメリット、今後のスケジュールや通院頻度、セカンドオピニオンの必要性などを整理します。
曖昧な点は遠慮なく質問し、家族間で情報を共有することが重要です。
② 本人の希望を丁寧に聞く(療養場所・治療の程度)
在宅療養を望むのか、延命措置を希望するのかなど、本人の価値観や意思を確認することが最優先です。
どこで過ごしたいか、延命治療への考え方、痛みのコントロール、最期に会いたい人ややりたいことなどを話し合いましょう。
緩和ケアは、入院・外来・在宅のいずれの場でも受けることができます。
参考:国立がん研究センター がん対策情報センター『がんと療養シリーズ 緩和ケア』第3版第2刷(2021年6月)
本人の希望を尊重することが、残された時間をより良いものにする鍵です。
【重要】1ヶ月以内に進めること
宣告から少し落ち着いた段階では、経済面や療養環境の整備を進めていきましょう。
この時期に基盤を整えておくことで、介護や生活の負担を減らすことが可能です。
③ 保険・医療費・経済面の確認と手続き
経済的な負担は大きな課題となります。
生命保険の給付内容や請求、高額療養費制度、介護保険サービス、傷病手当金、医療費控除などを早めに確認しましょう。
④ 生活環境を整える(在宅療養・施設利用の準備)
本人の希望に応じて療養環境を整えます。
在宅療養ならバリアフリー化や訪問医療、福祉用具レンタル。
施設利用なら見学や手続きを早めに行いましょう。
⑤ 家族の役割分担を明確にする
介護、通院付き添い、金銭管理など、誰が何を担うのかを話し合いで決めておくことでトラブルを防げます。
主要な介護担当者、付き添い当番、金銭管理の責任者、緊急時の連絡体制を整理しましょう。
【中長期】数ヶ月かけて準備すること
少し時間が経つと、相続やデジタル資産整理など長期的な課題に目を向ける余裕も出てきます。
ここでは将来の安心につながる準備を進めましょう。
⑥ 相続・遺言・エンディングノートの準備
財産に関する争いを防ぐため、本人の意思を明確にしておきます。
遺言書作成、公正証書遺言、エンディングノート記入、重要書類整理を進めましょう。
⑦ デジタル遺品の整理
現代特有の準備として、デジタル資産の整理も必要です。
SNSアカウント、ネット銀行・証券、サブスク、パスワード、PC・スマホデータを計画的に整理しましょう。
⑧ 「一緒に過ごす時間」を何より大切にする
実務的なことに追われがちですが、親子として過ごす時間を最優先にしましょう。
思い出話や感謝の言葉を伝え、写真・動画を一緒に見たり、好きなことを共に楽しむ時間を作ってください。
余命宣告後の心のケアとサポート

実務的な準備と同じくらい大切なのが、心のケアです。
本人も家族も精神的負担を抱えやすいため、支え合える環境を整えることが欠かせません。
本人の心のケア(不安・孤独感への対応)
病気への不安や孤独感は大きな負担です。
話を聞く時間を作る、適度なスキンシップ、一人にしない時間、緩和ケアやカウンセリングを活用しましょう。
家族の心のケア(相談窓口・サポートグループ)
家族も精神的に疲弊しやすいため、一人で抱え込まないことが大切です。
地域包括支援センターや患者会、カウンセリングを利用しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 余命宣告を受けたあと、まず何をすればよいですか?
まずは医師の説明を整理し、家族で共有することから始めましょう。
治療方針や本人の希望(療養場所・延命治療の有無など)を確認し、次に経済面や生活環境の準備を進めるのが基本です。
Q2. 本人が余命を知らない場合、家族はどう対応すればいいですか?
本人への告知は非常にデリケートな問題です。医師と相談し、本人の性格や希望を踏まえて慎重に判断しましょう。
無理に伝えるよりも、安心して過ごせる環境づくりを優先する選択もあります。
Q3. 介護や医療費が心配なとき、どんな制度が使えますか?
高額療養費制度、介護保険、傷病手当金、医療費控除などの公的制度が利用できます。
申請時期や条件によって支給額が異なるため、早めに社会福祉協議会や地域包括支援センターに相談しましょう。
Q4. 心がつらいとき、どこに相談すればいいですか?
家族の心のケアも大切です。
地域包括支援センターや病院内の相談員、グリーフケア団体などでカウンセリングを受けられます。
一人で抱え込まず、話を聞いてもらうことが回復への第一歩です。
まとめ|「できることリスト」を決めて一歩ずつ
親の余命宣告を受けると、大きな不安と悲しみに直面します。
しかし医療方針の確認、本人の希望の尊重、経済面・相続の準備、生活環境の整備、心のケアを整理し、無理のない範囲で取り組むことで後悔の少ない時間を過ごせます。
すべてを完璧にこなす必要はありません。
行動の第一歩として、今日できることを一つ決めることから始めましょう。
そして何より、親との時間を大切にすることを忘れないでください。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。