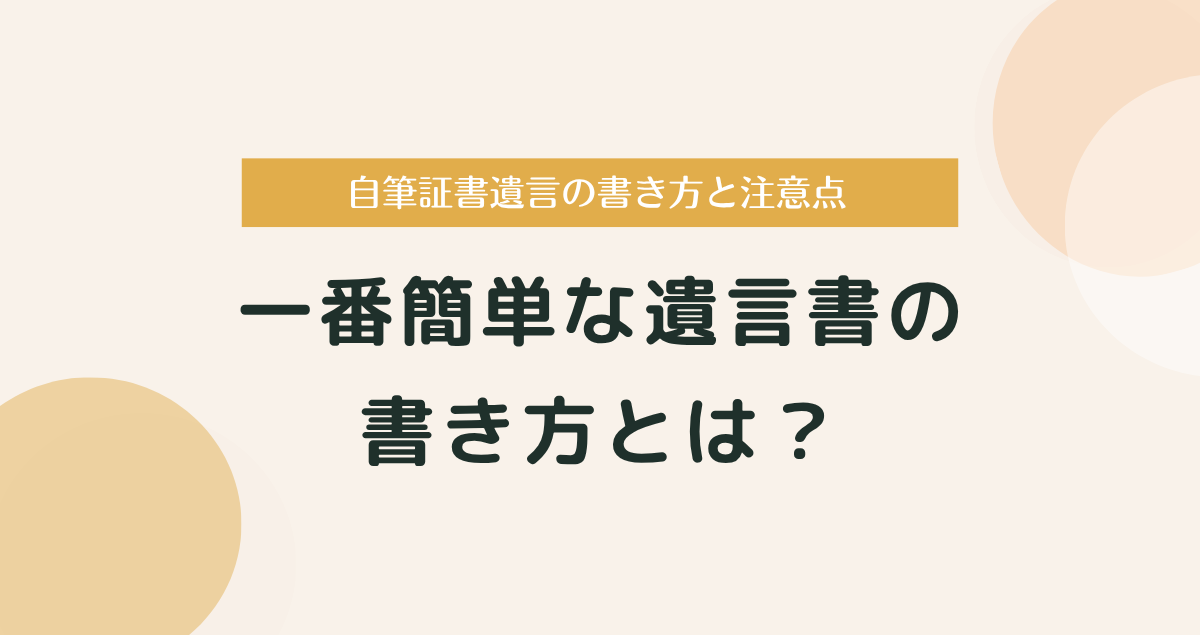「遺言書を書きたいけれど、できるだけ簡単に済ませたい」
そんな方におすすめなのが自筆証書遺言です。
この記事では初心者でも失敗せずに作れる簡単な遺言書の書き方を、シンプルな文例や作成のコツとあわせて紹介します。
目次
簡単な遺言書は「自筆証書遺言」
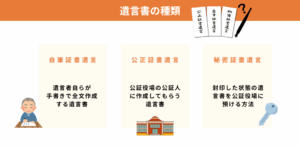
最も手軽に作れる遺言書は、本人が自分で手書きする「自筆証書遺言」です。
公証人の立ち会いは不要で、思い立ったときにその場で作れる手軽さが魅力です。
公正証書遺言との違い
- 公正証書遺言は安全性が高いが、費用と手間がかかる
- 自筆証書遺言は費用ゼロで作れるが、形式不備で無効になる可能性がある
自筆証書遺言の基本ルールは法律で決まっている
自筆証書遺言は、誰でも簡単に作れる一方で、法律に定められた形式を守らないと無効になります。
民法第968条および法務省の解説では、次のルールが明記されています。
- 遺言の本文は遺言者が全文を自筆で書くこと
- 日付を特定できるように書くこと(例:「2025年9月18日」/「吉日」は不可)
- 遺言者本人の氏名を自署すること
- 押印をすること(認印でも可。ただし実印を推奨)
これらの条件を欠くと、せっかく作成した遺言書が無効になるおそれがあります。
また、2020年の法改正により財産目録はパソコンで作成できますが、各ページごとに署名・押印が必要です。
初心者でも失敗しない簡単な遺言書の書き方3ステップ

初心者でも迷わず作れる、3つの基本ステップを押さえましょう。
1. 全文は自筆で書く
本文は必ず本人が自筆で書きます。代筆やパソコン印刷では無効です。
財産目録だけはパソコンや印刷が認められていますが、その場合も各ページに署名・押印が必要です。
2. 日付・署名・押印を忘れない
日付は「2025年9月18日」のように特定できる形で書きましょう。「吉日」など曖昧な書き方は無効とされた判例があります。
署名は遺言者本人の自署が必要で、押印は認印でも有効ですが、実印や銀行印を使うと安心です。
3. 間違えたときは正しく訂正
書き間違えた場合は、民法第968条3項に基づき次の方法を守ります。
- 間違えた箇所に二重線を引く
- 近くに正しい文字を書く
- 訂正箇所に押印(同じ印鑑を使用)
- 欄外に「第○行目○字削除○字加入」と署名する
複雑な訂正が必要になった場合は、書き直した方が確実です。
簡単でシンプルな遺言書の文例
遺言書はシンプルでも、法律の条件を守っていれば有効です。ここでは、すぐに使える基本形の文例を紹介します。実際に書くときは「日付・署名・押印」を忘れずに記入してください。
全財産を一人に相続させる場合
遺言書 私〇〇〇〇は、下記のとおり遺言する。 第1条 私の有する一切の財産を、長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 第2条 この遺言の執行者として、長男〇〇〇〇を指定する。 令和〇年〇月〇日 東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号 遺言者 〇〇〇〇 ㊞
特定の財産を分ける場合
遺言書 私〇〇〇〇は、下記のとおり遺言する。 第1条 私の所有する下記不動産を妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 所在:東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号 家屋番号:〇番〇号 種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階〇〇.〇〇㎡、2階〇〇.〇〇㎡ 第2条 私の所有する下記預貯金を長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇 第3条 この遺言の執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。 令和〇年〇月〇日 東京都〇〇区〇〇丁目〇番〇号 遺言者 〇〇〇〇 ㊞
「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
- 法定相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)には「相続させる」を使用
- 法定相続人以外(孫・甥姪・友人など)には「遺贈する」を使用
この表現の違いを間違えると、手続きに余分な手間がかかることがあります。相続人以外に財産を渡すときは「遺贈する」と書きましょう。
遺言書を作るおすすめのタイミング
遺言書は「まだ早い」と思っているうちに作っておくのが安心です。健康で判断能力がしっかりしている時に作成しましょう。特に次のようなライフイベントは作成のきっかけになります。
- 結婚・離婚したとき
- 子どもが生まれたとき
- 不動産を購入したとき
- 60歳を迎えたとき
- 家族構成に変化があったとき
一度書いた遺言書も、数年ごとに見直すと安心です。
自筆証書遺言のメリットとデメリット
メリット
- 費用ゼロで作れる
- 公証人なしで、その日のうちに作れる
デメリット
- 形式不備で無効になるリスク
- 紛失や発見されない可能性
- 家庭裁判所で検認が必要(ただし法務局保管なら不要)
よくある失敗と防止策
- 日付の不備
「吉日」と書くと無効になる可能性あり。必ず「2025年9月18日」のように具体的に書く。 - 記載のあいまいさ
不動産は登記簿どおり、預金は銀行名・支店名・口座番号まで正確に。 - 判断能力の不安
元気なうちに作成し、必要に応じて医師の診断書を添付すると安心。
遺言書を安全に保管する方法
自宅保管のリスク
- 紛失、盗難、隠蔽のリスク
- 信頼できる人に預けるか、封印して保管する工夫が必要
法務局の保管制度を利用する
2020年に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、法務局に安全に預けられます。
手数料は1通3,900円。紛失や改ざんのリスクがなく、家庭裁判所での検認も不要になります。
申請に必要なもの
- 遺言書保管申請書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 住民票の写し
- 遺言書
よくある質問(FAQ)
Q1. 自筆証書遺言は本当に費用ゼロで作れますか?
はい。紙とペン、印鑑があれば費用をかけずに作成可能です。
ただし、法務局の保管制度を利用する場合は1通3,900円の手数料が必要です。
Q2. 日付は「令和〇年吉日」と書いても大丈夫ですか?
いいえ。「吉日」など曖昧な表現は無効とされる可能性があります。
必ず「2025年9月22日」のように、年月日を特定できる形で書きましょう。
Q3. 遺言書は自宅に保管しても大丈夫ですか?
自宅保管も可能ですが、紛失・改ざん・発見されないリスクがあります。
確実に効力を発揮させたい場合は、法務局の保管制度を利用すると安心です。
Q4. 一度書いた遺言書は後から書き直せますか?
はい。遺言書は何度でも作り直し可能です。
新しい遺言書が優先されるため、古いものは破棄するか、最新の日付を必ず記載しましょう。
まとめ|初心者でも書ける一番簡単な遺言書
- 自筆証書遺言は費用ゼロで誰でも作れる
- 日付・署名・押印を守れば法的に有効
- 文例を使えばシンプルでも十分
- 保管は法務局制度を利用すると安心
今日からでも、簡単に遺言書の準備を始められます。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。