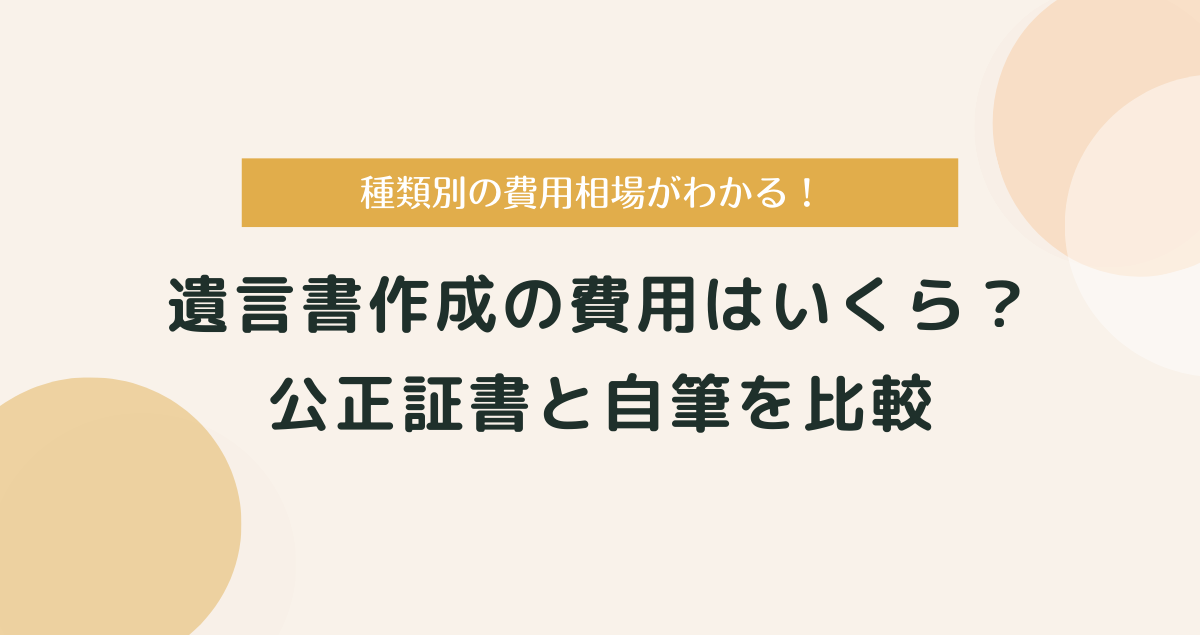遺言書の作成を検討しているけれど、「どの方法を選べばいいの?」「費用はどれくらいかかるの?」と迷っていませんか?
この記事では、遺言書の種類別の費用相場や、専門家に依頼した場合の料金、メリット・デメリットまで簡潔に解説します。
大切な財産を次の世代に確実に引き継ぐための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
目次
遺言書にはどんな種類があるの?
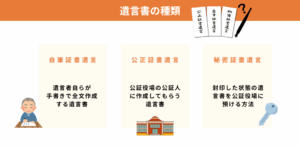
遺言書には大きく分けると自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印する方法です。
自分の意志を反映させるために非常に簡単に作成できる方法ですが、いくつかの重要なポイントを抑えておく必要があります。
自筆証書遺言のメリット
- 費用がかからず手軽に作成できる
- 内容を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 要件不備で無効になる恐れがある
- 紛失や忘れ去られるリスクがある
- 遺言書が勝手に書き換えられるなど改ざんのリスクがある
- 家庭裁判所での検認が必要で手間や時間がかかる
自筆証書遺言の費用と注意点
自筆証書遺言の費用はほぼかかりません。
紙とペンさえあれば誰でも作成することができます。ただし以下の点には注意が必要です。
- すべて自筆で書かなければならない。
- 日付と氏名を記載し、押印が必要。
- 形式不備があると無効になるリスクがある。
- 遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できない。※民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成可能に。
自筆証書遺言の法務局保管制度と手数料
2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」では、法務局に遺言書を預けることができます。
法務省によると、保管申請1件につき3,900円の手数料が必要で、収入印紙で納付します。
また、閲覧や証明書発行の際にも手数料が設定されています。
| 手続名 | 手数料額 | 手続できる方 |
|---|---|---|
| 遺言書の保管の申請 | 3,900円/1通 | 遺言者 |
| 閲覧請求(モニターによる) | 1,400円/1回 | 遺言者・関係相続人等 |
| 閲覧請求(原本) | 1,700円/1回 | 遺言者・関係相続人等 |
| 遺言書情報証明書の交付請求 | 1,400円/1通 | 関係相続人等 |
| 遺言書保管事実証明書の交付請求 | 800円/1通 | 関係相続人等 |
なお、遺言書の撤回や住所変更の届出については手数料が不要です。
手数料はすべて収入印紙で納付し、法務局で購入できます。
(出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」)
公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で証人2名以上の立会いのもと、公証人に遺言の内容を伝えて作成する方法です。
遺言者が遺言書を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを筆記し、遺言書が完成します。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者の死亡後も安全に保管されます。
公正証書遺言のメリット
- 公証人という法律の専門家が遺言書を作成するため、遺言が無効になるリスクが低い
- 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
- 公正証書遺言は法的に有効とされ、遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが不要
公正証書遺言のデメリット
- 遺言書作成時に証人が2名必要
- 公証役場での手続きが必要なため、作成費用と手続きにも時間がかかる
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の手数料は、「公証人手数料令」という政令によって法定されています。
財産の価額に応じて手数料が決まり、法定基準は以下の通りです。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 49,000円+超過額5,000万円ごとに15,000円加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 109,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 10億円を超える場合 | 291,000円+超過額5,000万円ごとに9,000円加算 |
なお、財産を受け取る人ごとに価額を算出して上記基準に当てはめ、合計する形で手数料を計算します。
さらに、以下のような加算・注意点があります。
- 遺言加算:全体の財産が1億円以下の場合、上記金額に13,000円を加算
- 正本・謄本の交付手数料:電子データ発行の場合は各1通2,500円、書面発行は1枚300円
- 病院や自宅で作成する場合:公証人日当(1日2万円・4時間以内1万円)+交通費
これらの費用はすべて政令で定められており、全国共通の基準です。
詳細は、日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料(Q7)」をご確認ください。
専門家に依頼する場合の費用
遺言書をより安全に作成するために、専門家に依頼することも選択肢です。
専門家に依頼する費用の目安
- 弁護士:10万~30万円(相続や法的助言も含む)
- 司法書士:5万~15万円(文案作成、公証役場同行)
- 行政書士:3万~10万円(書類作成、公証役場同行)
専門家への依頼を検討する場合、相続が複雑であったり、大きな資産がある場合には有効です。
遺言書と合わせて検討しておきたい、遺言執行者について
遺言執行者は、遺言者が亡くなった後に遺言の内容を実現するための役割を担います。
遺言執行者の主な業務は以下の通りです。
- 相続財産の調査・目録作成
- 相続人への連絡・遺言内容の説明
- 不動産の名義変更手続き
- 預貯金の解約・分配手続き
- 遺贈がある場合の引き渡し
特に複雑な財産構成の場合や、相続人間でトラブルが予想される場合は、遺言執行者を指定しておくと安心です。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な人物です。費用は以下の通りです。
- 信託銀行:50万~100万円(遺産総額の1~3%)
- 弁護士:30万~70万円(遺産総額の1~3%)
- 司法書士:20万~50万円
遺言執行者としては、信託銀行や弁護士が一般的ですが、親族を遺言執行者に指定する場合もあります。その場合、費用は抑えられますが、親族間での調整が必要です。
よくある質問(FAQ)
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきですか?
「費用を抑えたい」「手軽に作りたい」なら自筆証書遺言がおすすめです。ただし、形式不備で無効になるリスクがあるため、確実性を求める場合や財産が多い場合は公正証書遺言を選ぶと安心です。
遺言書を作るタイミングはいつがよいですか?
遺言書は資産状況や家族構成に変化があったときに作成・見直すのが理想です。たとえば、結婚・出産・不動産の購入・退職・大きな医療費が発生したときなどがタイミングです。
遺言書を変更・取り消すことはできますか?
はい、遺言書は何度でも書き直すことが可能です。最新の日付の遺言が有効になります。生活状況や資産に応じて定期的に更新するのがおすすめです。
専門家に依頼するメリットは何ですか?
専門家に依頼すると、法的に無効にならないよう形式を整えてもらえるだけでなく、相続税対策や遺産分割トラブル防止の助言も受けられます。特に資産が多い方や相続人同士で揉める可能性がある場合に有効です。
まとめ|自分に合った遺言書の作成で、安心できる未来を
遺言書は、残された家族が安心して相続を進めるための大切な準備のひとつです。
種類ごとの特徴や費用、注意点を把握したうえで、自分に合った方法を選びましょう。
特に財産が多い・相続が複雑なケースでは、公正証書遺言や専門家への依頼を検討するのがおすすめです。
まずは「将来の不安を減らす第一歩」として、どんな内容を残したいか、どの方法が自分に向いているかを考えてみてください。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。