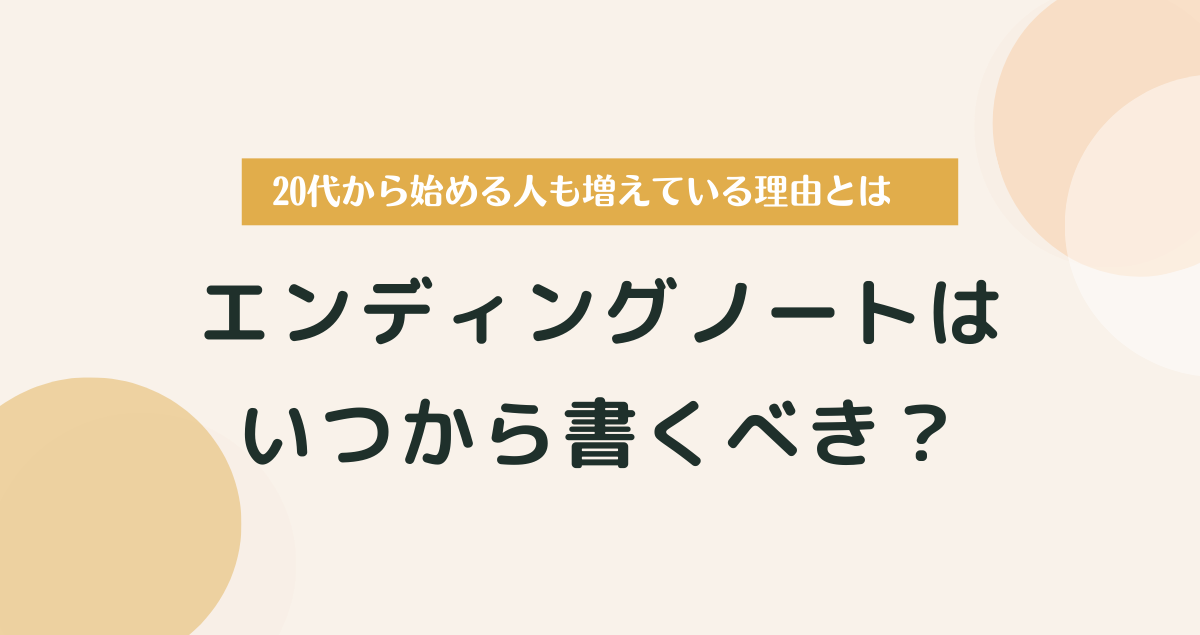エンディングノートと聞くと「高齢者が書くもの」という印象を持つ方も多いでしょう。
「いつから始めるべき?」という問いに明確な正解はありませんが、この記事では年代別の最適なタイミングや、書きやすい始め方、注意点などを通して、自分に合った”始めどき”を見つけるためのヒントをお届けします。
目次
エンディングノートはいつから書くべきか?
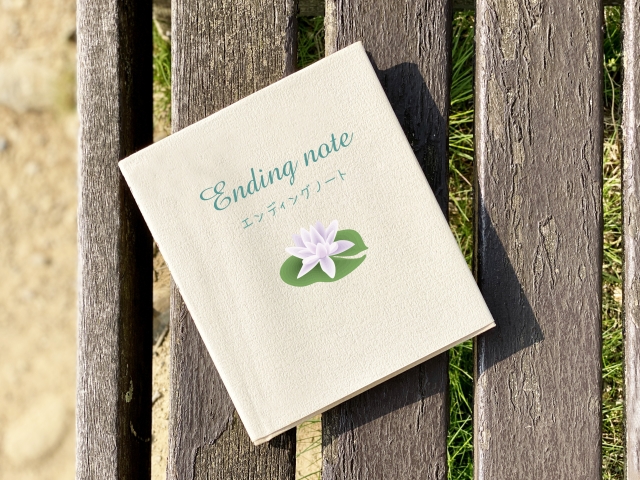
エンディングノートに「正しい始めどき」はありませんが、後回しにしてしまうと、いざというときに間に合わないことも。
大切なのは、今の自分にとって必要なことから始めることです。ここでは、年代やライフイベントに応じた“おすすめの書き始めタイミング”をご紹介します。
エンディングノートを始める年代別の推奨タイミングと具体的メリット
| 年代 | 主なライフイベント | 書いておきたい内容 | 主なメリット |
|---|---|---|---|
| 20代 | 就職・一人暮らし・結婚など | SNSアカウント管理、スマホのロック情報、医療意向のメモ | 不慮の事故・病気時にも家族が対応しやすくなる |
| 30〜40代 | 結婚・出産・住宅購入・親の介護開始 | 子どもの養育方針、保険や資産情報、介護の希望 | 家族への責任が重くなる時期に「もしも」への安心感が得られる |
| 50代〜 | 定年退職・相続経験・親の見送り | 財産の詳細、医療・介護の希望、家族へのメッセージ | 「迷惑をかけたくない」という想いを具体的に残せる |
20代:人生の基盤固めと同時に
最適タイミング:就職・一人暮らし開始・結婚など人生の転換点
重点項目:SNSアカウント管理、スマホのロック解除情報などデジタル遺品の整理、基本的な医療意向
メリット:突然の事故や病気への備え、家族が離れて暮らしている場合の緊急時対応
30代〜40代:責任の重さを実感する時期
最適タイミング:結婚・出産・住宅購入・親の介護開始など
重点項目:子どもの養育方針、保険・資産情報、介護の希望
メリット:家族への責任が重い時期だからこそ、「もしも」の備えで安心感を得られる
50代以降:人生の折り返しとして
最適タイミング:両親の介護や相続の経験、定年退職の意識
重点項目:財産の詳細、医療・介護の詳細な希望、家族へのメッセージ
メリット:「迷惑をかけたくない」という想いを具体的な形にできる
なぜ今、エンディングノートを書くべきなのか?
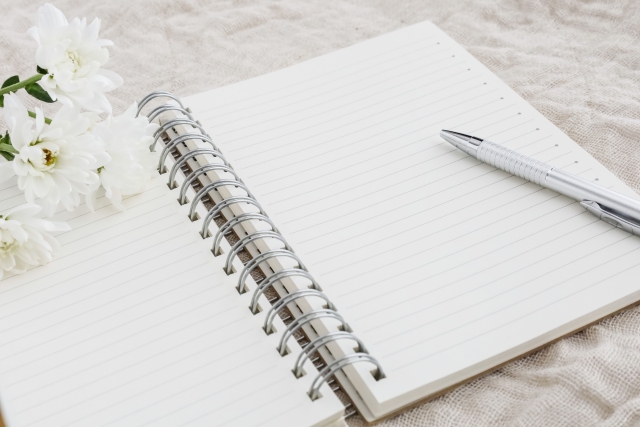
「今はまだ早い」と思っていても、いざという時には準備ができていないという事態も少なくありません。早めに取り組むことで得られるメリットは多くあります。
若いうちに始めると選択肢が広がる
エンディングノートを書くことは、人生の選択肢を確認し、未来の自分に備える行為でもあります。若いうちに始めれば、医療・介護・終末期についての意向を柔軟に見直すことができます。
また、デジタルネイティブ世代特有の「オンライン上の自分」についても整理できるメリットがあります。
40代以降は”人生の折り返し”として書きやすい
親の介護や子育てがひと段落するタイミングで、自身の将来に目を向ける方が増えます。この世代では、「もしものとき家族に迷惑をかけたくない」という意識からエンディングノートを書く方が多いです。
実際に親の終活を経験することで、準備の重要性を実感するケースも多く見られます。
書くことで”備えの安心”が手に入る
記録することで「伝えたかったことが伝わる」安心感が生まれます。メンタル面でも前向きな整理ができるという声も多く聞かれます。
「書くことで自分の価値観が明確になった」「家族との会話が増えた」といった副次的効果も期待できます。
エンディングノートを書く最適なタイミングと継続のコツ

どこかのタイミングでまとめて書こうとするとハードルが高くなりがちです。日常生活の中にうまく組み込む工夫をしましょう。
記念日や年末年始に書くのがおすすめ
誕生日:新たな一年の始まりとして、心機一転で自分を見つめ直す
元旦:家族との時間が多く、共有しやすい。新年の目標と一緒に整理
命日やお彼岸:故人を思い出すタイミングにあわせて、自分の想いを整理
このような“節目”に合わせると、毎年のルーティンとして自然に習慣化できます。
定期リマインダーで書き忘れを防止
Googleカレンダーや LINEリマインド機能を活用し、「半年に1回の見直し」などの定期更新を仕組み化するのもおすすめです。
スマートフォンの通知機能を使って、「月末の振り返り」として軽い気持ちで更新する習慣をつけましょう。
よくある疑問と不安への回答
エンディングノートについての不安や誤解を解消しましょう。気負わず、できるところから始めてOKです。
「若いうちに書くなんて縁起でもない?」
実際には、若い世代での終活が注目されています。「ライフプランを考える一環」「自分の価値観を整理するツール」として前向きに取り組む人も多いです。
縁起を気にする場合は、「未来設計ノート」「ライフプランノート」などの呼び方を使うのも一つの方法です。
「一気に完成させないといけない?」
全くその必要はありません。大切なのは“書き始めること”。まずは名前・連絡先・医療の希望など、書きやすいところから始めましょう。
「今日は連絡先だけ」「今回は医療の希望だけ」といった具合に、少しずつ積み重ねていくことが継続のコツです。
「遺言書との違いは?」
エンディングノートは法的効力はありませんが、気持ちを伝えるツールとして非常に有効です。
遺言書とあわせて使うことで、実務+心情両方の伝達が可能になります。遺言書では表現しきれない「想い」や「背景」を補完する役割を果たします。
「家族に反対された場合は?」
「縁起でもない」と反対される場合は、「家族が困らないための準備」「自分の価値観を整理したい」という前向きな理由を説明しましょう。
また、「健康なうちに考えておきたい」「親の介護で大変だった経験から」など、具体的な動機を伝えると理解を得やすくなります。
「書いた内容を変更したくなったら?」
むしろ定期的な見直しと更新が推奨されます。人生の状況や価値観は変化するもの。
年に1-2回は内容を見直し、必要に応じて更新することで、常に現在の自分の想いを反映できます。
エンディングノートを書く5ステップ

誰でも簡単に始められる5つのステップをご紹介します。
1. テーマを決める:医療・介護・財産・連絡先など、自分が最も伝えたいことを優先的に選択
2. テンプレートを使う:白紙から始めるよりも、チェック項目があるテンプレートが便利で継続しやすい
3. 家族に存在を伝える:秘密にせず、家族にも共有。保管場所も明示し、アクセス方法も説明
4. 定期的に見直す:年1-2回の更新を目安に。状況の変化に応じて柔軟に書き直し
5. 紙+デジタルで残す:紙だけでなく、GoogleドキュメントやEvernoteなどのクラウド活用も有効。バックアップも忘れず
に
まとめ|エンディングノートは”早すぎる”ことがない準備
エンディングノートは、年齢に関係なく始められる大切な「備え」です。20代・30代だからこそ、柔軟に人生の棚卸しができ、将来の見直しにもつながります。
完璧でなくても構いません。「書いてみようかな」と思ったその時が、あなたの”始めどき”です。
重要なのは、完璧を求めすぎないこと。少しずつでも継続することで、自分らしい人生の記録が完成していきます。
家族への愛情表現としても、自分自身の人生整理としても、エンディングノートは価値のあるツールです。
まずは小さな一歩から始めてみましょう。 今日から「自分にとって大切なもの」を1つだけでも書き出してみることから始めてみませんか?
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。