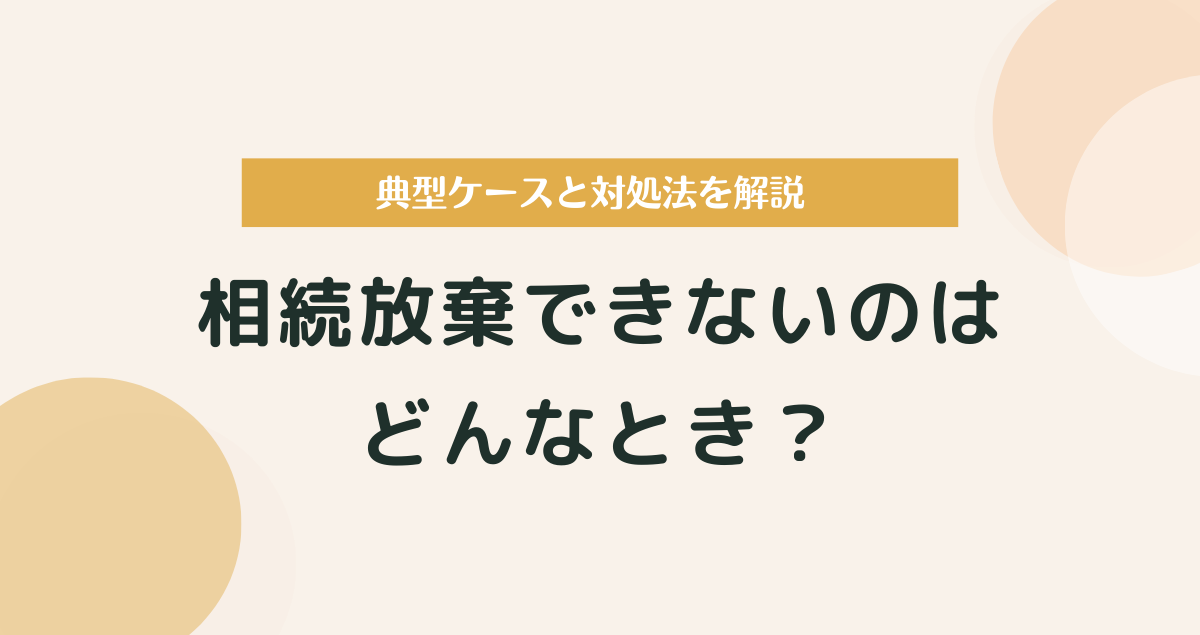相続放棄をすれば「借金を背負わずに済む」と考える方は多いでしょう。
しかし、実際には相続放棄が認められないケースが存在します。期限を過ぎてしまったり、知らないうちに遺産を使ってしまったりすると、放棄できなくなる可能性があります。
この記事では、相続放棄できない典型例と対処法を整理し、失敗を防ぐための注意点を解説します。
目次
相続放棄できない典型ケース

相続放棄は誰でも自由に行える手続きではなく、一定の条件を守らなければ認められません。
相続人の行動や期限の過ぎ方によって「放棄できない状態」に陥ることもあります。以下で代表的なケースを確認しておきましょう。
法定単純承認が成立してしまった場合
相続人が遺産の一部を使ったり売却してしまうと、自動的に「相続を受け入れた」とみなされます。
これを法定単純承認と呼び、以降は相続放棄ができません。
相続財産の処分や換金といった行為が典型例のため、迷う場合は何も触れず専門家に相談するのが安全です。
熟慮期間(3か月)を過ぎてしまった場合

民法第915条では、相続人が相続を承認するか放棄するかについて、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に判断しなければならないと定められています。
参考:
e-Gov法令検索|民法第915条
死亡日と「相続を知った日」が異なる場合、起算点が変わるため注意が必要です。
把握した日付をメモしておくと、手続きの遅れを防げます。
例1(死亡日と同日に知った):1月1日死亡→この日を起算点として4月1日までが熟慮期間
例2(死亡から数日後に知った):1月1日死亡/1月10日に知った→1月10日から3か月→4月10日まで
必要書類に不備がある場合
家庭裁判所への申立書や添付書類に不足があると、相続放棄は受理されません。
戸籍謄本や申述書の記載誤りなど、細かな不備が原因になることもあります。
やむを得ず相続放棄できなかった場合の対処法

「すでに放棄できない状態になってしまった」場合でも、取れる手段は残されています。
状況に応じて実行可能性と負担を比較し、最適な対応を選びましょう。
不服申立て(即時抗告)
家庭裁判所の判断に納得できない場合、一定の期限内で即時抗告を申し立てることが可能です。
認められるハードルは高いため、可否の見立てを専門家に相談し、理由書の整理から着手するのが現実的です。
限定承認の活用
相続財産の範囲内でのみ債務を負う限定承認という制度があります。
すべての相続人の合意が必要ですが、借金のリスクをコントロールできる点がメリットです。資産・負債の棚卸しを同時に進めると判断がしやすくなります。
債権者と交渉する
返済条件の緩和や分割など、債権者との交渉が現実的な選択肢になる場合もあります。
交渉の前提として、支払能力の見通しと代替案を用意し、交渉記録を残すことが重要です。
相続放棄で失敗しないための注意点
放棄できない事態を避けるには、日頃からの意識と準備が大切です。
相続財産に触れない、期限を意識する、専門家の力を借りるという基本を守るだけで、リスクを大きく減らせます。
相続財産に手を付けない
「使ってしまったら放棄できない」という大原則を徹底しましょう。
判断に迷う場合は、財産に触れず、まずは相談窓口へ。
期限内に判断するための準備
3か月は短く感じる場合も多いため、財産状況の確認と書類収集を早めに開始します。
起算点のメモとタイムライン作成が効果的です。
専門家に相談するメリット
複雑な書類作成や判断が必要になるため、司法書士や弁護士へ相談することでリスクを減らせます。
初回相談を活用し、必要書類の洗い出しから進めましょう。
なお、相続放棄は「事前に備えること」でもリスクを下げられます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄の3か月期限は延長できますか?
A. 家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をすれば、やむを得ない事情がある場合に延長が認められる可能性があります。
ただし必ず認められるわけではないため、早めに行動することが重要です。
Q2. 相続放棄を一度したら取り消せますか?
A. 原則として取り消すことはできません。
ただし詐欺や強迫など例外的な事情がある場合は無効が主張できるケースもあるため、専門家に相談してください。
Q3. 借金だけを放棄して財産だけを相続することはできますか?
A. できません。相続放棄は「すべての財産と負債」を放棄する手続きであり、一部だけ選ぶことはできません。
Q4. 相続放棄をすると他の相続人に迷惑がかかりますか?
A. 自分が放棄すると、代わりに他の相続人に権利と義務が移ります。
結果的に借金の負担が他の家族に集中することもあるため、事前に家族で話し合っておくことが大切です。
Q5. 相続放棄は自分で手続きできますか?
A. 書類を揃えて家庭裁判所へ提出すれば自分でも可能です。
ただし不備があると却下される可能性もあるため、司法書士や弁護士に依頼する人も多いです。
まとめ
相続放棄できない典型的なケースは、期限切れ・単純承認・書類不備の3つです。
放棄できなかった場合でも、限定承認や債権者交渉などの代替手段があります。
相続放棄は「時間」と「行動」に左右される手続きのため、迷ったら早めに専門家に相談し、家族の負担を最小限に抑えましょう。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。