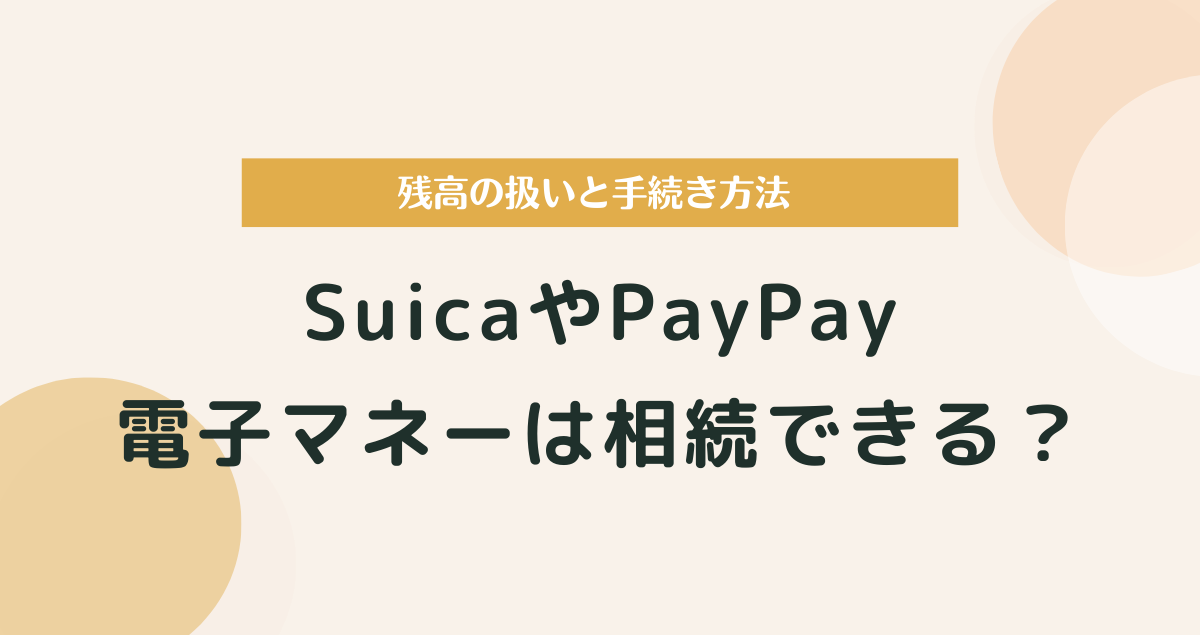スマホ決済や交通系ICカードなどの電子マネーが広く使われる今、もし利用者が亡くなった場合、その残高はどうなるのでしょうか。
本記事では PayPay、Suica、楽天Pay、WAON の主要サービスを対象に、死亡時の相続・払い戻しの可否と具体的な手続き方法をまとめます。
目次
電子マネーの残高は相続できる?
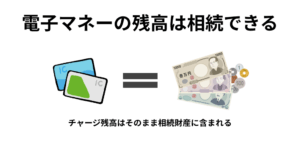
電子マネー残高は相続税の課税対象です。
- 評価額:死亡時点での残高がそのまま相続税評価額になる
- 申告:他の相続財産と合算し、基礎控除額を超える場合は申告が必要
- 証明書:サービス提供会社から残高証明書を取得する場合がある
少額でも申告漏れを避けるため、複数サービスを合算して把握することが重要です。
故人の電子マネーを発見する方法

スマートフォンの確認
- iPhone:「ウォレット」や「ぺい」で検索すると電子マネーアプリが表示される
- Android:Google Playの購入履歴やインストール済みアプリ一覧から決済アプリを確認
- チェックすべき主なアプリ:PayPay、LINE、メルカリ、楽天ペイ、au PAY、d払い など
家計管理アプリの確認
マネーフォワードやZaimなどの家計管理アプリに電子マネーが連携されている場合があります。銀行口座や証券口座と同様に、電子マネーも一緒に登録されている可能性があります。
銀行口座・クレジットカード明細の確認
電子マネーへのチャージ履歴やクレジットカード明細から、利用していたサービスを特定できます。
主要電子マネーサービスの相続・払い戻し対応一覧
以下に代表的な電子マネーの対応をまとめました。
| サービス | 相続・払い戻し | 手続き方法(概要) | 公式情報 |
|---|---|---|---|
| PayPay | 可能(残高を振込返金) | 遺族がカスタマーサポートに連絡し、死亡証明・相続人確認書類を提出。残高から振込手数料を差し引いて指定口座に返金。 | PayPay ヘルプ |
| Suica | 可能(SF残高とデポジット返金) | 記名式カード:駅窓口で払い戻し。 モバイルSuica:専用フォームから払い戻し申請後郵送書類を送付。残高+デポジットから手数料差引き。 |
Suicaを払戻す(JR東日本) |
| 楽天Pay(楽天キャッシュ) | 可能(振込返金) | 遺族が問い合わせフォームから連絡。死亡証明・相続人書類を提出。残高から振込手数料を差し引いて返金。 | 楽天ペイアプリ ヘルプ |
| WAON | 可能(残高は返金、ポイントは失効) | 遺族がWAON窓口やイオン店舗に連絡。死亡証明書類を提出し、残高を返金。WAONポイントは相続不可。 | WAON公式サイト |
電子マネーの相続に必要書類
各サービスに共通して求められる主な書類は次の通りです。
- 死亡を証明する書類:死亡証明書または死亡診断書、戸籍謄本
- 相続人であることを証明する書類:戸籍謄本(相続関係を証明)、遺産分割協議書や遺言書(場合により)
- その他:相続人の本人確認書類、返金先口座の通帳やキャッシュカード
※具体的な必要書類はサービスにより異なるため、事前に問い合わせて確認してください。
電子マネーを相続する際の注意点と準備のすすめ

電子マネーは気づかないうちに残高が失効したり、ログイン情報が分からず手続きが進まないといったトラブルも起こりやすいのが特徴です。
ここでは、相続時に注意すべきポイントと、生前に準備しておくべき対策を整理しました。
時効・失効のリスク
- 長期間利用がないと残高が失効する可能性
- サービス終了のリスクもあるため早めの手続きが重要
事前準備の重要性
- サービスごとに対応が異なるため、家族が知らないと残高が消滅する可能性あり
- パスワードやログイン方法を共有していないと、手続きが難航する
- エンディングノートや資産リストに記録しておくと家族が安心
デジタル資産全般の整理
電子マネー以外にも以下の資産について整理が必要です。
- ネット銀行:楽天銀行、住信SBIネット銀行など
- ネット証券:SBI証券、楽天証券など
- 暗号資産(仮想通貨):ビットコインなどの取引所口座
- ポイントサービス:楽天ポイント、Tポイントなど
よくある質問
Q. 電子マネーの残高は必ず相続できるの?
A. 主要な電子マネー(PayPay、Suica、楽天Pay、WAON)は残高の払い戻しや相続対応が可能です。
ただしポイントや特典は相続できない場合が多いため注意が必要です。
Q. 相続の手続きはどれくらい時間がかかる?
A. 各サービスの審査や確認に時間を要するため、数週間~1か月程度かかるのが一般的です。
必要書類が揃っていれば比較的スムーズに進みます。
Q. 少額でも手続きをしないといけない?
A. 数百円程度の残高であっても、相続税の対象となります。
相続税申告が不要なケースでも、払い戻しを希望する場合は手続きが必要です。
Q. 相続人が複数いる場合はどうなる?
A. 原則として遺産分割協議書などの書類で誰が受け取るかを明確にする必要があります。
サービスによっては相続人全員の同意が求められることもあります。
Q. ログインIDやパスワードが分からないと手続きできない?
A. 多くのサービスでは、死亡証明書や戸籍謄本などの書類で相続人であることを証明すれば手続き可能です。
必ずしも故人のログイン情報が必要なわけではありません。
Q. 電子マネーの残高が失効していたらどうなる?
A. 失効後は原則として払い戻しできません。
長期間放置すると権利を失う可能性があるため、早めの確認と手続きをおすすめします。
まとめ
電子マネー残高は相続の対象となり、主要サービスではいずれも払い戻しが可能です。
ただし サービスごとに手続き窓口や条件が異なるため、利用規約や公式ページを確認しながら進めてください。
まずは自分が使っている電子マネーをリストアップし、残高と手続き窓口をエンディングノートに記載しておきましょう。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。