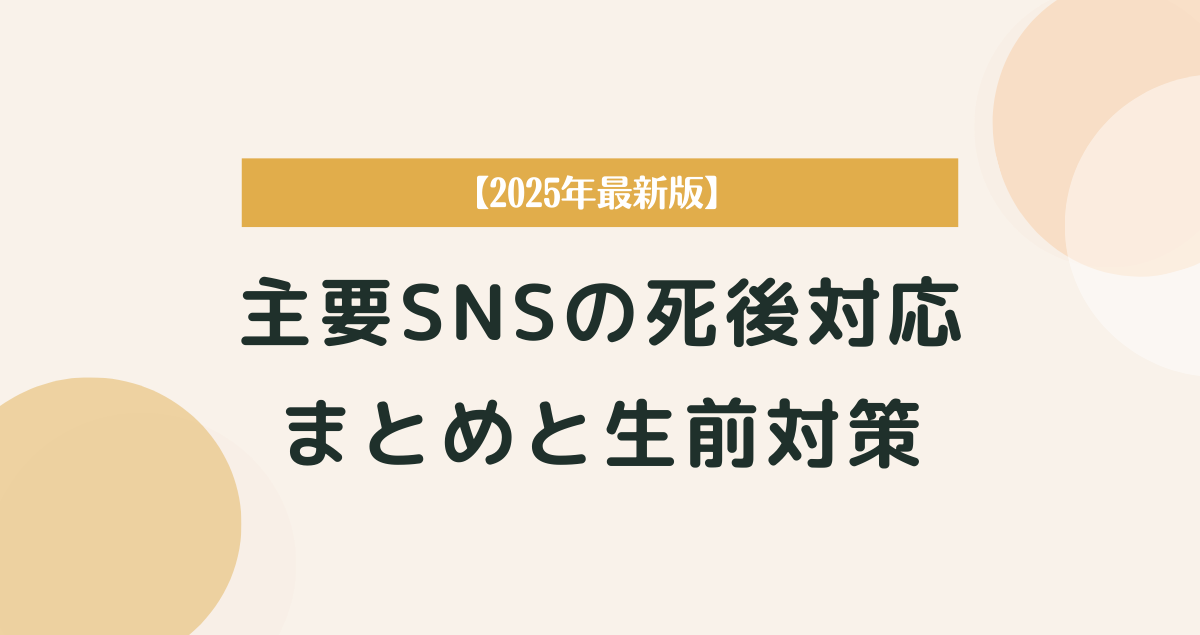もし自分や家族が亡くなったら、SNSアカウントはどうなるのでしょうか。
デジタル社会の今、SNSの「死後対応」は誰にとっても大切な課題です。
FacebookやInstagram、LINE、X(旧Twitter)などのアカウントを放置すると、不正アクセスのリスクや、故人を偲ぶ人々にとっての心理的な負担につながることもあります。
本記事では、主要SNSごとの死後のアカウント対応方法と、生前にできるデジタル終活のポイントをわかりやすく整理しました。
大切な思い出や個人情報を守るために、今から一緒に確認していきましょう。
目次
死後にSNSアカウントはどうなるのか

放置されたSNSアカウントがもたらすリスク
故人のSNSアカウントがそのまま残されていると、なりすまし被害や不正アクセスのリスクがあります。
アカウントが乗っ取られて迷惑投稿に利用されたり、個人情報が流出する恐れも否定できません。
また、友人知人が故人のアカウントにメッセージを送り続けてしまうなど、心理的な負担を生じるケースもあります。
亡くなった後のアカウントを適切に処理しないと、残された人々に思わぬトラブルや悲しい思いを与えてしまう可能性があるのです。
デジタル遺品としてのSNSアカウント
SNSアカウントは写真やメッセージなど思い出のデータが蓄積されたデジタル遺品でもあります。
家族にとっては故人の足跡として残しておきたい反面、プライバシーの観点から削除したい場合もあるでしょう。
サービス提供元のルール上、アカウントは個人に帰属し相続できないことが多く、生前に対策を講じていないと遺族が対応に困るケースがあります。
そのため生前の意思表示や公式機能の活用が重要となります。
主要SNS別の死後アカウント対応方法
SNSごとに死後の対応方法は大きく異なります。
ここでは、FacebookやLINEなど主要サービスの公式ルールを整理し、遺族や本人が取るべき具体的な行動を解説します。
主要SNSの死後アカウント対応一覧
| SNSサービス | 対応内容 | 生前設定 | 遺族による対応 | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 追悼アカウントに変更、または削除申請が可能。 | 「追悼アカウント管理人(Legacy Contact)」を設定可能。 | 削除申請時は死亡証明書等の提出が必要。 | Facebook公式ヘルプ | |
| 追悼アカウント化または削除申請が可能(Meta社)。 | Facebook連携設定で一部引き継ぎ可。 | 死亡証明書を提出して削除リクエスト可能。 | Instagram公式ヘルプ | |
| X(旧Twitter) | アカウント削除のみ対応(ログイン不可)。 | 生前設定なし。 | 死亡証明書と申請者身分証の提出が必要。 | X公式ヘルプ |
| LINE | アカウント削除対応のみ。トーク履歴は復元不可。 | 生前設定なし。 | 本人確認書類と契約証明書の提出が必要。 | LINE公式ヘルプ |
| Googleアカウント | 無効化管理ツールで自動削除やデータ共有設定が可能。 | 「アカウント無効化管理ツール」で信頼できる連絡先を登録。 | 設定がない場合、遺族申請で削除・データ提供を検討。 | ツール概要 遺族申請方法 |
| Apple ID | 「デジタル遺産プログラム」でアクセス管理可。 | 「故人アカウント管理連絡先」を登録可能。 | アクセスキーと死亡証明書でデータ申請可。 | Apple公式サポート |
生前に備えてやっておきたいSNSのこと

死後のSNSアカウント処理は遺族にとって大きな負担になります。
ここでは、生前に利用者自身が準備しておくべきポイントや公式機能の活用法を紹介します。
事前に決めておくべきこと・伝えておくこと
まずは自分が利用しているSNSやオンラインサービスのリストアップから始めましょう。
そのうえで、死後にどうしてほしいかを家族に伝え、紙のエンディングノートやデジタルツールに記録しておくことが大切です。
Facebookの追悼アカウント管理人、Googleの無効化管理ツール、Appleのデジ
タル遺産プログラムなど、公式の生前設定は早めに済ませておくと安心です。
デジタル遺品整理チェックリスト
以下は今すぐ着手できる実践リストです。ひとつずつ進めれば、万一の際も家族が迷わず対応できます。
- 主要SNSアカウントの洗い出し:利用サービスを一覧化し、ログインIDや連絡先メールを整理。
- 死後の方針決定:アカウントごとに「削除」「保存」「公開範囲変更」など希望を明記。
- 公式の事前設定:Facebook・Google・Appleの生前設定を有効化。
- ログイン情報とバックアップ:パスワード管理ツール活用。大切な写真やメッセージは定期バックアップ。
- 家族への共有:希望と所在を家族に伝え、必要なら専門家に相談。
上記を実践することで、死後のSNS対応が円滑になり、心理的負担も軽減されます。
よくある質問(FAQ)
故人のSNSアカウントは相続できますか?
アカウントはほとんどのサービスで本人に帰属し、相続の対象にはなりません。遺族は削除や追悼アカウント化など、公式の申請手続きを行う必要があります。
パスワードを知っていれば家族がログインできますか?
規約上、本人以外のログインは禁止されています。たとえパスワードを知っていても、正規の手続きで削除や追悼化を申請する必要があります。
削除や追悼化の手続きに必要な書類は?
多くのSNSでは死亡証明書や申請者の身分証明書が必要です。LINEなど一部サービスでは電話番号契約証明書など追加資料を求められることもあります。
生前に準備できることはありますか?
Facebookの「追悼アカウント管理人」、Googleの「アカウント無効化管理ツール」、Appleの「デジタル遺産プログラム」などを設定しておくと、遺族の負担を軽減できます。
まとめ
主要SNSはいずれも死後対応の仕組みを用意していますが、事前設定や意思表示が鍵です。
放置や不正利用のリスクを避け、思い出のデータを確実に継承するためにも、生前の準備を進めましょう。
大切なデータと想いを守るために、今すぐ一歩を踏み出しましょう。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。