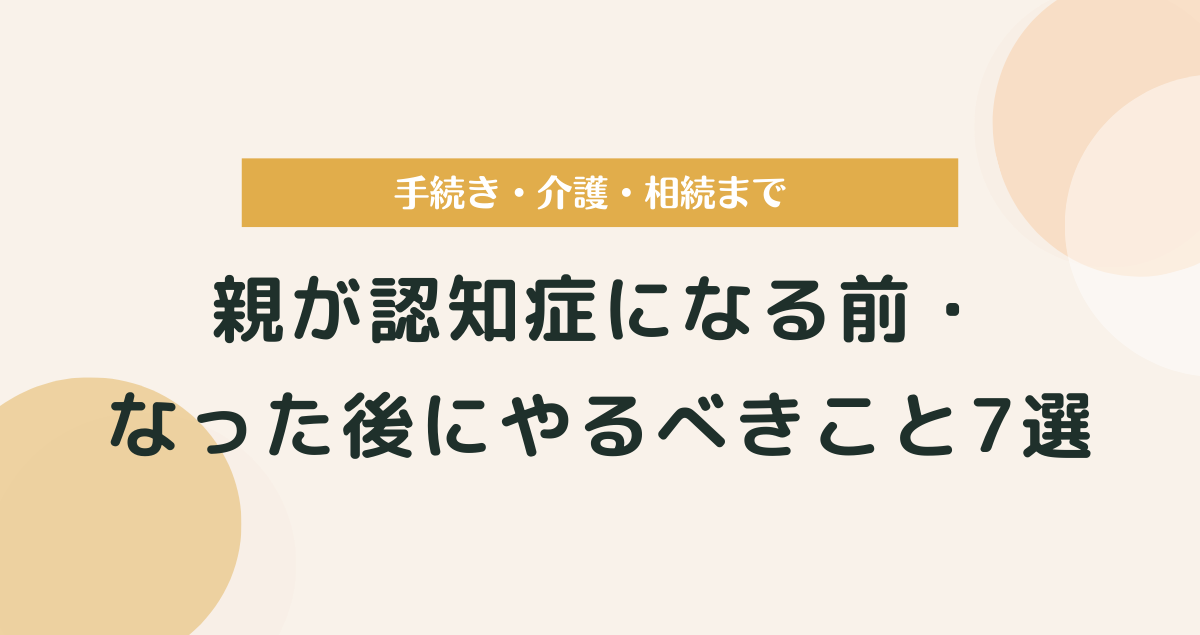「最近ちょっと物忘れが増えてきたかも…」
そう感じたときこそ、認知症に備える準備の始めどきです。
認知症は進行性の病気で、いったん発症すると本人の“意思”を確認できなくなり、多くの契約や手続きができなくなります。
銀行口座の凍結や相続の遅れなど、家族にとって大きな負担になることも。
この記事では、親が認知症になる前と、認知症になった後に家族がやるべきことを重要度の高い順に7つ解説します。
将来の不安を減らし、安心して備えられるように、今からできることを一緒に確認していきましょう。
目次
【最優先】認知症になる前にやるべきこと7選
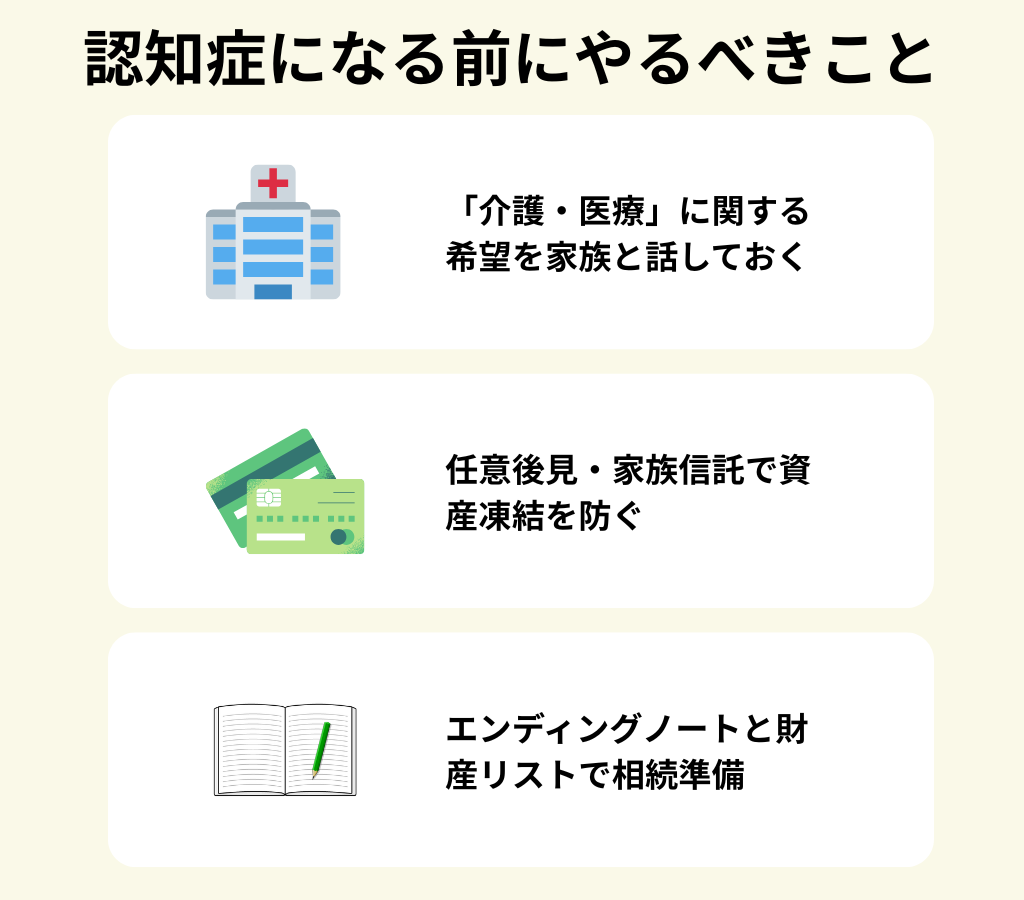
認知症になる前の準備は、家族の生活を守るための「最重要ステップ」です。
特に介護・医療の希望確認、財産管理の仕組みづくり、相続準備は手遅れになる前に取り組むことが大切です。
1. 「介護・医療」に関する希望を家族と話しておく
親がどのような介護や医療を望んでいるのか、元気なうちに話し合っておくことで、家族が迷わずサポートできます。話しづらいテーマこそ早めに共有を。
今すぐ確認したいポイント
- 延命治療を希望するかどうか
- 施設入所・在宅介護の希望
- 誰に相談したいか、信頼できる人は誰か
- かかりつけ医はどこか、持病や服薬状況
話し合いのコツ
テレビの介護特集を見ながら「もし自分だったらどう思う?」と自然に話題を振るのがおすすめです。
今月のチェック項目
- 親と介護について一度話し合った
- 延命治療の希望を確認した
- 信頼できる相談相手を聞いた
2. 任意後見・家族信託で資産凍結を防ぐ
認知症になると親の財産は凍結され、管理や契約が難しくなります。預金の引き出しすらできなくなるケースも。そうなる前に「家族が代わりに管理できる仕組み」を整えておくことが重要です。
2つの主要な選択肢
- 任意後見契約:将来に備えて、親が信頼できる人を後見人として事前に指定しておく制度(費用:公正証書作成に約2〜3万円+専門家報酬)
- 家族信託:親の財産を契約によって家族に託し、柔軟に運用・管理ができる仕組み(費用:財産額の1〜3%程度)
重要な注意点
これらは「意思能力があるうち」しか契約できません。認知症が進行してからでは手遅れです。
3ヶ月以内のチェック項目
- 専門家(司法書士・行政書士)に一度相談した
- 任意後見と家族信託の違いを理解した
- どちらが我が家に適しているか検討中
3. エンディングノートと財産リストで相続準備
田中さん家族の例
お父さんが急に倒れたとき、通帳がどこにあるかわからず、ネットバンクのパスワードも不明。保険の連絡先もわからず、手続きに3ヶ月もかかってしまいました。
相続トラブルの多くは「情報が整理されていなかった」ことが原因です。親が元気なうちに、財産の見える化と意向の共有を始めておきましょう。
最低限整理したいリスト
- 預金口座、保険、不動産、証券などの一覧
- ネットバンクや暗号資産のログイン情報
- 相続の希望や遺言書の有無
- 重要書類の保管場所
2ヶ月以内のチェック項目
- エンディングノートを購入した
- 財産リストの作成を開始した
- ログイン情報を親と一緒に整理した
4. 認知症予防につながる生活習慣を整える
日々の生活習慣を整えることは、認知症の予防や進行の遅延につながります。家族でできる取り組みを中心に、実践しやすい予防策を紹介します。
具体的な取り組み
- 食事:魚・野菜中心の食事、一緒に料理を作る
- 運動:週3回30分程度のウォーキング、ラジオ体操
- 睡眠:規則正しい就寝時間、昼寝は30分まで
- 社会参加:趣味のサークル、近所の人との交流
- 脳トレーニング:読書、パズル、新しいことへの挑戦
健康診断も忘れずに
年1回の健康診断で、認知症のリスク要因(高血圧・糖尿病・脂質異常症)をチェック。
5. 家の安全対策とデジタル環境整備
生活の中の“つまずき”を減らす環境整備と、IT機器を使った記録・共有の仕組みを取り入れることで、認知症の進行を穏やかにする助けになります。
安全対策の基本
- 段差の解消、手すりの設置
- 家具の配置見直し(動線の確保)
- 照明の明るさアップ
- 滑り止めマット、コード類の整理
デジタル活用術
- LINEやアプリで家族と情報共有
- 写真・日記アプリで記憶をサポート
- 薬の管理アプリ、通院記録の共有
6. 支援機関・専門家とのつながりを今のうちに
何かあったときにすぐ相談できる“つながり”を作っておくことで、家族の負担は大きく軽減されます。まずは情報収集から始めて、顔の見える関係を築いておきましょう。
主要な相談先リスト
- 地域包括支援センター:介護の総合相談窓口
- 司法書士・行政書士:成年後見、相続手続き
- 税理士:相続税、財産管理
- 社会福祉協議会:生活支援サービス
- 介護保険窓口:市区町村の担当課
7. きょうだい間の役割分担と情報共有
佐藤さん家族の成功例
長男が財産管理、長女が医療・介護、次男が緊急時対応と役割を決めて、月1回のLINE会議で情報共有。親の認知症が始まっても、家族が連携して対応できています。
複数のきょうだいがいる場合、事前に役割分担を決めておくことで、いざという時の混乱を避けられます。
話し合うべきポイント
- 誰が主たる介護者になるか
- 費用負担の分担方法
- 連絡・情報共有のルール
- 重要な判断をする時の決定プロセス
認知症になってしまった後にすべき対応
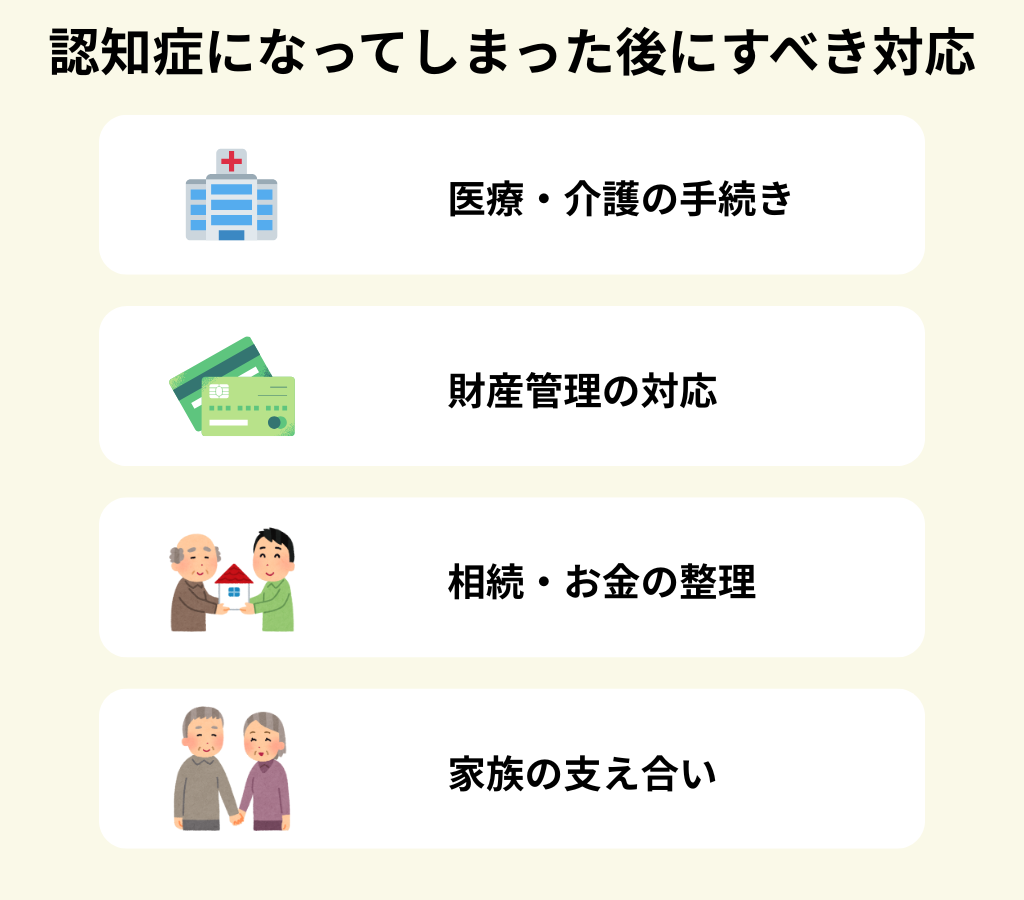
「準備をする前に親が認知症になってしまった…」というケースも少なくありません。その場合でも、利用できる制度や手続きはあります。慌てず、次のステップを確認しましょう。
1. 医療・介護の手続き
- かかりつけ医で診断を受け、診断書を取得
- 市区町村の窓口で「要介護認定」を申請
- 訪問介護・デイサービス・ショートステイなど介護保険サービスを利用開始
2. 財産管理の対応
- 契約ができない場合は家庭裁判所に「法定後見」を申し立てる
- 後見人が選任されると、預貯金の管理や施設入所契約などが可能になる
- 選任まで数ヶ月かかることもあるため、司法書士など専門家に相談を
3. 相続・お金の整理
- 相続が発生した場合、遺言書がなければ「遺産分割協議」が必要
- 銀行口座や保険手続きでは戸籍・診断書など多くの書類を提出
- 税理士や司法書士など専門家のサポートを受けるとスムーズ
4. 家族の支え合い
- 介護負担の偏りを防ぐため、きょうだい間で役割分担を調整
- 定期的に情報共有する仕組み(LINEグループ・月1回の話し合い)を作る
- 地域包括支援センターや社会福祉協議会に相談して外部支援を受ける
チェックリスト:認知症になる前・なった後の準備を一気に確認
これまでの準備がどこまで進んでいるかを確認するために、段階別のチェックリストをまとめました。
【最優先】必ず取り組むべきこと
- 親と介護・相続について話し合ったことがある
- 任意後見や家族信託を検討し、専門家に相談した
- 財産一覧・ログイン情報を整理している
- エンディングノートを一緒に書き始めている
【重要】生活の質向上のための準備
- 認知症予防の生活習慣を家族で実践している
- 家の中の安全対策を始めている
- LINEやアプリなどを親が使えている
【長期的】支援体制の構築
- 専門家・支援機関に一度相談してみた
- きょうだい間で役割分担を話し合った
進捗目安
- 3ヶ月以内:最優先項目の着手
- 6ヶ月以内:重要項目の実行開始
- 1年以内:長期的項目の基盤作り
よくある質問(FAQ)
Q1. 認知症の準備はいつから始めるべきですか?
「少し物忘れが増えてきたかな」と感じた段階が、もっとも適した準備のタイミングです。
意思能力があるうちにしかできない手続き(任意後見契約・家族信託など)が多いため、早めに話し合いや整理を始めましょう。
Q2. 任意後見契約と家族信託はどちらを選べばいいですか?
任意後見契約は生活や医療の契約・手続きを代理でき、
家族信託は財産の管理・運用に強い制度です。
家庭の状況(不動産や金融資産の有無、介護方針)によって適した選択が変わるため、司法書士など専門家に相談して決めるのが安心です。
Q3. エンディングノートと遺言書はどう違いますか?
エンディングノートは自分の思いや希望を家族に伝えるメモで、法的効力はありません。
遺言書は相続に関する意思を法的に有効に残せる文書です。
両方を組み合わせると、家族が迷わず手続きを進めやすくなります。
Q4. 準備をしないまま親が認知症になったらどうなりますか?
銀行口座や契約手続きができなくなるため、家族が困ることがあります。
その場合は家庭裁判所に法定後見を申し立てる必要があります。
後見人の選任まで数ヶ月かかることもあるため、早めの準備が望ましいです。
Q5. 認知症の進行を遅らせるために家庭でできることはありますか?
バランスの良い食事、定期的な運動、規則正しい睡眠は基本です。
また、趣味や交流といった社会参加、読書やパズルなどの脳トレも効果が期待できます。
あわせて健康診断を定期的に受け、生活習慣病の予防に取り組みましょう。
まとめ:認知症になる前と認知症になった後の両方に備える
親が認知症になる前に備えておけば、介護・相続・財産管理の多くの問題を未然に防げます。
「まだ早い」と思うタイミングこそが準備の最適期。
ただし、すでに認知症になった後も、後見制度や介護保険など利用できる仕組みはあります。大切なのは「なる前に備えること」と「認知症になった後に冷静に対応すること」を両輪で考えることです。
まずは「介護の話し合い」「専門家への相談」「財産整理」の3つから始め、家族みんなが安心できる準備を進めていきましょう。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。