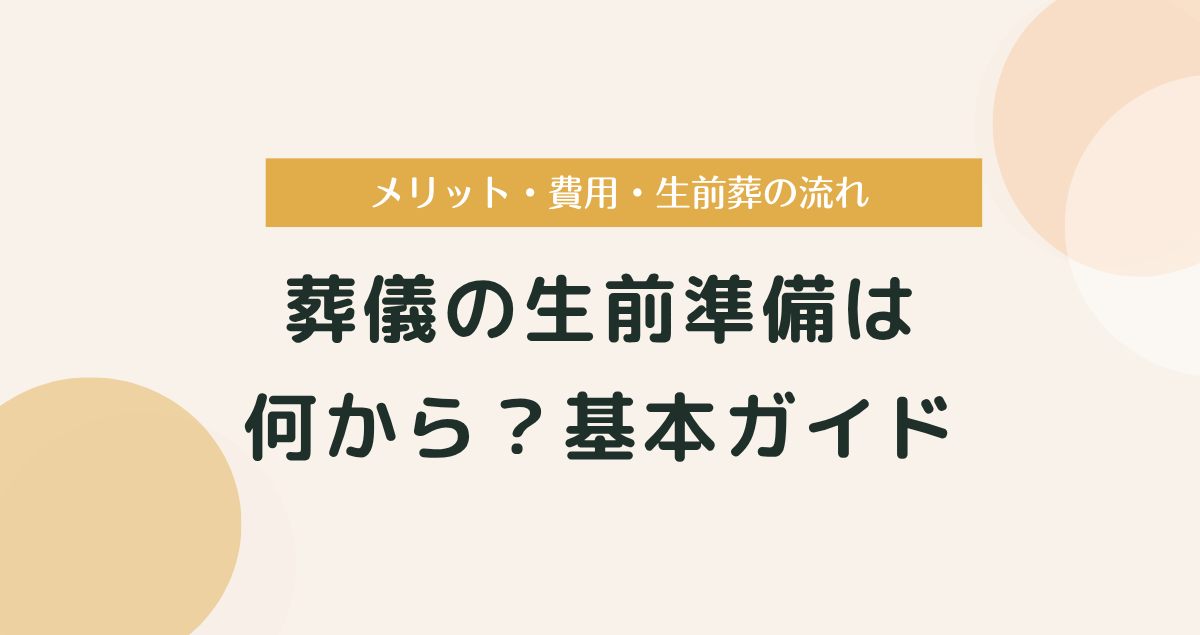将来への備えとして、生前に葬儀の準備をしておきたいと考える方が増えています。
鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査」によると、葬儀費用の平均総額は約119万円(前回約111万円)と、前回調査(2022年)から約8万円増加しました。
費用や形式、場所、規模などを自分で決めておくことは、残される家族の負担を減らし、自分らしい最期を実現するための大切な選択です。
この記事では、葬儀の生前準備の方法や生前葬の流れについて、実践的なステップを交えて分かりやすく解説します。
目次
生前に葬儀を準備するメリットとは

生前に葬儀を準備しておくことで、精神的・実務的の両面で多くのメリットがあります。代表的なポイントを整理しましょう。
家族の負担を減らせる
葬儀は突然の出来事であることが多く、残された家族は短期間で多くの決定を迫られます。
事前に「どんな形式で」「どこで」「誰を呼ぶか」を決めておくことで、家族の迷いや不安を減らすことができます。
また、葬儀費用は内容によって大きく異なります。
事前に見積を取り、必要に応じて積立や生前契約を行えば、急な出費に慌てることもありません。
自分らしい最期を実現できる
近年は、仏式葬だけでなく、家族葬・直葬・音楽葬・生前葬など多様なスタイルがあります。
生前に希望を整理しておけば、自分らしい葬儀の形を選び取ることができます。
また、時間に余裕があるうちに複数社を比較して契約すれば、信頼できる葬儀社を選び、後悔のない判断がしやすくなります。
葬儀の生前準備は何からやるべき?基本のステップ

1. 葬儀の形式を決める
宗教(仏式・神式・キリスト教・無宗教など)、規模(一般葬・家族葬・直葬など)、場所(自宅・会館・寺院)を整理し、誰を呼ぶかも検討します。
2. 費用の見積もりと予算設定
葬儀の費用には、式場・祭壇・火葬・返礼品・飲食などが含まれます。
プランごとに見積を取り、予算に合わせた現実的なプランを選びましょう。
3. 葬儀社への事前相談
信頼できる葬儀社を見つけるためには、複数社から資料を取り寄せて比較することが大切です。
最近はオンライン相談やLINE相談も増えています。
4. 生前契約や積立を検討する
費用を固定できる「生前契約」や「互助会」を利用すれば、インフレや値上がりの影響を抑えられます。
契約時には返金条件・解約手数料なども確認しておきましょう。
5. 家族への共有と記録
決めた内容を家族に共有し、エンディングノートやメモに残しておくことが重要です。
突然のときに家族が知らなければ、せっかくの準備も意味を持ちません。
「生前葬」とは?通常の葬儀との違い

生前葬は、本人が主催して感謝やお別れの気持ちを伝える葬儀スタイルです。宗教的制約が少なく、自由な演出で「人生の集大成」を表現できます。
| 比較項目 | 生前葬 | 通常の葬儀 |
|---|---|---|
| 実施時期 | 生前(本人が健在) | 死亡後 |
| 主催者 | 本人または家族 | 遺族(喪主) |
| 本人の出席 | 出席する | 出席しない |
| 目的 | 感謝・お別れ・自分らしさの表現 | 供養・故人とのお別れ |
| 宗教色 | 自由形式が多い | 宗教儀礼が中心 |
| 費用負担 | 本人が負担することが多い | 遺族が負担するのが一般的 |
生前葬の流れ(例)
代表的な流れは以下のとおりです。
- 受付・開場:記帳や香典辞退の案内、記念品配布などを行う。
- 開会の挨拶:司会または主催者から趣旨説明。
- 本人スピーチ:感謝の言葉や人生の振り返り。
- 映像上映:写真・動画・音楽で人生を回顧。
- 参加者スピーチ:家族や友人からのメッセージ。
- 会食・懇親:歓談・記念撮影などの時間。
- 記念品・寄せ書き:感謝を形に残す演出。
- 閉会の挨拶:本人または司会による締めの言葉。
生前に葬儀を準備する際の注意点
生前準備をしておくことで家族の負担を減らせますが、契約内容の不明確さや家族間の情報共有不足によってトラブルになるケースも少なくありません。
ここでは、実際に起こりやすい注意点と、その対策を分かりやすくまとめました。
1. 契約内容を「口約束」で終わらせない
生前契約や互助会プランを利用する際は、口頭説明だけで安心せず、見積書・契約書・パンフレットなどの書面を必ず受け取りましょう。
特に確認すべきポイントは以下の通りです:
- 契約金額と含まれる項目(祭壇・火葬料・返礼品など)
- 追加費用が発生する条件(参列人数増加・日程変更など)
- 解約や返金の可否、違約金の有無
営業担当者が異動した場合や、数年後に契約内容を忘れてしまうケースもあるため、契約時の資料は家族に共有し、原本を自宅で保管しておくのが理想です。
2. 家族と話し合わずに決めない
「自分のことだから自分で決めたい」と考える方も多いですが、葬儀は家族や親族にも影響する大切な儀式です。
特にトラブルになりやすいのは、
- 家族が「知らなかった」ため契約が無効になった
- 本人の希望と家族の宗派・慣習が合わなかった
- 費用を誰が支払うか明確にしていなかった
こうした事態を避けるために、家族会議で希望内容を共有し、反対意見が出た場合は中立な第三者(終活アドバイザーや葬儀社相談員)を交えて話し合うのもおすすめです。
3. 費用を一括払いにする場合は、会社の信頼性を確認
互助会や生前契約では、契約時に前払い金を支払う形式もあります。万が一、葬儀会社が倒産した場合に備え、加入団体や補償制度の有無を確認しておきましょう。
具体的には、以下をチェックしてください。
- 経済産業省の「冠婚葬祭互助会の登録制度」に加盟しているか
- 第三者機関による保証(消費者保護制度)があるか
- 口コミや評判、設立年数など会社の安定性
不安な場合は、一括前払いではなく積立型プランを選ぶのもリスク軽減になります。
4. エンディングノートと契約書の内容を一致させる
意外に多いのが、エンディングノートと契約内容の食い違いです。ノートに「家族葬希望」と書いていても、契約が一般葬のままだと、希望が反映されないことがあります。
契約後に希望が変わった場合は、ノートと契約書の両方を更新し、家族にも伝えておきましょう。ノートに「最終更新日」を記入しておくと、内容が古くならず安心です。
5. 定期的な見直しを忘れない
生前準備は、一度整えたら終わりではありません。年齢や家族構成、生活環境の変化に合わせて、年に1回程度の見直しを行うのが理想です。
特に、以下のような変化があったときは更新タイミングです。
- 家族の状況(結婚・同居・離婚など)が変わった
- 葬儀社のプランや料金が改定された
- 信仰や価値観に変化があった
変更後は、最新情報をエンディングノートに反映し、家族へ再共有しておきましょう。
まとめると、生前準備の最大のリスクは「情報の断絶」と「書面の不備」です。家族と情報を共有し、書面を整理しておくことが、後悔しない終活の第一歩となります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 生前に葬儀の準備をしておくメリットは?
最大のメリットは家族の負担を減らせることです。
事前に形式や費用、希望内容を決めておくことで、突然の時にも家族が迷わず対応できます。
また、複数社の見積もりを比較できるため、費用を抑えつつ納得のいくプランを選びやすくなります。
Q2. 葬儀費用はどのくらいが目安ですか?
鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査」によると、平均総額は約119万円です。
家族葬は80〜100万円前後、直葬(火葬式)は30〜50万円、一日葬や一般葬は100〜150万円が目安です。(出典:鎌倉新書)
Q3. 生前契約をした後でキャンセルや変更はできますか?
ほとんどの葬儀社や互助会ではキャンセル・変更が可能です。
ただし、時期や契約内容によっては解約手数料が発生することもあります。契約時には「解約・返金条件」が明記されているか必ず確認しましょう。
Q4. 家族に内緒で生前契約しても大丈夫?
契約自体は可能ですが、実際に葬儀を執行するのは家族です。
内容を知らないと手続きが進まず、希望どおりに実施されない恐れがあります。契約内容や保管場所を信頼できる家族に伝えておくことが大切です。
Q5. 準備内容はどのくらいの頻度で見直すべき?
年に1回程度の見直しがおすすめです。
家族構成や生活状況、信仰や価値観が変わったときは内容を更新し、エンディングノートにも最新情報を反映させましょう。
まとめ|葬儀の準備は家族への思いやり
葬儀の生前準備は、家族への思いやりであり、自分らしい人生の締めくくりでもあります。準備をすることで家族の負担が軽くなり、希望をしっかり反映した葬儀が実現できます。
まずはエンディングノートに希望を書き出し、複数の葬儀社に見積を取ることから始めてみましょう。見積の内訳・追加費用・返金条件を確認することが、安心の第一歩です。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。