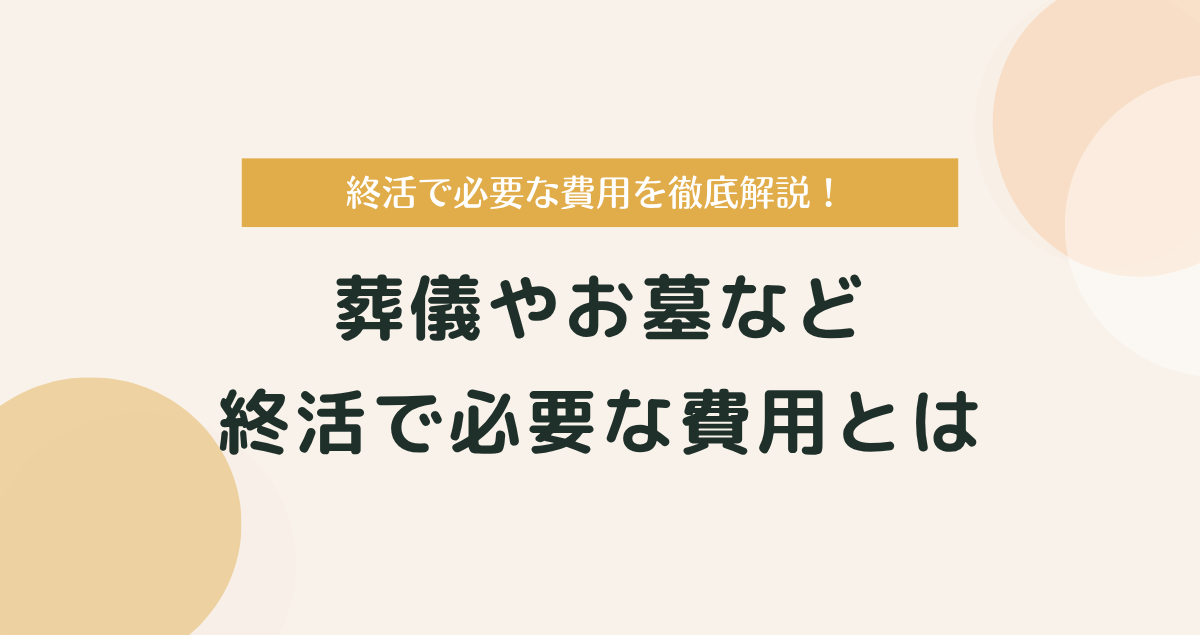終活を始めたいけれど、「終活にかかる費用は総額いくら?」「どこまで準備すべき?」と迷っていませんか。
終活費用は、葬儀・お墓(納骨)・遺言書・相続や死後事務・生前整理など多岐にわたり、希望する内容によって金額が大きく変わります。
この記事では、終活に必要な費用の内訳や平均相場を、最新の調査データをもとにわかりやすく解説します。自分や家族の希望を明確にし、安心して終活を進めるための参考にしてください。
目次
終活にかかる主な費用と平均相場
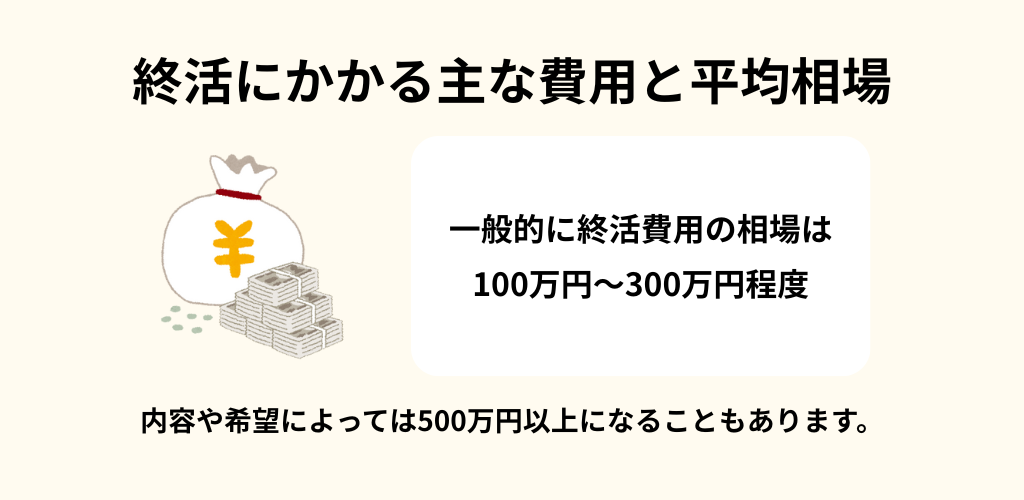
終活にはさまざまな支出が伴います。まず全体を把握することで、優先順位をつけやすくなります。
一般的に終活費用の相場は100万円〜300万円程度とされますが、内容や希望によっては500万円以上になることもあります。
葬儀費用
葬儀費用の全国平均は118.5万円という最新調査があります(いい葬儀「葬儀費用の実態と納得度調査 2025」)。
人生の最期を見送る葬儀は、終活費用の中でも特に大きな割合を占めます。形式によって費用は大きく異なります。
- 一般葬:目安100万〜200万円(平均161.3万円のデータあり)
- 家族葬:目安50万〜100万円(平均105.7万円)
- 直葬(火葬のみ):目安20万〜40万円(平均42.8万円)
内訳の例:式場・祭壇・棺・搬送などの基本料金、通夜・精進落とし等の飲食費、香典返し等の返礼品費など。参列人数や地域で変動します。
費用が変わるポイント:参列人数、式場のグレード、返礼品の有無、搬送距離、地域差で総額が上下します。
お墓・納骨にかかる費用
お墓については、購入したお墓の平均購入金額が一般墓155.7万円・樹木葬67.8万円・納骨堂79.3万円というデータが出ています(いいお墓「お墓の消費者全国実態調査 2025」)。
供養方法によって費用は大きく異なります。近年は永代供養や樹木葬、納骨堂など選択肢が広がっています。
- 一般墓(墓石+区画):平均155.7万円
- 樹木葬:平均67.8万円
- 納骨堂:平均79.3万円
立地・区画の広さ・管理内容によって差が出ます。維持費(年間数千円〜1万円程度)も見込みましょう。
遺言書の作成費用
自分の意思を法的に残すには、公正証書遺言が最も確実です。種類と費用の目安は以下の通り。
- 自筆証書遺言:作成自体は費用不要。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、保管手数料3,900円(法務省:手数料)。
- 公正証書遺言:財産額に応じて手数料が決まり、証人費用等を含めおおよそ5万〜15万円が目安。具体的な算定方法は日本公証人連合会の手数料ページを参照(日本公証人連合会:手数料)。
相続・死後事務の手続き費用
「おひとりさま」や家族が遠方にいる場合は、死後の手続きを担う第三者(司法書士・行政書士等)と死後事務委任契約を結ぶと安心です。
- 相続税申告の税理士費用:相続財産額の0.5〜1%が目安。
- その他専門家報酬:事案の難易度・地域・作業範囲により大きく変動(各事務所の見積もり要)。
生前整理・不用品処分の費用
生前整理を進めておくと、遺族の負担や急な高額費用を抑えられます。金額は物量・間取り・作業内容で大きく変動します。
- 相場の目安例:1K・ワンルームで数万円〜、家財量が多い一軒家で十数万〜数十万円。
- 業者選びは複数見積りが必須。無許可業者とのトラブルに注意。
終活費用を抑える5つのコツ

終活にかかる費用は、すべてを削る必要はありません。大切なのは「自分にとって必要なもの」と「削っても困らない部分」を分けて考えることです。
事前に方針を決めておくだけで、不要なオプションや重複した支出を避けやすくなり、結果として総額を抑えられます。
- 葬儀は「形式」と「参列人数」を先に決める(見積りがブレにくい)
- お墓は購入費用だけでなく、管理費などの維持費も含めて比較する
- 遺言は内容が複雑な場合、公正証書遺言を選ぶことで無効リスクを防ぐ
- 生前整理は一気に業者へ依頼せず、まずは自分で分類から始める
- 業者に依頼する場合は、必ず複数社から見積りを取り、作業範囲を書面で確認する
よくある質問(FAQ)
Q1. 終活の費用はどのタイミングで準備すればいいですか?
A. まとまった費用になりやすい葬儀・お墓は、無理のない範囲で早めの準備が安心です。最新調査では葬儀総額の全国平均が118.5万円。終身保険・積立などで計画的に備えると負担を平準化できます。
Q2. おひとりさまの終活では、どんな費用を重視すべき?
A. 死後の手続きを誰が行うかを明確にし、死後事務委任契約や葬儀・納骨の実行手配に関わる費用を優先的に確保しましょう。遺言は公正証書遺言にすると実務上の混乱を抑えられます。
Q3. 家族と費用・情報を共有した方がいい?
A. 可能であれば共有を。葬儀社の事前相談先、保険金の受取人、遺言の保管先(法務局の保管制度:手数料3,900円)などは事前に伝えておくと安心です。
まとめ|自分に合った終活費用の備えを
終活にかかる費用は、葬儀やお墓、遺言書作成、相続手続き、不用品の整理まで多岐にわたります。
平均相場や調査データを踏まえつつ、自分の希望に合った優先順位を決めることで、無理のない備えが可能です。
老後資金とのバランスを意識し、できることから少しずつ準備を始めていきましょう。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。