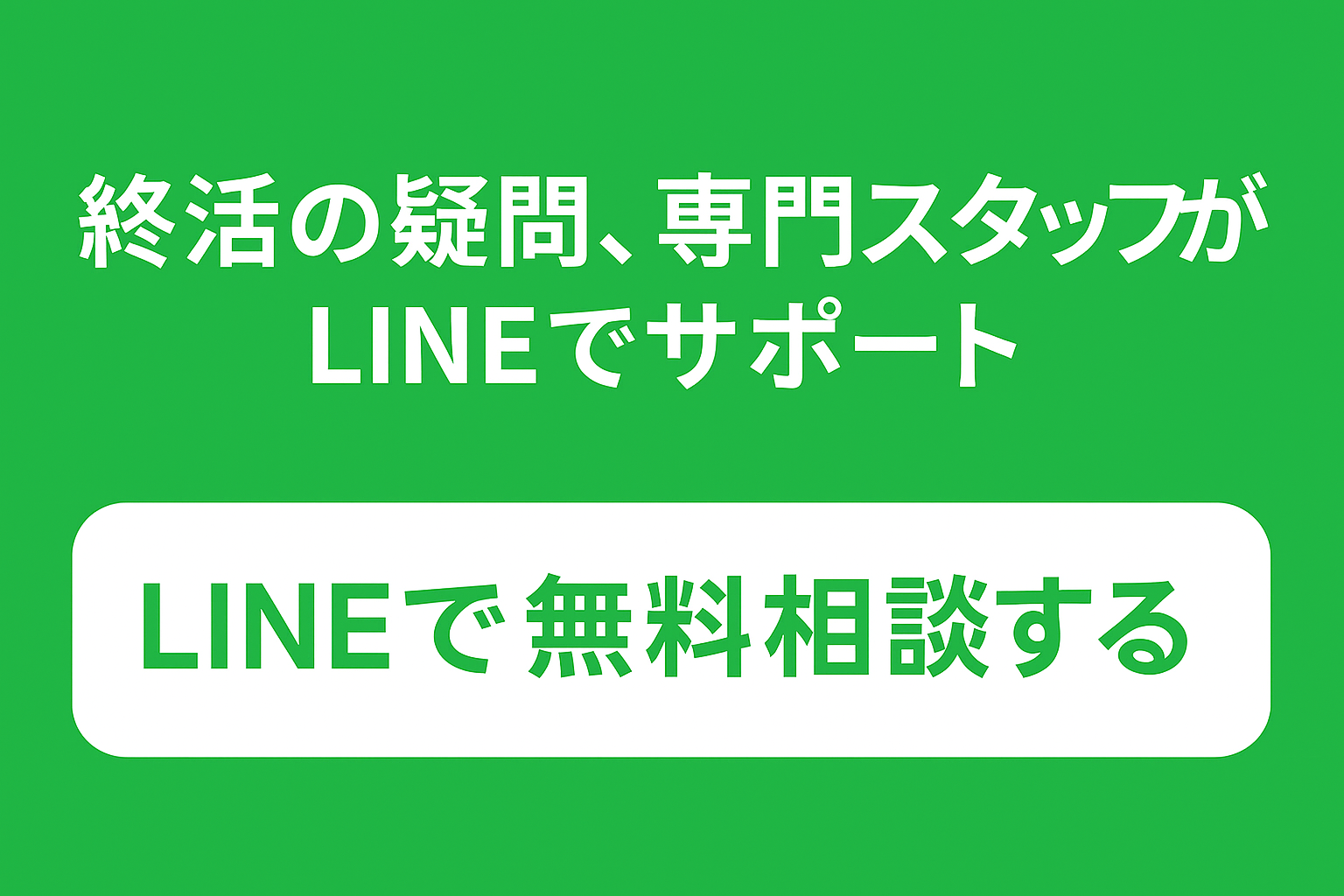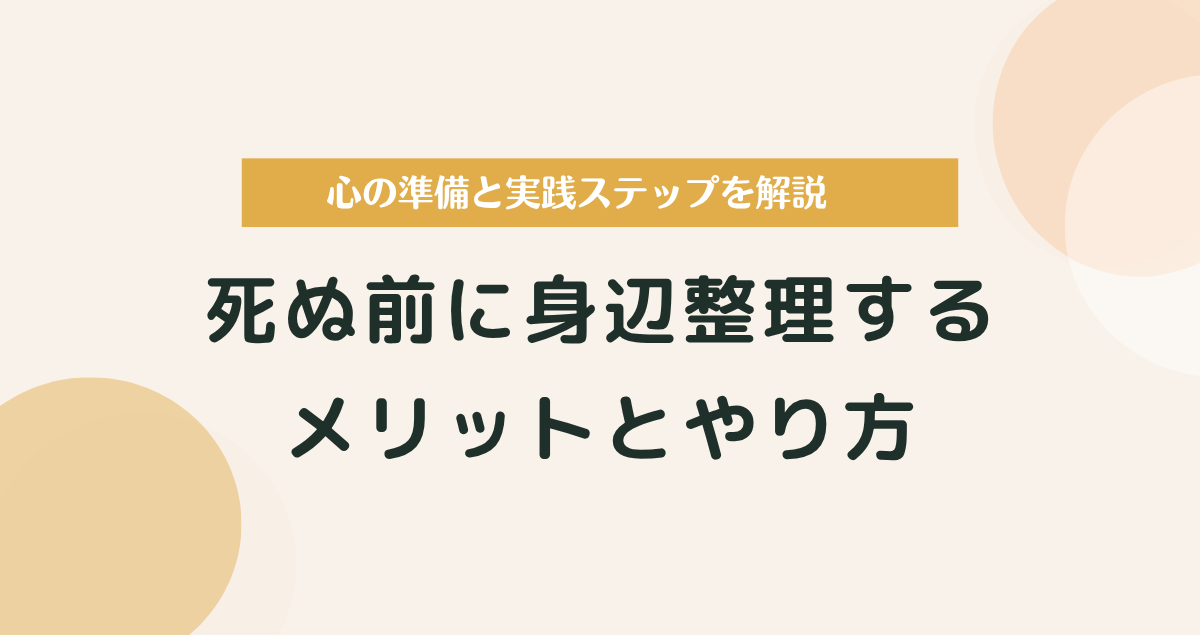「まだ元気だから、身辺整理なんて早すぎる」 そう思っていませんか?
身辺整理は「死ぬ前の準備」としてだけでなく、「これからの人生を豊かに生きる」ためにも重要なステップです。
この記事では、実際に整理すべきモノ・コトを具体的にリスト化しながら、無理なく始められる方法を解説します。
目次
身辺整理をする5つのメリット

身辺整理を行うことは、自分自身と家族の双方にとって多くのメリットがあります。多くの人が「やって良かった」と感じる理由を、心理的・実務的な観点から5つの具体的な利点としてご紹介します。これらのメリットを理解することで、整理への取り組みがより前向きになるでしょう。
1. 大切な人への負担を減らせる
自分の死後、身の回りの整理や遺品の処分をすべて家族に任せるのは大きな負担です。一般的な遺品整理には平均30〜50時間かかり、費用も10〜100万円と幅があります。事前に整理しておくことで、家族が精神的・時間的に追い込まれる状況を避けることができます。
2. 遺産相続や手続きがスムーズになる
財産や契約関係が整理されていると、相続手続きが円滑になります。相続争いの約40%は財産の所在が不明確なことが原因です。特に金融資産や不動産に関する情報を明確にしておくことが、争族(争いによる相続トラブル)を防ぐ鍵です。
3. 自分の人生の棚卸しができる
身辺整理は、これまでの人生を振り返る良い機会にもなります。自分にとって何が大切だったか、何を残したいかを見つめ直す時間になります。多くの人が「物を通じて人生を振り返れた」と感じています。
4. 万が一のときも安心して過ごせる
急な病気や事故に見舞われても、「すでに準備してある」という事実が安心感を与えてくれます。老後の生活を穏やかに過ごすための心の保険とも言えるでしょう。
5. 心が軽くなり、生活の質が上がる
整理が進むと、物理的にも精神的にも空間が生まれます。本当に必要なものだけに囲まれた生活は、シンプルで快適です。掃除や管理の時間も短縮され、自分の好きなことに時間を使えるようになります。
身辺整理の主な内容とやるべきことリスト

身辺整理と一口に言っても、その範囲は多岐にわたります。何をどこから始めればいいのか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは整理すべき対象を5つの分野に分けて、それぞれの具体的な内容と取り組み方を明確にします。この分類に沿って進めることで、抜け漏れなく効率的に整理を進められます。
1. 物の整理(家の中のモノ・遺品になりうる物)
対象となるもの
- 日用品、衣類、家具、本、アルバムなど
- 趣味の道具、コレクション品
- 書類、写真、手紙類
整理の基準
- 残すもの:現在使用している、思い出が深い、価値がある
- 譲るもの:使えるが自分には不要、誰かに喜んでもらえそう
- 捨てるもの:壊れている、長期間使用していない、重複している
感情のこもった品は後回しにして、捨てやすいものから始めましょう。
2. 財産の整理(通帳・保険・不動産・負債)
整理すべき項目
- 銀行口座(通帳、キャッシュカード)
- 保険証券(生命保険、損害保険)
- 不動産関係書類(権利証、固定資産税納税通知書)
- 有価証券(株式、債券、投資信託)
- 負債(借入金、ローン、クレジットカード)
通帳、保険証券、土地・建物、借入契約書などを一か所にまとめておくことが重要です。財産目録や一覧表を作っておくと、家族にとって非常に助けになります。
3. デジタルの整理(スマホ・SNS・パスワードなど)
整理対象
- スマホ、タブレット、パソコンのデータ
- SNSアカウント(LINE、X、Facebook、Instagram)
- ネットバンキング、証券会社のオンライン口座
- サブスクリプションサービス
- クラウドストレージ(Google Drive、iCloudなど)
今ではデジタル遺品の整理も欠かせません。スマホのロック解除方法や、各種アカウントの扱いも含めて、整理しておきましょう。
4. 人間関係・連絡帳の整理
整理すべき項目
- 年賀状リスト
- 電話帳、アドレス帳
- 緊急連絡先
- 訃報を知らせてほしい人のリスト
年賀状や電話帳、アドレス帳の見直しも意外と大事です。いざというときに連絡してほしい人をリスト化しておくと、家族も安心です。
5. 気持ちの整理(遺言書・エンディングノート)
記録しておきたいこと
- 財産の分配希望
- 葬儀・埋葬の希望
- 医療・介護に関する意向
- 家族へのメッセージ
- 人生の振り返り
「誰に何を伝えたいか」「どんな最期を迎えたいか」を記録しておくことは、気持ちの整理にもなります。法的効力のある遺言書に加え、自由記述ができるエンディングノートも活用しましょう。
身辺整理の具体的な進め方

身辺整理は大変に感じられるかもしれませんが、適切な手順を踏むことで無理なく進めることができます。ここでは、実際に多くの方が成功している5つのステップをご紹介します。重要なのは一気にやろうとせず、小さく始めてコツコツ続けることです。この方法なら、体力的・精神的な負担を最小限に抑えながら、着実に成果を上げることができます。
【STEP1】まずは小さく始める:捨てやすいモノから着手
最初に手をつけるべきもの
- 使っていない衣類(サイズが合わない、流行遅れ)
- 古い書類(期限切れの保証書、古いレシート)
- 重複している日用品
- 読まなくなった本や雑誌
目安時間:1日30分程度から始める
「できた感」を積み重ねていくことで、前向きな気持ちになれます。
【STEP2】カテゴリー分けと優先順位を決める
おすすめの順序
- 紙類の整理(1〜2週間)
- 衣類・日用品(2〜4週間)
- 財産関係(1〜2週間)
- デジタル関係(1週間)
- 思い出の品(じっくり時間をかけて)
何を優先して整理するかを決めておくと、混乱を防げます。計画的に進めることで、挫折せずに続けられます。
【STEP3】信頼できる人に相談・共有する
相談する内容
- 整理の進め方
- 判断に迷う物の取り扱い
- 財産や重要書類の保管方法
- 家族の希望や意見
一人で悩まず、家族や信頼できる友人に相談しましょう。客観的な意見をもらうことで、より良い判断ができます。
【STEP4】デジタル遺品や財産は書き残しておく
記録すべき情報
- スマホ・パソコンのパスコード
- 各種アカウントのID・パスワード
- 銀行口座情報
- 保険証券の保管場所
- 重要書類の保管場所
紙の管理表に記録し、保管場所を家族と共有しておくことが重要です。デジタルデータだけでなく、必ず紙にもバックアップを取りましょう。
【STEP5】定期的に見直す
見直しのタイミング
- 年に1回(誕生日や新年など)
- 生活環境が変わったとき
- 健康状態に変化があったとき
- 家族構成が変わったとき
一度整理しても、時間が経てば情報は古くなります。定期的なメンテナンスを心がけましょう。
年代別:身辺整理を始めるベストなタイミング

「いつから始めるべきか」が分からず先延ばしになってしまう人も多いのが現実です。しかし、年代によって体力や生活環境、優先すべき項目が異なるため、それぞれに適したタイミングと取り組み方があります。ここでは50代、60代、70代以上の年代別に、最適な開始時期と具体的な取り組み方法をご紹介します。自分の年代に合ったペースで始めることが、継続成功の鍵となります。
50代:準備期間として軽やかに始める
この年代の特徴
- まだ体力・気力が充実している
- 子どもの独立など生活環境の変化
- 老後を意識し始める時期
おすすめの取り組み
- 使わなくなった物の整理
- 重要書類の整理・保管
- 家族との話し合いの機会を作る
60代:本格的な身辺整理のスタート
この年代の特徴
- 退職による時間的余裕
- 健康への意識が高まる
- 相続について考え始める
おすすめの取り組み
- 全体的な物の整理
- 財産目録の作成
- エンディングノートの作成開始
70代以上:無理のない範囲で継続
この年代の特徴
- 体力的な制約が生じる可能性
- 判断力の衰えへの不安
- 家族のサポートが必要
おすすめの取り組み
- 家族と一緒に整理する
- 重要な部分から優先的に
- 専門家のサポートを活用
その他のきっかけ
病気や入院をきっかけにする
健康に不安を感じたときは、身辺整理を始める絶好の機会です。「気づいた時が始めどき」と捉えて前向きに取り組みましょう。
家族との話し合いを機にする
終活の話題をきっかけに、家族と将来について話すことはとても大切です。「整理しておくね」と伝えることで、家族も安心感を得られます。
よくある問題と対処法
身辺整理を始めてみると、思わぬ問題や困難に直面することがあります。「捨てられない」「時間がかかりすぎる」「家族が反対する」など、多くの人が同じような悩みを抱えています。ここでは、実際に整理を進める中でよく遭遇する問題と、それらを解決するための具体的な対処法をご紹介します。事前に対策を知っておくことで、スムーズに整理を進めることができるでしょう。
整理が進まない時の対処法
問題:「捨てられない」
- 対処法:「保留箱」を作り、1年後に再判断する
- 写真に撮って記録として残す
問題:「時間がかかりすぎる」
- 対処法:1日の作業時間を決める(30分〜1時間)
- 完璧を求めず、「今日はここまで」と区切る
問題:「何から始めればいいかわからない」
- 対処法:一番簡単な場所(引き出し1つ)から始める
- チェックリストを作って進捗を確認する
家族が反対する場合の対応
よくある反対理由
- 「縁起が悪い」
- 「まだ早い」
- 「勝手に捨てないで」
対応方法
- 「生活を快適にするため」と説明する
- 一緒に整理することを提案する
- 段階的に理解を求める
身辺整理チェックリスト
身辺整理の全体像を把握し、進捗を確認するためのチェックリストをご用意しました。このリストを活用することで、何をどこまで進めたか、まだ何が残っているかが一目でわかります。すべてを一度に完了する必要はありません。自分のペースで一つずつチェックを入れていき、達成感を味わいながら進めましょう。印刷して手元に置いておくと、より使いやすくなります。
物の整理
- ☐ 使わない衣類の処分
- ☐ 古い書類の整理
- ☐ 重複している日用品の整理
- ☐ 本・雑誌の整理
- ☐ 家具・家電の見直し
- ☐ 思い出の品の整理
財産の整理
- ☐ 銀行口座の整理・一覧作成
- ☐ 保険証券の整理
- ☐ 不動産関係書類の整理
- ☐ 有価証券の整理
- ☐ 負債の整理・一覧作成
- ☐ 財産目録の作成
デジタルの整理
- ☐ スマホ・パソコンの整理
- ☐ SNSアカウントの整理
- ☐ パスワード一覧の作成
- ☐ サブスクリプションサービスの見直し
- ☐ クラウドデータの整理
人間関係の整理
- ☐ 連絡先の整理
- ☐ 年賀状リストの見直し
- ☐ 緊急連絡先の作成
- ☐ 訃報連絡先リストの作成
気持ちの整理
- ☐ エンディングノートの作成
- ☐ 遺言書の検討
- ☐ 葬儀・埋葬の希望整理
- ☐ 家族へのメッセージ作成
まとめ:身辺整理は「人生の仕上げ」ではなく「生き方の再確認」
身辺整理は「死の準備」ではなく、「よりよく生きる」ための行動です。物や情報を整理することで、心にも余裕が生まれ、これからの人生をより自分らしく過ごすことができます。
今日から始められる3つのこと
- 使わない物を1つ処分する
- 重要な書類を1つの場所にまとめる
- 家族と終活について話し合う時間を作る
まずはできることから始めてみましょう。「いつかやろう」ではなく、「今、少しずつ」が未来の安心につながります。
整理は一度で完了するものではありません。人生と同じように、継続的に見直しながら、自分らしい生き方を見つけていくプロセスです。