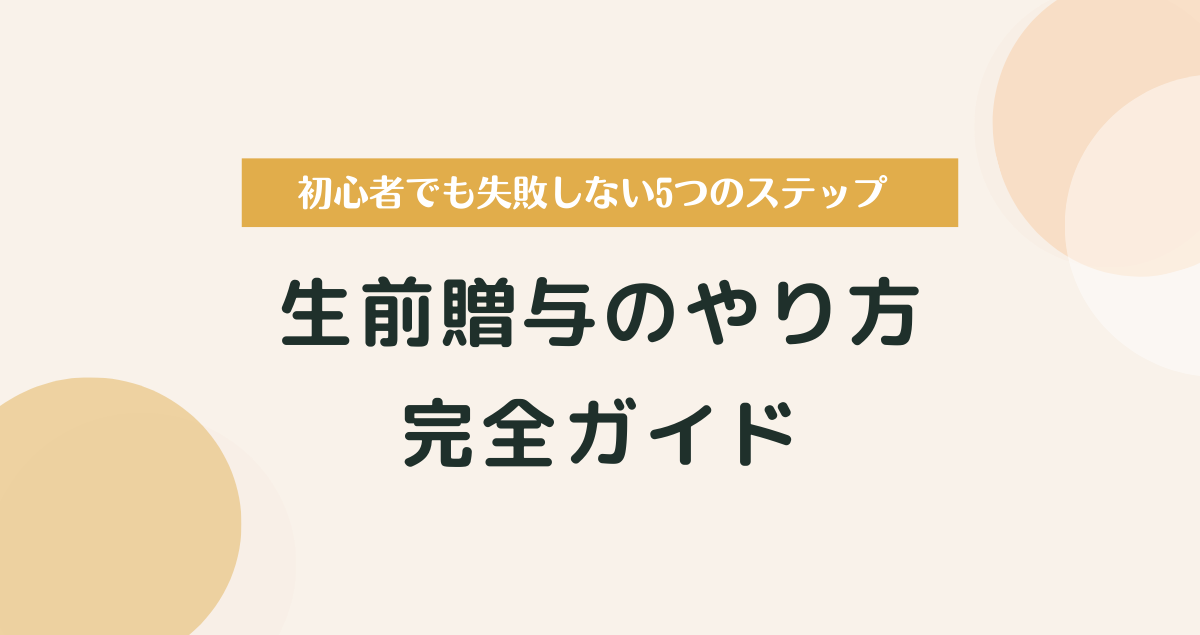「生前贈与をやってみたいけど、手続きが複雑そうで不安…」
「税制改正で何が変わったの?今からでも間に合う?」
そんな疑問をお持ちの方へ。
この記事では、生前贈与の基本的なやり方を、初心者でも迷わず実践できるよう分かりやすく解説します。
生前贈与とは?
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を子や孫などに無償で譲り渡すことです。相続が発生する前に行うため、相続税対策や家族間トラブルの予防に活用されています。
相続との主な違い

※一般に相続には相続税、贈与には贈与税が関係します。
| 項目 | 生前贈与 | 相続 |
|---|---|---|
| 実施時期 | 生存中 | 死亡後 |
| 受取人 | 自由に選択可能 | 法定相続人 |
| 税金 | 贈与税 | 相続税 |
| 効果 | 即座に財産移転 | 死亡時に移転 |
生前贈与を行う3つのメリット
- 相続税の負担軽減:計画的な贈与で将来の相続税を削減
- 子や孫の生活支援:教育資金や住宅購入資金の提供
- 遺産分割トラブルの回避:事前の財産整理で争族を防止
生前贈与のやり方【5つのステップで完全解説】

「生前贈与をやってみたいけど、何から始めればいいか分からない」という方のために、実際の手続きを5つのステップに分けて詳しく解説します。
ステップ1:誰に何を贈与するか決定する
まずは、贈与する相手と財産を決めます。配偶者や子、孫といった直系親族だけでなく、兄弟姉妹や第三者も対象にできます。
現金:銀行振込で行い、振込明細を保存(手渡しは避ける)
不動産:固定資産税評価額の確認、登録免許税・不動産取得税が発生
株式:評価額を算定し、証券会社で名義変更手続き
さらに、教育資金・住宅資金などには特例非課税制度が使える場合があります。
なお、2024年改正により「相続開始前7年以内の贈与」が持ち戻し対象となるため、時期選びも重要です。
ステップ2:贈与に合意する
贈与は贈与者だけの意思表示では成立しません。
「贈与する」「受け取る」という双方の合意が必要です。
特に子や孫への贈与では、受贈者(未成年の場合は親権者)が贈与を認識し、実際に管理していることを明確にしておきましょう。
ステップ3:贈与契約書を作成する
贈与契約は口頭でも可能ですが、税務調査やトラブルを避けるためには贈与契約書の作成が必須です。
- 双方の署名・押印
- 贈与財産の内容(所在地・通帳番号など正確に記載)
- 契約日
- 印鑑証明書の添付、公正証書化も有効
確定日付を公証役場で取得すれば、成立日を客観的に証明できます。契約書は贈与者・受贈者が1部ずつ保管しましょう。
ステップ4:贈与税の申告・納付
年間110万円を超える場合や、相続時精算課税・各種特例を使う場合は申告が必要です。
申告期限:翌年2月1日~3月15日
申告方法:税務署窓口、郵送、e-Tax
必要書類:贈与契約書の写し、戸籍謄本、財産評価資料、特例の場合は証明書や領収書
納付方法:現金納付、口座振替、クレジットカード、インターネットバンキング
2024年改正で、相続時精算課税制度にも基礎控除110万円が追加され、小額贈与にも活用しやすくなりました。
ステップ5:財産を受贈者へ移す
最後に、実際に財産を移転して完了です。
現金:銀行振込で口座へ入金し、通帳・カードは受贈者が管理
不動産:法務局で所有権移転登記を行う(契約書、印鑑証明、住民票、固定資産税評価証明などが必要)
株式:証券会社で名義変更を行う
また、不動産取得税が別途課税されるケースもあるため、納税通知に備えましょう。
振込明細、登記簿、証券残高報告書など移転の証拠を保管しておくと安心です。
生前贈与のケーススタディ

理論だけでなく、実際によくある贈与シーンを想定した具体例を見ることで、自分に当てはまるケースが見つかり、すぐに行動に移せます。
ケース1:現金を孫に贈与【最も一般的】
状況
- 祖父(75歳)が孫3人(小学生)に教育資金として贈与したい
- 贈与予定額:年間300万円(各100万円)
最適解
- 暦年課税を選択(各110万円以内で非課税)
- 各孫に年間100万円ずつ10年間継続
- 総額3,000万円を無税で移転可能
手続きの流れ
- 各孫名義の銀行口座開設(親が代理)
- 贈与契約書作成(年ごとに更新推奨)
- 毎年決まった時期に振込実行
- 通帳管理は各家庭に委託
ケース2:不動産を子に贈与【高額資産】
状況
- 父(65歳)が自宅土地建物(評価額3,000万円)を長男に贈与
最適解
- 相続時精算課税を選択
- 2,500万円まで贈与税なし、残り500万円に20%課税
- 贈与税額:(3,000万円-2,500万円)×20%=100万円
注意点
- 登録免許税:3,000万円×2%=60万円
- 不動産取得税:約90万円(軽減措置適用後)
- 総コスト:約250万円
ケース3:教育資金をまとめて贈与【特例活用】
状況
- 祖母(70歳)が孫(高校生)の大学費用として1,200万円贈与
最適解
- 教育資金一括贈与特例を活用
- 信託銀行等で専用口座開設
- 1,200万円全額非課税で贈与
管理のポイント
- 教育費支払時に領収書提出必要
- 30歳時点で残額があれば贈与税課税
- 年間管理手数料(数千円~1万円程度)
生前贈与の注意点
生前贈与は相続税対策や家族支援に役立ちますが、以下の注意点を知らずに行うと、
思わぬ課税やトラブルにつながる可能性があります。
- 名義預金に注意:子や孫名義の口座に入金しても、通帳や印鑑を親が管理している場合は「実質的に贈与が成立していない」とみなされます。
- 持ち戻しルール:2024年改正で「相続開始前7年以内の贈与」は相続財産に加算されることになりました。長期的な計画が大切です。
- 贈与契約書の作成:税務署に否認されないためには、必ず契約書を作り、日付・署名・押印を残しましょう。
- 贈与税の申告漏れ:特例を使わない場合でも110万円を超える贈与は申告が必要です。申告漏れは追徴課税のリスクがあります。
- 不動産贈与のコスト:登録免許税・不動産取得税・司法書士費用など、贈与税以外の費用も発生します。
2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルールや、相続時精算課税制度に基礎控除110万円が追加されるなどの変更がありました。制度選択の際は必ず最新情報を確認してください。
参考:国税庁|贈与税(暦年課税・相続時精算課税) /
財務省|令和5年度税制改正大綱
よくある質問(FAQ)
Q1. 年間110万円までなら申告しなくてもよい?
はい。暦年課税制度では年間110万円までは非課税枠内であり、申告不要です。
ただし、証拠として契約書や振込記録を残しておくと安心です。
Q2. 相続時精算課税と暦年課税は途中で変更できる?
一度「相続時精算課税」を選択すると、原則として暦年課税には戻せません。
選択前に税理士など専門家にシミュレーションしてもらうことをおすすめします。
Q3. 子どもが未成年でも贈与は可能?
可能です。ただし、親権者が代わりに手続きを行います。
この場合も「子ども名義の口座」を用い、子ども自身の財産として管理する必要があります。
Q4. 贈与契約書は手書きでないと無効?
手書きでもワープロ作成でも有効です。
ただし、署名は直筆、印鑑は実印を使うことが推奨されます。
公正証書化すればより確実です。
Q5. 不動産を贈与するときの税金は?
贈与税のほかに、登録免許税(固定資産税評価額×2%)や不動産取得税がかかります。
軽減措置があるケースもあるので、必ず事前に確認しましょう。
まとめ:生前贈与で確実に節税するために
生前贈与は早く始めるほど節税効果が大きいため、まずは年間110万円以内の暦年贈与から着実にスタートしましょう。
財産の整理と相続税試算を行い、10年単位の長期計画を立てて専門家に相談しながら進めましょう。
高額贈与や不動産・株式の贈与は必ず税理士等に確認するのが安心です。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。