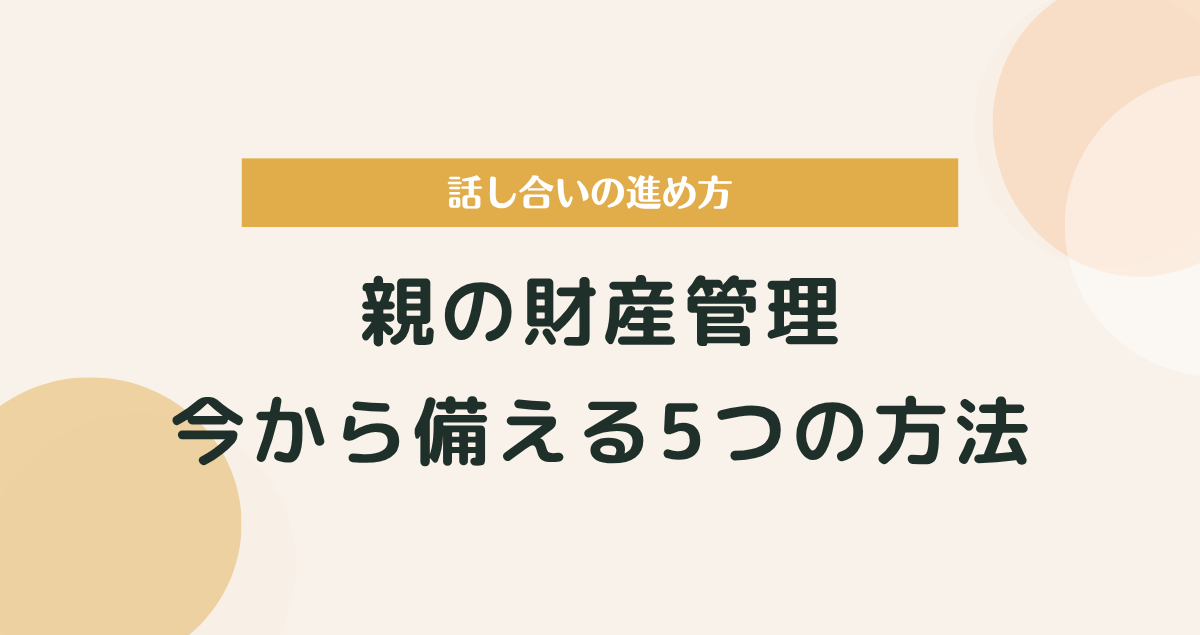「親の財産、どう管理すればいいの?」
親が高齢になり、もしものときに備えたいと思いつつ、話を切り出せないまま時が過ぎていませんか?
実は認知症患者の約7割で、財産管理に何らかの問題が生じているというデータもあります。
元気なうちに「財産管理」の準備をしておくことが、家族全体の安心につながります。
本記事では、親の財産管理の基本から制度の選び方、親への切り出し方まで、具体的なステップで解説します。
目次
親の財産管理が必要になる理由

親の財産管理は「相続」の話だけではありません。むしろ、親が元気なうちに準備しなければ間に合わないケースが多く存在します。
判断力が低下した後では「手続き不可」に
財産管理の多くは、親の「同意」が必要です。一度認知症などで判断能力が著しく低下すると、以下のような問題が発生します:
- 銀行口座の凍結:本人以外の引き出しができなくなる
- 不動産の売却不可:介護費用のために自宅を売りたくても手続きできない
- 保険の解約や変更不可:必要な保険金の受け取りができない
こうなると成年後見制度などを使わなければ対応できず、手続きに数ヶ月かかることもあります。
相続・介護トラブルの火種になる前に
よくあるトラブル例
- 「兄が勝手にお金を動かしていた」
- 「親の意思がわからない」
- 「介護費用を誰が負担するのか揉めている」
事前に話し合いと制度活用をしておくことで、家族全体が納得できる形に導けます。
親の財産を管理する5つの方法【比較表あり】
| 方法 | 始めやすさ | 認知症後の有効性 | 法的効力 | 費用 | 手続き期間 | 相続対策との相性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意後見 | △ | ◎ | ◎ | 中 | 1〜2ヶ月 | △ |
| 家族信託 | △ | ◎ | ◎ | 高 | 1〜3ヶ月 | ◎ |
| 委任契約 | ◎ | × | ○ | 低 | 2〜4週間 | △ |
| 法定後見 | × | ◎ | ◎ | 中 | 2〜4ヶ月 | × |
| 代理人登録 | ◎ | × | × | 低 | 即日 | × |
親の財産管理にはいくつかの制度があります。それぞれ特徴が異なるため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
1. 任意後見制度
将来、認知症などで判断力が低下したときに備えて、事前に信頼できる人を後見人として指定しておく制度です。
特徴
- 認知症になる前に契約が必要
- 法的に強力な効力がある
- 家庭裁判所の監督下に置かれる
- 費用目安:公証役場手数料2〜3万円、司法書士報酬10〜20万円
2. 家族信託
家族に財産の管理や処分を託す仕組みです。親が元気なうちに組成し、自由度が高いのが特徴です。
特徴
- 財産の運用・管理に柔軟に対応できる
- 認知症後でも信託契約に基づき対応可能
- 専門家のサポートが必要(信託契約書の作成など)
- 費用目安:信託財産の0.5〜1%程度(最低30万円〜)
3. 財産管理委任契約
財産管理を誰かに委任する契約。任意後見と似ていますが、より柔軟に設計できます。
特徴
- 代理人による口座管理や支払いが可能
- 本人の意思能力があるうちからスタート可能
- 後見制度のような法的保護は弱め
- 費用目安:公証役場手数料1〜2万円、司法書士報酬5〜15万円
4. 法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
特徴
- 家庭裁判所への申し立てが必要
- 後見人は裁判所が選任(家族とは限らない)
- 手続きに2〜4ヶ月かかる
- 費用目安:申立費用3〜4万円、後見人報酬月額2〜6万円
5. 共有口座・代理人登録
もっとも簡易的な方法ですが、リスクもあります。
特徴
- 金融機関によっては制限される
- 相続時に「贈与」とみなされるリスクあり
- トラブルになりやすい
- 費用目安:ほぼ無料
親にどう切り出す?話し合いの進め方
制度の前に大切なのは、家族での話し合いです。「財産のことなんて聞きにくい…」という声も多いですが、伝え方とタイミングを意識することで自然に進めることができます。
「元気なうちに」がベストタイミング
親にとっても、自分の意志で選べるうちに話をしてもらった方が安心です。以下のタイミングを狙いましょう:
- 生活の節目:退職、引っ越し、病気の回復後など
- 身近な出来事:知人の相続話、テレビのニュースなど
- 家族の集まり:お盆、正月、誕生日など
会話の切り出し例
避けたい表現
- 「財産の話をしたい」
- 「相続について決めておこう」
- 「認知症になったら困る」
おすすめの切り出し方
- 「最近テレビで財産管理の話を見て…」
- 「自分たちも親のこと、考えておきたいなと思って」
- 「急なことがあったとき、何も分からないと不安だからさ」
- 「○○さんのお話を聞いて、うちも準備しておいた方がいいのかなと」
ポイント
「財産の話」よりも「家族の安心」の話から始めると、角が立ちません。
話し合いで確認すべきこと
- 親の希望を聞く
- 口座の管理を誰に任せたいか
- 将来の住まいについて
- 葬儀や供養の希望
- 現状を把握する
- 財産の全体像
- 重要な書類の保管場所
- かかりつけ医や薬の情報
- 家族の役割分担
- 誰が中心になって管理するか
- 他の兄弟姉妹への情報共有方法
- 緊急時の連絡体制
ケース別:親の財産管理の選び方

どの制度を使えばよいかは、親の状態や家族の構成によって異なります。
【ケース1】親が元気で財産もそれなりにある場合
おすすめ:家族信託
- 不動産の管理・売却が柔軟にできる
- 相続税対策も同時に進められる
- 認知症になっても継続して機能する
具体例
田中さん(75歳)は自宅と賃貸アパートを所有。長男に家族信託で管理を委託し、将来の介護費用や相続税対策を同時に進めた。
【ケース2】親が元気だが財産がそれほど多くない場合
おすすめ:任意後見契約 + 財産管理委任契約
- 費用を抑えて必要な範囲で対応
- 段階的にサポートを強化できる
具体例
佐藤さん(78歳)は年金と預金が中心。娘と財産管理委任契約を結び、将来に備えて任意後見契約も併せて締結した。
【ケース3】すでに認知症の兆候がある場合
おすすめ:法定後見制度
- 新たな契約は難しい状況
- 家庭裁判所の手続きが必要
- 医師の診断書が必要
具体例
山田さん(82歳)は軽度認知症と診断済み。家族が法定後見の申し立てを行い、専門職後見人が選任された。
【ケース4】相続や不動産も含めて整理したい場合
おすすめ:家族信託 + 遺言書の併用
- 生前の財産管理と相続対策を一体化
- 複雑な相続関係にも対応可能
- 専門家(司法書士・弁護士・税理士)との連携が重要
今すぐ始めるためのチェックリスト

「まだ早いかな」と思っていても、今日からできることはあります。以下のステップを参考に準備を始めましょう。
STEP1:財産の棚卸しをする
金融資産
- 銀行口座(普通預金・定期預金)
- 証券口座(株式・投資信託)
- 保険(生命保険・医療保険)
- 年金(国民年金・厚生年金・企業年金)
不動産
- 自宅(土地・建物)
- 投資用不動産
- 農地・山林
その他
- 借金やローン
- 貸付金
- 骨董品・貴金属
ポイント
一覧にすることで、全体像がつかめます。通帳や権利証の保管場所も確認しておきましょう。
STEP2:家族内の認識合わせ
親の希望を確認
- 財産の管理方法について
- 将来の住まいについて
- 葬儀や供養について
- 延命治療について
兄弟姉妹との情報共有
- 親の財産状況
- 介護の方針
- 役割分担
- 緊急時の連絡体制
ポイント
あらかじめ認識をそろえておくことで、後のトラブルを防げます。
STEP3:専門家に相談する
相談先の選び方
- 司法書士:信託契約や後見手続きのプロ
- 弁護士:トラブルや相続に強い
- 税理士:相続税対策の相談に最適
- 金融機関:信託銀行は家族信託に対応
相談時に準備するもの
- 財産の一覧表
- 家族構成図
- 親の希望をまとめたメモ
- 予算の目安
ポイント
まずは無料相談からでも始めてみましょう。複数の専門家に相談して比較検討することも大切です。
よくある質問(Q&A)
Q1:費用はどのくらいかかりますか?
A:制度により異なりますが、目安は以下の通りです
- 家族信託:30万円〜100万円(財産額による)
- 任意後見:20万円〜30万円
- 財産管理委任契約:10万円〜20万円
- 法定後見:初期費用3万円+月額2〜6万円
Q2:親が財産管理の話を嫌がる場合はどうすればいい?
A:段階的なアプローチがおすすめです
- まず「家族の安心」の話から始める
- 具体的な事例を交えて説明する
- 「今すぐ決めなくても、選択肢を知っておこう」というスタンスで話す
- 専門家から説明してもらう
Q3:兄弟姉妹で意見が分かれた場合はどうする?
A:中立的な専門家を交えた話し合いが有効です
- 家族会議に司法書士や弁護士に参加してもらう
- 親の意志を最優先に考える
- 役割分担を明確にする
Q4:すでに認知症になっている場合は手遅れ?
A:法定後見制度が利用できます
- 医師の診断書が必要
- 家庭裁判所への申し立て
- 手続きに2〜4ヶ月かかる
選択肢は限られますが、対応可能です。
まとめ:親の財産管理は「今」から始めよう
親の財産管理は、「いつか」ではなく「今」始めることが重要です。
重要なポイント
- 元気なうちに準備する:判断能力が低下してからでは選択肢が限られる
- 制度を正しく選ぶ:家族の状況に応じて適切な制度を選択する
- 家族で話し合う:タイミングと伝え方を工夫して自然に進める
- 専門家を活用する:複雑な手続きは専門家のサポートを受ける
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。