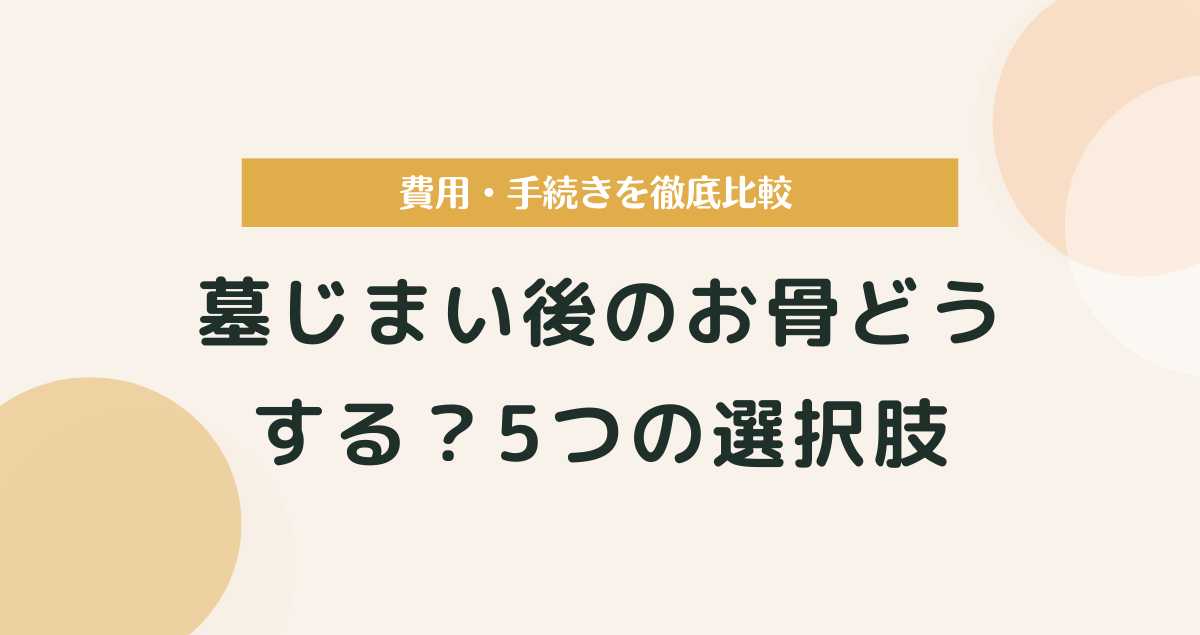お墓の後継者がいない、管理費が払えない、遠方で通えないなどの理由から墓じまいを考える方が増える一方で、その後のお骨の扱いに迷うケースが少なくありません。
本記事では、お骨の行き先としての5つの選択肢を比較し、それぞれの特徴や手続き、費用、気をつけたいポイントまで徹底解説します。
目次
墓じまい後に知っておくべきお骨の扱い方

墓じまい=遺骨の移動と再供養
墓じまいとは、既存の墓を撤去し、納められていた遺骨を別の場所へ移す「改葬」のことを指します。
単に墓石を撤去するだけでは完了しません。遺骨をどう扱うかを家族で話し合い、正式な手続きを踏む必要があります。
墓じまい後のお骨の行き先5つを比較
| 方法 | 特徴 | 費用目安 | 継承者 |
|---|---|---|---|
| ① 改葬 | 新しいお墓や納骨堂へ移す伝統的な方法 | 30〜100万円 | 必要 |
| ② 永代供養・樹木葬 | 管理不要で寺院や霊園が供養 | 5〜30万円 | 不要 |
| ③ 散骨 | 自然へ還す自由葬のスタイル | 5〜15万円 | 不要 |
| ④ 手元供養 | 遺骨の一部を自宅で保管 | 3千〜5万円 | 不要 |
| ⑤ 自宅保管 | 全骨を自宅に安置 | 無料 | 不要 |
① 改葬(他のお墓・納骨堂・合祀墓)

- 特徴:遺骨を新しいお墓や納骨施設に移す一般的な方法。法的手続き(改葬許可証)が必要。
- 費用目安:30〜100万円(墓石代・永代使用料・管理費を含む)
- おすすめ:継承者がいて、伝統的な供養を重視したい方。家族でお参りを続けたい方。
実例:Aさん(60代)
「遠方の実家の墓を管理できないため、自宅近くの霊園に改葬しました。年2回のお参りが楽になり、家族も安心しています。」
② 永代供養・樹木葬

- 特徴:お寺や霊園が供養と管理を代行。一定期間個別で納め、その後合祀されるタイプが一般的。樹木葬は自然志向の方に人気。
- 費用目安:5〜30万円(個別期間・法要費含む)
- おすすめ:継承者がいない方、子どもに負担をかけたくない方、管理の手間を省きたい方。
実例:Bさん(70代)
「子どもたちに負担をかけたくないので永代供養を選択。年1回の合同法要で十分供養されている実感があります。」
③ 散骨(海・山・空)

- 特徴:遺骨を粉末化して海や山などに撒く方法。自然へ還す自由な葬送スタイル。
- 費用目安:5〜15万円(粉骨・船代・代行費など)
- おすすめ:自然を愛する方、宗教的な形式にとらわれたくない方、故人の遺志が散骨の方。
実例:Cさん(50代)
「海が好きだった父の遺志で海洋散骨を選択。家族で船に乗り、思い出話をしながら見送ることができました。」
④ 手元供養(ミニ骨壺・アクセサリー)

- 特徴:遺骨の一部を小さな骨壺やペンダントなどに納めて自宅で供養。いつでも故人を感じられる。
- 費用目安:3千〜5万円(骨壺・アクセサリー代など)
- おすすめ:故人を身近に感じたい方、費用を抑えたい方、他の供養方法と併用したい方。
⑤ 自宅保管(全骨を安置)
- 特徴:全ての遺骨を自宅に安置する方法。費用がかからず、いつでもそばに感じられる。
- 費用目安:無料(専用仏壇などを設ける場合は別途数万円)
- おすすめ:一時的な保管を考えている方、他の選択肢を検討中の方。
改葬に必要な書類と注意点

改葬に必要な書類は以下のとおりです。
- 改葬許可申請書(新旧の墓地管理者の証明)
- 埋葬証明書
- 戸籍の附票(自治体によって必要)
各自治体の窓口で手続きできます。書類の不備があると時間がかかるため注意が必要です。
散骨の法的留意点
散骨は「葬送の一形態」とされ違法ではありませんが、以下に注意してください。
- 必ず粉骨処理が必要(焼骨をそのまま撒くのはNG)
- 散骨可否は自治体ごとに異なる
- 海洋散骨では環境省・国交省のガイドラインも要確認
よくある疑問Q&A
Q1. お骨を分けても大丈夫?
A. 分骨は法的に問題ありません。分骨証明書を発行してもらえば、一部を手元供養、残りを永代供養といった組み合わせも可能です。
Q2. 手続きにどのくらい時間がかかる?
A. 改葬の場合は1〜3ヶ月、永代供養は数週間程度が目安です。書類の準備期間も含めて余裕を持って計画しましょう。
Q3. 家族の反対があった場合は?
A. まずは家族会議を開き、それぞれの想いを聞くことから始めましょう。複数の選択肢を提示し、妥協点を見つけることが大切です。
Q4. 費用が払えない場合は?
A. 自治体によっては低所得者向けの支援制度があります。また、分割払いが可能な霊園も増えています。
Q5. 後から変更はできる?
A. 散骨や合祀墓は基本的に変更不可。永代供養や納骨堂は条件によって可能な場合があります。
まとめ|墓じまい後のお骨の行き先は「想い」と「状況」に合わせて選ぼう
「墓じまい後のお骨をどうするか?」という問いに、唯一の正解はありません。供養・費用・手続き・家族の想いのバランスをとりながら、最適な選択をすることが何より大切です。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。