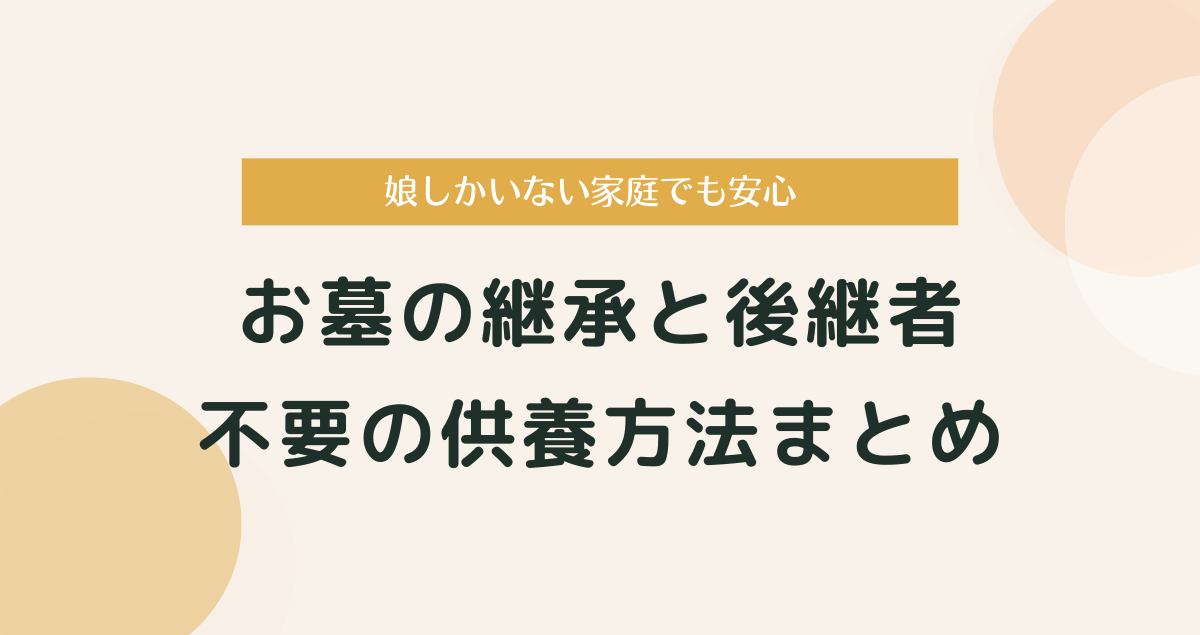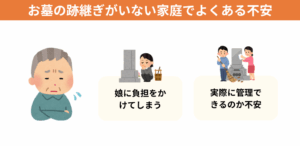「うちは娘しかいないけど、お墓はどうなるの…?」
「後継ぎがいなくて、お墓の管理が不安…」
少子化や核家族化が進む今、こうした悩みは多くの家庭に共通しています。
本記事では、娘しかいない家庭でも安心できるお墓の承継方法や、後継者不要の供養方法をわかりやすく解説します。
目次
お墓の跡継ぎがいない家庭でよくある不安
娘しかいない家庭や跡継ぎがいない家では、お墓を誰が守るかが大きな心配事です。ここでは、よくある悩みを整理します。
娘に負担をかけてしまう心配
結婚や転居で名字や住所が変わると、娘にお墓の管理を任せる負担が大きくなります。
- 遠方に住むと掃除や法要に通うのが大変
- 経済的・心理的な負担を心配する親も多い
実際に管理できるのかという現実的な問題
お墓の管理には、日常的な手間が伴います。高齢になってから娘に全てを任せるのは不安が残ります。
- 墓地の掃除や草取り
- 法要やお寺とのやり取り
- 交通費や時間の負担
娘でもお墓を継げる?法的な根拠と注意点

法律では、娘でも問題なくお墓を継ぐことができます。民法の規定を理解し、安心して準備を進めましょう。
民法第897条による祭祀承継
民法では、性別や名字に関係なくお墓などの「祭祀財産」を承継できることが明記されています。
遺言や家族の合意で承継者を指定することも可能です。
- 承継は性別・名字を問わない
- 遺言書があればさらに確実
民法第897条では、祖先の祭祀を主宰すべき者がこれらを承継すると定めており、祭祀財産は相続財産とは別枠で承継される点が重要です。
トラブルを避けるためには、遺言で祭祀承継者を明確に指定しておくと安心です。
祭祀承継者とは
祭祀承継者はお墓や仏壇、位牌を引き継ぎ供養を行う人です。相続とは異なり、借金などは承継しません。
- お墓の管理・法要を行う人
- 財産や負債とは別枠で承継可能
後継ぎがいなくても安心の供養方法4選
跡継ぎがいなくても、近年は後継者不要の供養方法が豊富です。永代供養・樹木葬・納骨堂・合祀墓の特徴を解説します。
| 方法 | 費用目安 | 維持費 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 永代供養 | 10〜50万円 | なし | 供養・管理を寺院や霊園に任せられる |
| 樹木葬 | 20〜60万円 | なし | 自然志向で宗教不問、後継者不要 |
| 納骨堂 | 30〜100万円 | 年1〜3万円 | 屋内で便利、天候に左右されない |
| 合祀墓 | 5〜20万円 | なし | 費用が安く、無縁仏にならない |
娘に負担をかけないために親ができる準備

事前準備をすることで、娘の精神的・経済的な負担を大幅に軽減できます。
生前整理を始める
60〜70代のうちに準備を始めると、余裕を持って選択できます。
- 供養方法を決める
- 娘と話し合いをする
- エンディングノートに記録する
生前契約や死後事務委任契約
葬儀や遺品整理、納骨などを専門家に任せられる契約。遠方の娘でも安心です。
デジタル遺品の整理
スマホ・PC・SNSなどの情報は生前に整理しておきましょう。
- ID・パスワードを安全に管理
- 家族が困らないように準備
まとめ|跡継ぎがいなくても安心できるお墓の選び方
娘しかいない家庭でも、後継者不要のお墓や供養方法を選べば安心です。
- 娘でも法的にお墓を継ぐことは可能
- 永代供養・樹木葬など現代的な方法が充実
- 早めの準備で家族の負担を軽減できる
まずは家族で話し合い、納得できる供養の形を見つけましょう。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。