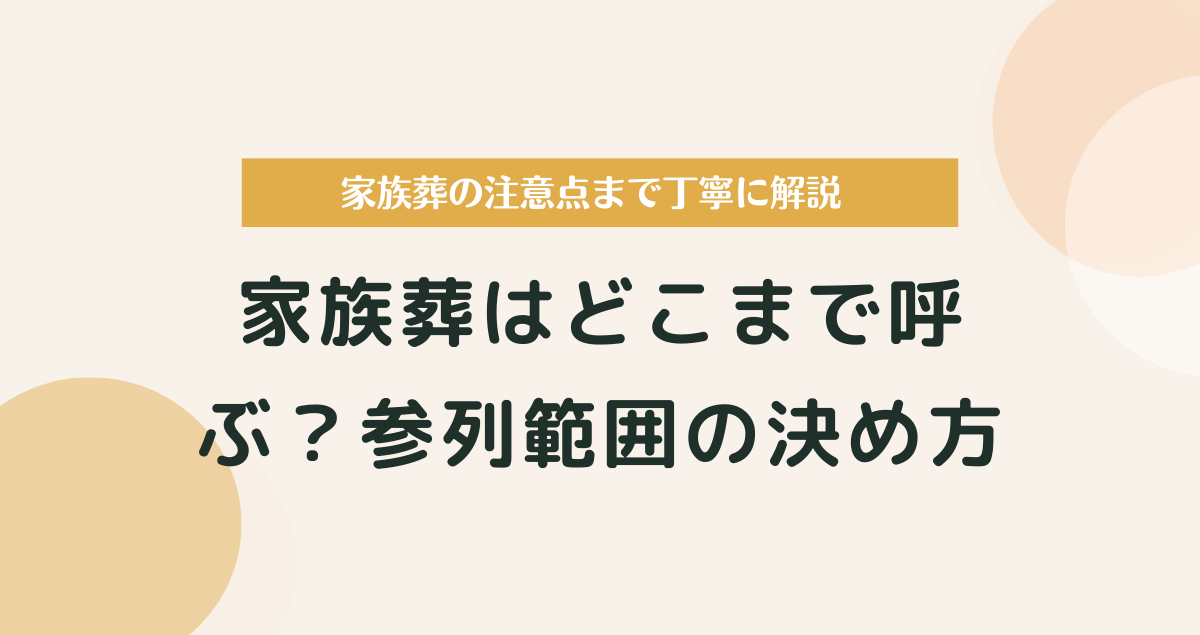「家族葬でどこまで呼ぶか」。親族だけにするのか、どこまで知らせるのか──多くのご遺族が最初に迷うポイントです。
本記事では、参列範囲を“親等”という客観的な基準で整理し、決め方と注意点を中立的に解説します。
目次
家族葬とは?一般葬との違い
家族葬は、親族やごく親しい関係者のみで行う小規模なお葬式です。形式に縛られにくく、静かに見送れる一方、
「誰まで呼ぶか」の線引きが課題になります。
参列範囲は“親等”で考える

※数字は親等を示しています。灰色の枠は姻族(配偶者関係)を表します。
一親等(もっとも近い家族)
配偶者・父母・子。多くの場合、家族葬の中心となる範囲です。
二親等(兄弟姉妹・祖父母・孫など)
関係が深い場合や生前から交流がある場合は参列をお願いすることも。
別世帯であることが多いため、状況に応じて柔軟に検討します。
三親等(おじ・おば・おい・めい・ひ孫など)
知らせる・後日報告にとどめるケースもありますが、特に親しい間柄であれば参列を依頼することもあります。
姻族(子の配偶者・孫の配偶者など)の扱い
姻族は血族ではありませんが家族行事に関わることがあります。
図では点線や淡色の枠で区別し、血族と混同しないように表現します。
決め方のポイント
- 故人の意向:生前の希望や価値観を最優先に。
- 遺族の負担:会場規模・返礼・受付・移動など現実的な負担を見積もる。
- 家族内の合意:後日の説明・報告方法(会葬礼状、弔問の受け入れ等)も含め共有。
参列できなかった方への配慮
家族葬では「呼べなかった方」が生じます。後日のご報告やご挨拶で関係が円滑になります。
伝え方の例文
・「葬儀は近親者のみで執り行いました。改めてご挨拶申し上げます。」
・「故人の意向により、葬儀は家族のみで行いました。」
よくある質問(FAQ)
Q1. 家族葬に友人を呼んでもよいですか?
問題ありません。
家族葬は「家族だけに限定する葬儀」ではなく、小規模で親しい人を中心に行う形式です。
故人と特に親しかった友人を招くことも自然な選択です。
Q2. 会社関係者には連絡すべき?
勤務先や取引先など、仕事関係者には基本的に訃報と葬儀の形式(家族葬で行う旨)を伝えるだけで十分です。
参列を控えてもらう場合は「故人の意向により、参列はご遠慮いただいております」と明記しましょう。
Q3. 遠方の親戚にも知らせるべき?
二親等以内であれば、距離に関係なく連絡するのが一般的です。
三親等以降の親戚には、葬儀後に報告する形でも問題ありません。
Q4. 香典を辞退したいときはどうすれば?
案内文に「誠に勝手ながら香典のご厚志はご辞退申し上げます」と記載しておきます。
受付の混乱を防ぐためにも、事前に明示しておくと安心です。
Q5. 家族葬の後にお別れ会を開いてもいい?
もちろん可能です。
家族葬では身内だけで見送り、後日改めて「お別れ会」や「偲ぶ会」として関係者を招く形式も増えています。
まとめ
家族葬で「どこまで呼ぶか」に絶対の正解はありません。
“親等”という客観的な軸で家族構成を整理し、故人の意向・遺族の負担・家族内の合意を踏まえて決めることで、納得感のある形に近づけます。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。