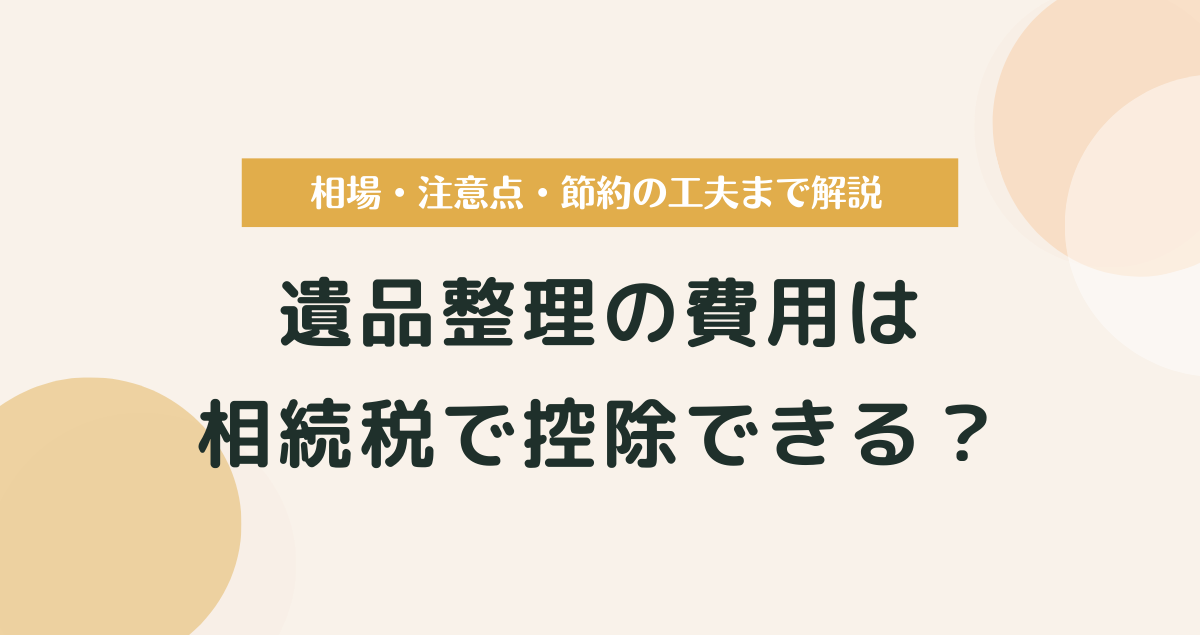遺品整理を進める際、多くの方が最初に気になるのは「費用は相続税の控除対象になるのか?」という点です。
結論からいえば、遺品整理の費用は原則として相続税の控除対象外です。
ただし、費用を少しでも抑える工夫や、相続手続きと同時に進めることで負担を軽減できる方法はあります。
本記事では、相続税と遺品整理費用の関係、相場の目安、よくある疑問、実際に使える節約策までを詳しく紹介します。
目次
遺品整理費用は相続税で控除できる?
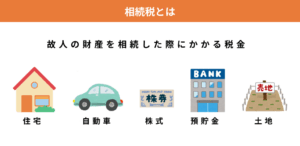
遺品整理の費用が相続税で控除できるかどうかは、多くの遺族が抱える最初の疑問です。
遺品整理費用は、控除対象外が原則
相続税の計算では、被相続人が生前に負っていた債務や未払い金は「債務控除」として差し引けます。
一方、遺品整理の費用は相続発生後に遺族が負担する費用と位置づけられ、控除の対象にはなりません。
「葬式費用」との違い
葬式にかかった会場費や火葬費などは相続税の控除対象になり得ますが、遺品整理に要した費用は含まれません。
名称や領収書の有無ではなく、費用の性質の違いがポイントです。
誤解されやすいケース
- 業者の領収書があれば控除できる → 誤り
- 相続財産から支払えば節税になる → 控除可否には影響しない
遺品整理の費用相場と内訳

控除対象にはならないものの、遺品整理には一定の費用が発生します。
相場の目安と内訳を把握すれば、無駄のない見積もり依頼や比較が可能になります。
間取り別の平均費用
費用は住居の広さと荷物量で大きく変わります。以下は目安です。
| 間取り | 目安費用 |
|---|---|
| 1K・1DK | 3万〜8万円 |
| 2DK・2LDK | 10万〜25万円 |
| 一戸建て(3LDK以上) | 30万〜80万円 |
内訳:作業費・人件費・処分費など
- 基本作業費(仕分け・搬出)
- 人件費(作業人数・時間に比例)
- 処分費(粗大ごみ・リサイクル費用)
- オプション(仏壇・車両撤去・特殊清掃など)
費用を左右する要因
- 荷物量の多さ
- 搬出条件(階段のみ、駐車場の有無など)
- 繁忙期(春・秋は高額になりやすい)
相続税と遺品整理に関するよくある疑問

控除関係はシンプルでも、実務上は相続手続きや税務と絡む場面が少なくありません。
代表的な疑問をQ&A形式で紹介します。
遺品整理で出た収益物は課税対象?
整理の過程で発見された現金や貴金属は相続財産に含まれます。
不動産を売却する場合は譲渡所得税の対象になる可能性があります。
相続放棄をした場合、費用は誰が負担する?
相続放棄をすると原則として費用負担もしません。
ただし実務上は親族間で分担するケースもあります。
遺品整理と相続登記の関係
不動産を相続する場合、遺品整理と相続登記は並行して進める必要があります。
登記を放置すると売却や名義変更ができません。
遺品整理と相続手続きを同時に進めるコツ

遺品整理と相続手続きを分けて考えると非効率になりがちです。
スケジュールを意識して同時に進めることが、時間と費用の節約につながります。
死後〜10か月までのタイムライン
- 死亡届の提出・葬儀の手配
- 財産・負債の把握
- 遺品整理業者の依頼と作業
- 遺産分割協議
- 相続登記・名義変更
- 相続税の申告・納付(10か月以内)
チェックリストで漏れを防ぐ
- 銀行口座の凍結と解約
- 不動産の相続登記準備
- 遺品整理業者の手配と立ち会い
- 税務申告用の領収書の保管
遺品整理と相続税に関するよくある質問
遺品整理費用を相続財産から支払ったら控除できる?
多くの方が誤解しやすいポイントですが、遺品整理費用を相続財産から支払っても控除はできません。
相続税の「債務控除」の対象になるのは、被相続人が生前に負っていた借金や未払い費用などです。遺品整理は相続発生後に遺族が任意で行う作業であり、相続財産の減額要件には該当しません。
したがって、領収書を残していても税務上は控除できない点に注意が必要です。
例外的に遺品整理費用が控除されることはある?
原則として遺品整理費用は控除の対象外ですが、非常に限定的なケースで検討されることがあります。
たとえば、特殊清掃や災害による遺品処理など、葬儀や遺体処理と不可分な形で発生した費用は、葬式費用として一部が認められる可能性もあります。
ただし、税務署の判断に委ねられる部分が大きいため、税理士など専門家に相談するのが安全です。
葬式費用として控除できるもの・できないものは?
葬式費用として控除できる代表例は次のとおりです。
・通夜・告別式の会場費や祭壇費
・火葬・埋葬・納骨にかかる費用
・遺体の搬送費・捜索費用
・読経料やお布施など、葬儀に直接関わる謝礼
一方、以下の費用は控除対象外です。
・香典返しの費用
・墓石や位牌、仏壇などの購入費用
・四十九日など法要にかかる費用
控除の可否は「葬儀に直接必要だったかどうか」が判断基準になります。
遺品整理で出た売却品や現金は課税対象になる?
遺品整理中に見つかった現金や貴金属、骨董品などは相続財産として扱われます。
これらは相続税の課税対象となるため、相続財産として申告が必要です。不動産や高額品を売却して利益が出た場合は、別途譲渡所得税の対象になることもあります。
価値のある品を整理中に発見した場合は、専門家に評価額を確認しておくと安心です。
相続放棄をした場合、遺品整理費用はどうなる?
相続放棄をした人は原則として費用負担の義務がありません。
ただし、実際には親族間で協力して整理を進めるケースも多く、費用を分担したり一部を自己負担することもあります。
税務上は相続放棄後に支払った遺品整理費用でも控除は認められないため、あくまで「実務上の負担」として考えるのが現実的です。
遺品整理費用を節約するにはどうすればいい?
税控除はできませんが、費用を抑える工夫は可能です。
複数業者に見積もりを依頼する、不要品を買取に回す、繁忙期を避けるといった方法で、全体のコストを2〜3割削減できることもあります。
また、自治体の粗大ごみ回収を併用する、遺族で仕分けを先に行っておくなども有効な節約策です。
まとめ|費用と相続税を正しく理解して賢く進めよう
- 遺品整理費用は相続税控除の対象外
- 葬式費用との違いを理解することが重要
- 複数見積もりや不用品買取で負担を軽減できる
- 相続手続きと同時に進めると効率的
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。