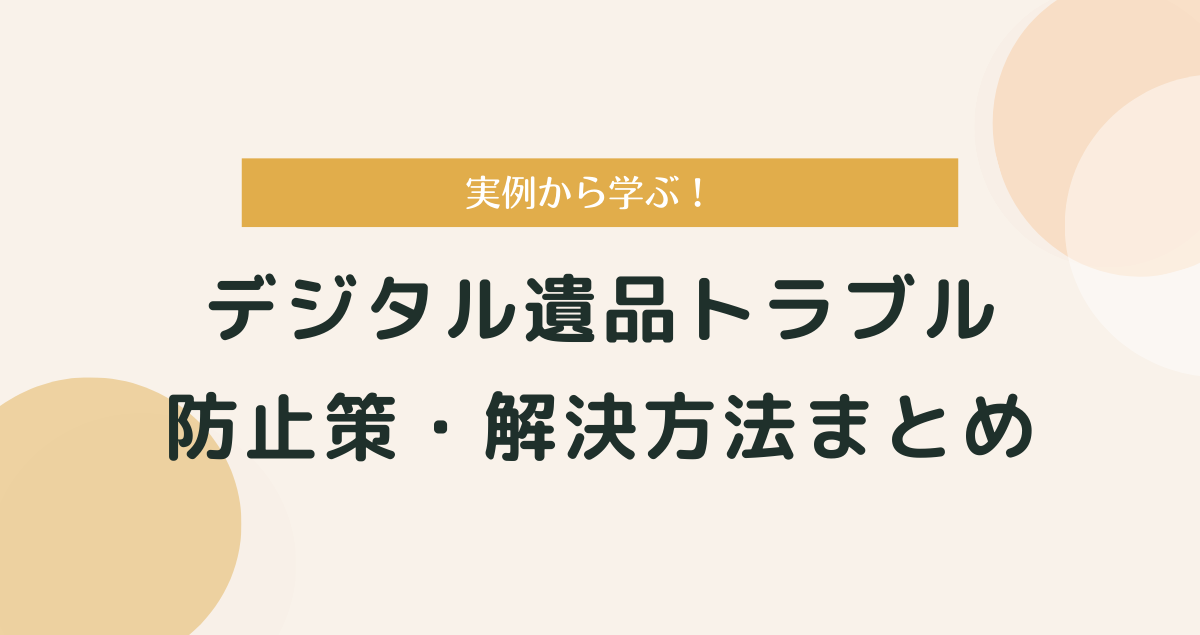スマホやパソコンのロックが解除できない、ネット銀行の口座がわからない──。
そんな「デジタル遺品」のトラブルが、残された家族を悩ませています。
この記事では、実例をもとにした防止策と解決方法を紹介。今からできる備えで、いざという時に備えましょう。
よくあるデジタル遺品トラブル事例
スマホやPC、ネット銀行、SNSなど、私たちの生活は多くのデジタル情報であふれています。
これらは、亡くなった後に”遺品”として残され、適切に管理されなければ思わぬトラブルにつながることがあります。
ここでは、実際に起こりやすい事例を紹介します。
故人の友人や知人に連絡が取れない
スマホの中にしか連絡先が保存されておらず、葬儀や訃報を知らせることができないケースがあります。
特におひとりさまや独居高齢者で起こりやすい問題です。
遺影に使える写真が見つからない
プリントされた写真がなく、デジタルデータにアクセスできないため、遺影写真の選定が困難になることがあります。
適切な写真が見つからず、やむを得ず過去の集合写真を使う例もあります。
スマホやPCにアクセスできない
端末がロックされたままになり、写真や連絡先、重要なファイルにアクセスできないケースは非常に多く見られます。
特にiPhoneやMacはセキュリティが厳しく、本人以外が解除するのはほぼ不可能。家族の写真やメモ、仕事上のデータが取り出せず困る例が増えています。
ネット銀行・証券口座がわからない
紙の通帳が存在しないネット銀行では、ログイン情報がなければ残高も相続財産も把握できません。
証券口座やFX口座の情報がわからず、相続税申告にも影響が出ることがあります。
クレジットカード・サブスクが自動引き落としされ続ける
契約者が死亡しても、放置されたサブスクリプション(動画配信、音楽、クラウドサービスなど)が毎月引き落とされてしまうトラブルも。
カードの停止が遅れると、数ヶ月~数年単位で無駄な支払いが発生します。
トラブルを防ぐために今できることはエンディングノートを作ることから!
デジタル遺品のトラブルは、事前の備えによって大きく減らすことができます。
エンディングノートは、デジタル遺品に関する情報を一元管理できる便利なツールです。
以下のような項目を整理しておくことで、家族が困らず、あなたの意志もきちんと伝わります。
スマホやPCのロック解除方法を記録しておく
端末にロックがかかっていてアクセスできない事態を防ぐには、パスコードや解除方法を紙やエンディングノートに記録しておくことが大切です。
金融・暗号資産・サブスクのアカウントをリスト化する
ネット銀行や証券、仮想通貨、サブスクなどの契約内容を把握できるよう、アカウント名・ID・利用目的を一覧にしておきましょう。
思いついたことから少しずつ記入していくだけでも、将来の備えとして十分に役立ちます。
思いついた項目から少しずつでも書き出しておくことで、家族にとっての大きな支えになります。
メール・連絡先を共有し、緊急連絡先リストを作っておく
大切な人への連絡ができないことで、葬儀や手続きに支障をきたす場合があります。
スマホやクラウドの中にしか連絡先がないと、いざという時に対応できません。
スマホにしか入っていない知人の連絡先にアクセスできない問題を防ぐために、親しい人の連絡先を紙でも控えておき、葬儀連絡などに備えましょう。
遺影に使える写真を選んでおく
遺影用の写真がスマホやSNSにしかない場合、アクセスできなければ困ることになります。
あらかじめ選定し、共有しておくことでスムーズな準備につながります。
遺影に使える写真がデジタルだけになっている人は、あらかじめお気に入りの1枚を家族と共有したり、プリントして保管しておくと安心です。
SNSやメールアカウントの取り扱いを明記する
アカウントが放置されると、周囲の混乱や心の負担になることがあります。
希望の処理方法を残しておくことで、家族が迷わずに対応できます。
「削除してほしい」「残しておいてほしい」といった希望がある場合は、エンディングノートなどに自分の意思を記しておきましょう。
パスワードの管理方法を見直す
トラブルを防ぐ第一歩は、家族が最低限の情報を把握できるようにすることです。
- パスワード管理アプリを使う(例:1Password、bitwarden など)
- 紙のノートにメモして保管(保管場所を家族に共有)
- 家族信頼者に定期的に見せる・共有する仕組みを持つ
パスワードの「見える化」で、いざという時の混乱を防げます。
アカウントの一覧を作成しておく
金融機関やサブスク、SNS、クラウドサービスなど、どんなアカウントを使っているかをリスト化しておくことが重要です。
- 利用サービス名
- ログインID(メールアドレス)
- 契約名義(個人/法人など)
一覧を作るだけでも、家族の負担は大きく減ります。
トラブルが起きてしまったときの対処法

どれだけ備えていても、予期せぬタイミングでトラブルが発生することはあります。
大切なのは、慌てず適切な手段をとること。
ここでは、実際にトラブルが起きてしまったときの対応方法をご紹介します。
AppleやGoogleなどの公式サポートを利用する
たとえば、Appleでは「故人アカウント管理連絡先」という制度を使えば、あらかじめ登録された相手がデータにアクセスできます。
- Appleサポートページ:Apple Accountの故人アカウント管理連絡先を追加する方法
Googleも「アカウント無効化管理ツール」を使うことで、指定の連絡先に情報を渡すことが可能です。
- Googleサポートページ:アカウント無効化管理ツール
専門業者や弁護士に相談する
スマホやPCの解除、アカウントの相続などが難航する場合は、専門の業者や法律家の力を借りましょう。
- デジタル遺品整理業者(データ復旧・ロック解除)
- 相続専門の弁護士・司法書士
相談先を見つけておくことが、最初の安心につながります。
今すぐチェック!デジタル遺品トラブルの備えチェックリスト
以下のような点を確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
- ✅ パスワード管理方法を家族と共有しているか
- ✅ 金融・SNS・サブスクなどのアカウントをリスト化しているか
- ✅ スマホやPCのロック解除手順を明記しているか
- ✅ エンディングノートにデジタル情報を記入しているか
- ✅ 万が一の相談先を把握しているか
このような備えを日頃から進めておくことで、いざというときの混乱やトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
まとめ|備えておけば、デジタル遺品は怖くない
デジタル遺品は、私たちの暮らしがデジタル化した現代ならではの課題です。ですが、事前の準備と情報共有で、多くのトラブルは防ぐことができます。
まずはエンディングノートやアカウントのリスト作成から始めてみましょう。身近な人の安心のために、今すぐ一歩を踏み出してみませんか?