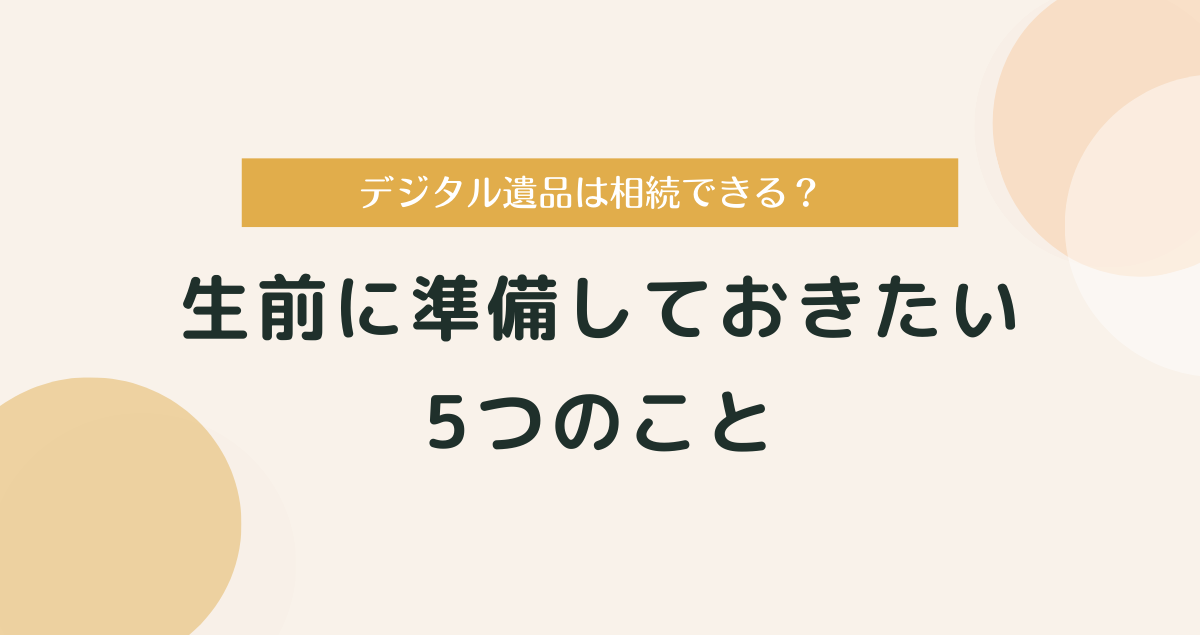スマホやパソコンには、写真、連絡先、ネット銀行、サブスク契約など、見えない財産=デジタル遺品が数多く存在します。
こうした情報は相続の対象になることもあり、放置するとトラブルの原因になる可能性もあります。
この記事では、デジタル遺品は相続できるのか?という基本から、相続時の注意点、生前整理で準備しておくべきポイントまでをわかりやすく解説します。
大切なデジタル資産を守るために、今できる対策を始めましょう。
デジタル遺品とは?──相続対象になる「見えない財産」

写真やSNSだけじゃない、見落とされがちなデジタル資産
近年は、スマートフォンやパソコン内に保存される情報が増加し、「デジタル遺品」としての存在感が高まっています。
具体的には以下のようなものが該当します。
- オンライン銀行・証券口座の残高
- 仮想通貨(ビットコインなど)
- SNSアカウントやクラウド保存された写真・動画
- サブスクリプション契約(Netflix、Amazon Primeなど)
- ポイントサービス(楽天ポイント、Tポイントなど)
- ネットショッピングの購入履歴や支払い情報
これらは「デジタルな形の財産」として、相続対象になる場合があります。
デジタル遺品は相続できる?法的な扱いと注意点

相続できるもの・できないものの違いとは
デジタル遺品は、すべてが相続の対象になるわけではありません。以下のように分けて考えると整理しやすくなります。
相続対象となるもの
- ネット銀行・証券口座の預金・資産
- 仮想通貨などの金銭的価値を持つもの
- 有料で保有しているコンテンツ(電子書籍など)
相続できないもの(一身専属のもの)
- 個人に帰属するSNSアカウント(例:Facebook、Xなど)
- 使用契約に「譲渡・相続不可」とあるクラウドサービスなど
財産的価値があるものは民法896条の「相続財産」に該当します。
SNSなどの個人アカウントは、利用規約により一身専属権として扱われることが多いです。
利用規約によってはアクセスが制限されることも
たとえば、Apple IDやLINEのように、契約者本人以外のアクセスを禁じる規約があるサービスも多く、相続人であってもログインできないことがあります。
その場合、事前の「管理連絡先」設定や「デジタル遺産管理者」の指定が必要です。
相続時によくあるトラブルとその原因

「存在を知らない」ことが最大のリスク
家族がその存在を知らないまま放置されることで、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
- ネット銀行や仮想通貨の口座が凍結されたまま相続されない
- 自動引き落としが続き、解約できずに金銭的損失が生じる
- 家族が故人のSNSアカウント削除や整理を行えない
- 故人の名義で登録されたサービスの不正利用につながる危険性も
「見えない資産」は、存在自体が認識されないことが最大のリスクです。
生前に準備しておきたい5つのこと

なぜ事前準備が必要なのか
デジタル遺品は物のように形が見えないため、生前の「見える化」と「共有」が重要です。
以下の5つの準備ができているかを確認してみましょう。
(1)保有しているデジタル資産をリスト化する
まずは、自分が使っているデジタルサービスを洗い出してみましょう。
- ネットバンク・証券口座名
- 契約しているサブスクリプション
- SNSアカウントの種類とID
- 利用しているクラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)
(2)ログイン情報(ID・パスワード)を安全に管理
相続人がアクセスできるよう、ログイン情報の整理は必須です。パスワード管理アプリの利用も有効です。
- 代表的なツール:1Password、Google パスワードマネージャーなど
- 紙のメモに残す場合は保管場所を明記し、誰に知らせるかを決めておきましょう
デジタルツールに不慣れな場合は、紙のノートにパスワードを記録し、封筒に入れて信頼できる家族に「万が一の時だけ開けてください」と伝えておくのも一つの方法です。
(3)重要なデジタル資産を優先的に記録
全てを記録するのが難しい場合は、以下のような金銭的・感情的に価値のあるものを優先しましょう。
- ネット銀行口座
- 写真や動画(思い出)
- 年間契約のあるサービス(解約漏れを防ぐ)
(4)家族や信頼できる人に引き継ぎ方針を伝える
いくら情報を整理しても、誰にも伝わらなければ意味がありません。
以下のような形で伝えておくと安心です。
- エンディングノートに記入し、保管場所を伝える
- デジタル遺品について会話の中で共有する
- 信頼できる人にアクセスのタイミング(死後○日など)を決めて託す
(5)エンディングノートや専用アプリを活用
紙でもデジタルでも構いませんが、なるべく一元化して記録することが大切です。
複数の場所に情報が分散していると、遺された家族が見落としたり、手続きに時間がかかったりする原因になります。
必要なときにすぐに確認できる状態を心がけることは、トラブルを防ぐうえでも非常に効果的です。
デジタル資産について以下の項目をチェックしてみましょう
このように準備状況を可視化することで、今すぐ取りかかるべきことが明確になり、家族が慌てずに対応できます。
- 自分のデジタル資産をリスト化しているか
- ログイン情報の保管方法を決めているか
- 優先順位をつけて記録しているか
- 家族や信頼できる人に伝えているか
- エンディングノートなどにまとめているか
- 定期的に情報を更新しているか
今すぐ使える!デジタル遺品整理ガイドを無料配布中
この記事で紹介した内容は、PDF形式のガイドとしてまとめた「デジタル遺品整理ガイド(記入式)」として無料でダウンロードできます。
- アカウント情報・パスワード・契約中サービスなどを簡単に記入可能
- 紙で管理したい方にも最適なレイアウト
- デジタルで管理したい人におすすめの終活アプリも解説
- 自分用にも、家族への引き継ぎ用にも活用できます
今すぐダウンロードして、“デジタルの見えない情報”を簡単に整理してみませんか?