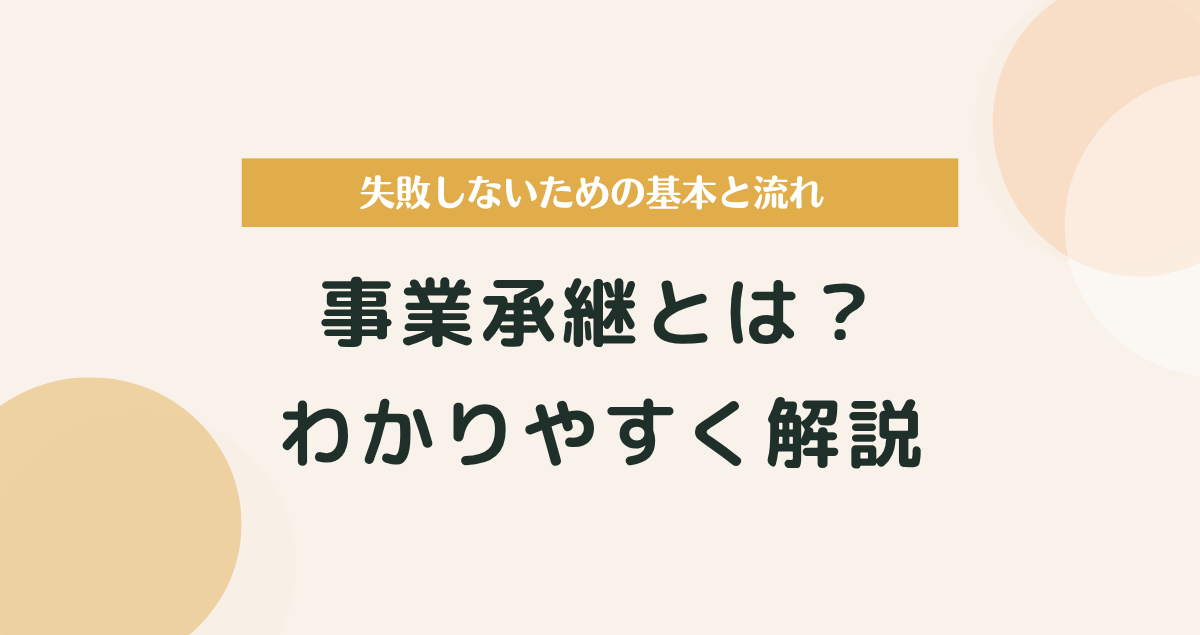「そろそろ引退を考えているが、誰に会社を任せればいいのか」「親から会社を継いでほしいと言われたが、自信がない」——事業承継は、経営者にとっても後継者にとっても、人生の大きな転機です。
この記事では、後継者の選び方で悩んでいる経営者の方、事業承継の税金対策や支援制度を知りたい方などに向けて、事業承継の基本から具体的な進め方まで、わかりやすく解説します。
目次
事業承継とは?意味と目的をやさしく解説

事業承継とは、会社の経営権(株式や代表権など)や資産を次世代に引き継ぐことを指します。単に「会社を譲る」だけでなく、次のような無形の資産も含まれます。
- 経営理念・企業文化
- 取引先との信頼関係
- 従業員の雇用と技術・ノウハウ
- ブランドや顧客基盤
日本では中小企業経営者の高齢化が進み、2025年までに70歳を超える経営者は約245万人、うち約半数の127万社(日本企業全体の約3分の1)が後継者未定という状況です。現状を放置すると、2025年までの累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があるとされています。
事業承継の3つの方法|親族内・社内・M&Aの違い
事業承継には、大きく分けて「親族内承継」「社内承継」「M&A(第三者承継)」の3つの方法があります。
それぞれに特徴・メリット・注意点があり、自社の状況によって最適な方法は異なります。
| 承継方法 | 概要 | 主なメリット | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 親族内承継 | 子どもや親族が経営を引き継ぐ方法。 | ・早期から後継者育成を進めやすい ・経営理念や企業文化を継承しやすい ・従業員や取引先に安心感を与えやすい |
・相続税・贈与税への対策が必要 ・兄弟姉妹など他の相続人との調整が必要 ・必ずしも経営能力があるとは限らない |
| 社内承継 | 役員や幹部、従業員が後継者となる方法。 | ・事業内容を理解しており承継がスムーズ ・経営の一貫性を保ちやすい ・従業員の士気向上につながる |
・株式取得や資金調達が課題となる ・個人保証・担保の引継ぎに注意が必要 ・他の社員との関係調整が必要 |
| M&A(第三者承継) | 外部の企業や個人に経営を引き継ぐ方法。 | ・後継者不在の問題を解決できる ・会社の存続と雇用維持が可能 ・創業者が譲渡益(売却益)を得られる |
・買い手との企業文化の違いによる摩擦 ・経営方針が変わる可能性 ・譲渡条件の交渉に時間がかかる |
どの方法を選ぶべきか?
どの方法が最適かは、後継者候補の有無・経営者の年齢や意向・会社の財務状況によって異なります。
いずれの方法も、早めに方針を定め、後継者の育成や税制対策を進めることが成功の鍵です。
事業承継は5〜10年計画で進める
事業承継には平均5〜10年の準備期間が必要です。時間をかけて後継者を育て、資産や株式の整理を進めることで、次のようなトラブルを防ぐことができます。
よくある失敗例:
- 急な承継で後継者が経営判断できず、取引先の信頼を失った
- 親族間で株式が分散し、経営方針が決められなくなった
- 税制要件を知らずに承継し、多額の相続税が発生した
- 従業員への説明が不十分で、優秀な人材が離職した
【5年計画】事業承継を成功させる4ステップ

事業承継は一度に進めるのではなく、段階的に計画・実行することが成功のポイントです。ここでは4つのステップに分けて解説します。
ステップ1:現状把握と課題整理(開始〜1年目)
まず、自社の経営資源を棚卸しします。
チェック項目:
- □ 経営者の年齢と引退希望時期
- □ 後継者候補の有無(親族・社内・外部)
- □ 会社の財務状況(資産・負債・利益)
- □ 株式の保有状況と評価額
- □ 主要取引先との関係性
- □ 従業員の構成と技術レベル
- □ 事業用不動産や設備の状況
これらを一覧化し、どの部分を引き継ぐべきか、課題は何かを明確にします。
ステップ2:後継者の選定と育成(1〜5年目)
経営理念を共有しながら、業務・財務・人事の引き継ぎを段階的に行います。
育成のポイント:
- 現場業務から始め、段階的に管理職へ
- 経営会議への参加で意思決定を学ばせる
- 外部研修や他社での修行も検討
- 取引先や金融機関への同行で関係構築
- 少なくとも3〜5年の育成期間を確保
失敗例: いきなり社長交代を発表し、後継者が現場の信頼を得られなかった
ステップ3:承継スキーム(具体的な方法)の設計(3〜7年目)
株式や事業用資産をどのように移転するか、税負担を最小化する方法を決めます。
検討事項:
- 株式の譲渡方法(贈与・相続・売買)
- 事業承継税制の活用
- 遺留分への配慮(他の相続人との調整)
- 金融機関の個人保証の切替
- 退職金や役員報酬の調整
この段階では、税理士・弁護士・金融機関などの専門家のサポートが不可欠です。
ステップ4:実行とフォローアップ(5〜10年目)
計画を実施し、関係者(社員・取引先・金融機関)へ丁寧に周知します。
実行時のポイント:
- 従業員説明会で不安を解消
- 取引先への挨拶と信頼関係の維持
- 前経営者は一定期間、顧問として残る
- 承継後も定期的に状況を確認
- 問題が生じたら迅速に軌道修正
承継は「完了」ではなく「新たなスタート」です。後継者をサポートする体制を整えましょう。
事業承継税制の基礎知識
事業承継税制とは、中小企業が後継者へ株式を贈与・相続する際に、相続税や贈与税を猶予・免除できる制度です。
通常、株式を引き継ぐと多額の税金が発生しますが、この制度を使えば最大100%の税負担が猶予され、要件を満たし続ければ最終的に免除されます。
中小企業庁が定める一定の要件を満たす必要があります。
参考:事業承継税制特集
主な要件とポイント
| 区分 | 要件の概要 | 留意点 |
|---|---|---|
| 対象企業 | 中小企業基本法の定義を満たす法人 | 大企業や上場企業は対象外 |
| 後継者 | 代表取締役への就任が必要 | 親族でなくても可 |
| 継続要件 | 5年間の雇用維持・経営継続 | 従業員数を平均8割以上維持 |
| 事前計画 | 特例承継計画の提出(2027年まで) | 認定支援機関の支援が必要 |
| 株式保有 | 総議決権の50%超を保有 | 筆頭株主である必要あり |
注意すべき「猶予取消リスク」
次のような場合、猶予が取り消され、税金+利子を一括納付しなければなりません。
- 代表取締役を辞任した
- 5年以内に従業員が2割以上減少した
- 会社を売却・解散した
- 株式を譲渡・贈与した
実際の失敗例: 業績悪化で人員削減したところ、雇用維持要件を満たせず猶予が取り消された
税制を活用することで、数千万円〜数億円の税負担を軽減できるケースもあります。ただし、計画的な準備と税理士・認定支援機関の支援が欠かせません。
事業承継を支援する公的制度・相談先
制度や専門家をうまく活用することで、承継のリスクを減らし、スムーズに進めることができます。ここでは代表的な公的支援策を紹介します。
事業承継・引継ぎ支援センター
各都道府県に設置されている公的機関で、無料相談が可能です。
支援内容:
- 事業承継の基礎知識の提供
- 承継計画の策定支援
- M&Aマッチング支援
- 専門家(税理士・弁護士)の紹介
詳細は中小企業庁の「事業承継・引継ぎ支援センター」をご参照ください。
事業承継補助金
後継者が新たな取組み(事業転換・設備投資など)を行う場合に支援される制度です。
対象となる経費例:
- 新商品・サービスの開発費用
- 設備投資・店舗改装費
- 広告宣伝・販路開拓費
- 専門家への支払報酬
補助率は通常2/3程度、上限額は数百万円〜と規模により異なります。最新情報は「中小企業庁 事業承継補助金ページ」を確認しましょう。
その他の支援策
- 日本政策金融公庫の低利融資:事業承継に必要な資金調達
- 経営承継円滑化法:遺留分に関する民法特例、金融支援
- 認定支援機関:税理士・公認会計士・商工会議所などの専門家
よくある質問(FAQ)
最後に、事業承継に関してよくある疑問に答えます。実際に検討を始めた際に気になるポイントをまとめました。
Q1. 事業承継はいつから始めればいい?
A. 理想は5〜10年前から準備を始めることです。後継者育成や資産整理には時間がかかります。具体的には、60歳になったら本格的に計画を始め、65〜70歳で承継完了を目指すのが一般的です。
Q2. 親族が継ぎたがらない場合は?
A. 社内承継やM&Aなど、第三者承継の選択肢を検討しましょう。実際、M&A件数は年々増加しており、事業承継型M&Aも着実に増加傾向にあります。「会社は子どもが継ぐもの」という固定観念にとらわれず、早めに事業承継・引継ぎ支援センターなどの専門家へ相談することで解決策が見えてきます。親族外承継の比率は年々増加しています。
Q3. 個人事業主も対象になる?
A. はい。個人事業の承継(事業譲渡・廃業)にも税制支援があります。事業用資産(設備・在庫・顧客リスト)や屋号なども含めて引き継ぎが可能です。個人版事業承継税制も整備されつつあります。
Q4. 株式の評価額はどう決まる?
A. 非上場株式の評価は複雑で、主に次の方法があります。
- 類似業種比準方式:同業他社との比較
- 純資産価額方式:会社の資産から負債を引いた額
- 配当還元方式:配当実績に基づく評価
評価額が高いと税負担も大きくなるため、税理士による事前評価と対策が必要です。
Q5. 兄弟間で後継者を決められない時は?
A. 第三者(専門家や顧問)を交えた話し合いが有効です。また、議決権を持つ株式は後継者に集中させ、他の兄弟には配当のみの株式や金銭で調整する方法もあります。感情的にならず、会社の未来を最優先に考えることが大切です。
Q6. M&Aで会社を売った後も経営に関われる?
A. 可能です。MBO(マネジメント・バイアウト)やアーンアウトという仕組みを使えば、一定期間は前オーナーが顧問や取締役として関与できます。買い手企業も、急激な変化を避けるため、一定期間の協力を求めることが多いです。
Q7. 従業員に継がせたいが資金がない場合は?
A. 次のような支援策があります。
- 持株会社スキーム:段階的に株式を移転
- MBO支援ファンド:金融機関が資金提供
- 日本政策金融公庫の融資:低利で資金調達
- 従業員持株会:複数名で株式を保有
専門家と相談しながら、無理のない資金計画を立てましょう。
まとめ:事業承継は「会社の未来をつなぐ終活」
事業承継とは、会社の命を次の世代へつなぐ大切なプロセスです。単なる相続ではなく、理念や人材を含めた「経営のバトンリレー」。早めの準備と計画的な進行が、会社を守り、家族・従業員・地域を支える結果につながります。
今日からできる第一歩
- □ 自社の経営資源を書き出してみる
- □ 後継者候補を3名リストアップする
- □ 最寄りの事業承継・引継ぎ支援センターを調べる
- □ 顧問税理士に事業承継税制について相談する
- □ 家族や幹部社員と将来について話し合う
「まだ早い」と思っているうちに、あっという間に時間は過ぎます。今のうちから、自社に合った承継方法を考えてみましょう。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。