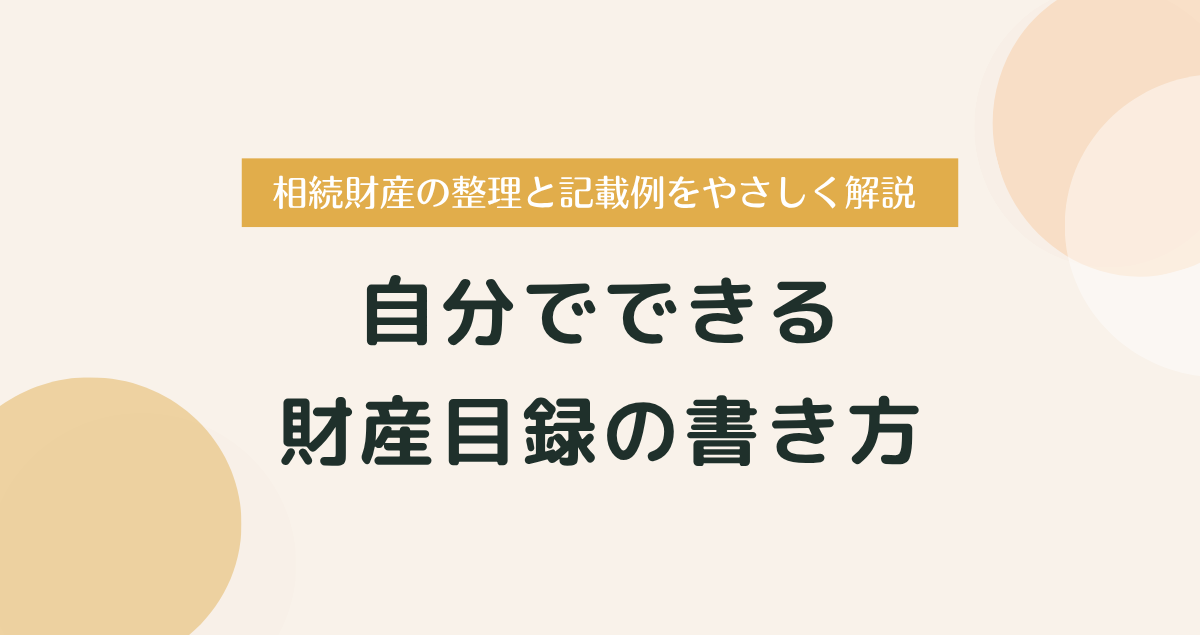相続の準備や手続きにおいて、「財産目録」は欠かせない書類のひとつです。
とはいえ、初めての方にとっては、
- どんな財産まで書けばいいの?
- 評価額はどうやって決めるの?
- エンディングノートの財産リストと何が違うの?
など、戸惑うポイントも多いはずです。
この記事では、財産目録の基本的な役割から、記載すべき財産の種類、評価額の考え方、自分で作成する手順まで、順を追ってやさしく解説します。
手間をかけずに、かつ後々の相続トラブルを防ぐためのポイントもあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
財産目録とは?必要な場面と作るメリット

財産目録とは「相続財産の一覧表」
財産目録とは、被相続人(亡くなった方)が持っていたすべての財産を一覧にしたものです。
預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も含めて記載します。
単に「土地」「預金」と書くだけでなく、次のような情報を整理するのが基本です。
- 財産の種類(不動産、預貯金、株式、保険、借入金など)
- 内容(所在地、金融機関名、銘柄名など)
- 名義人
- 評価額(いくら相当か)
- 所在(どこにあるか/どこの口座か)
- 特記事項(共有持分、名義預金、賃貸中かどうか など)
財産目録が使われる主な場面
財産目録は、相続のさまざまな場面で土台となる資料です。
- 遺産分割協議(相続人同士で財産をどう分けるか話し合うとき)
- 遺言書の作成・添付資料(とくに自筆証書遺言)
- 相続税申告(相続財産の合計額を把握するとき)
- 名義変更手続き(不動産・預貯金・証券・保険など)
このように、財産目録は相続手続き全体の「基本台帳」のような役割を果たします。
作成するメリット|トラブル防止と手続きの効率化
財産目録の作成は法律上の義務ではありませんが、作っておくと次のようなメリットがあります。
- 財産の全体像が一目でわかる(「何がどこにどれくらいあるか」が整理される)
- 相続人間の不信感や「隠し財産」疑惑を防げる
- 遺産分割協議をスムーズに進められる
- 相続税申告書作成の手間を大幅に減らせる
財産目録がなければ、「そもそも何が遺産なのか」から調べることになり、時間も手間もかかります。
逆に、財産目録がきちんと整っていれば、相続人にとっても親切な「道しるべ」になります。
財産目録に記載する財産と基本項目

対象となる財産の種類(プラスとマイナスの両方)
財産目録には、次のようなプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を漏れなく記載します。
- 預貯金(銀行名・支店名・口座番号・残高)
- 不動産(所在地・地番・家屋番号・登記内容・持分)
- 株式・投資信託などの有価証券(銘柄・証券会社名・数量・評価額)
- 生命保険金・死亡退職金など(受取人・見込額など)
- 現金(自宅金庫やタンス預金の有無・金額)
- 自動車などの動産(車種・登録番号・概算価格)
- 借入金・住宅ローン・カードローン(借入先・残高・返済条件)
- 未払金・連帯保証債務などの負債
プラスの財産だけでなく、負債を含めて記録することで「正味の遺産額」が分かるようになります。
押さえておきたい基本項目
財産目録を一覧表にする際は、次のような項目を設けておくと整理しやすくなります。
- 種類(不動産/預貯金/株式/保険/借入金など)
- 内容・名称(金融機関名・銘柄名・契約名など)
- 名義人
- 数量・評価額
- 所在(支店名・口座番号・所在地など)
- 特記事項(共有持分・名義預金・賃貸中など)
とくに重要なのが、名義・評価額・所在・特記事項の4点です。あとから第三者(相続人や専門家)が見たときに、「どの財産かを特定できる情報」を入れておきましょう。
評価額の考え方と注意点
原則は「相続開始時点の評価額」
相続税の計算や相続人間の公平な分配を考えるとき、評価額は「相続開始時点(死亡時)」を基準にするのが原則です。
生前に財産目録を作成する場合は、作成時点の概算額を記載しつつ、「評価時点」を備考欄などに明記しておきましょう。
例)「2025年4月1日時点の残高」「2025年課税明細より」など
相続税評価額と実勢価格の違いに注意
不動産などの資産は、
- 相続税などで用いる「相続税評価額(路線価・固定資産税評価額など)」
- 実際に売買するときの「実勢価格(取引価格)」
の2種類の「価値」が存在します。
都市部の不動産では、実勢価格が相続税評価額より高くなることもあれば、地方の不動産では逆に「売りにくいのに評価額は高い」というケースもあります。
そのため、相続税評価額だけを基準に遺産分割を行うと、あとから「実は不公平だった」という不満が出ることもあります。
財産目録には、
- 相続税評価額(固定資産税評価額・路線価など)
- 参考としての市場価格の目安(不動産会社の査定など)
を分けてメモしておくと、後々の話し合いがスムーズになります。
自分でできる財産目録の作り方ステップ

STEP1 財産を洗い出す
まずは、次のような資料を揃えながら、漏れのないように財産を洗い出します。
- 通帳・ネットバンキングの明細
- 登記事項証明書・固定資産税の納税通知書
- 証券会社の取引報告書・残高報告書
- 保険証券・契約内容のお知らせ
- 借入契約書・ローン返済予定表・カード明細
「昔作ったままの口座」「ネット専用銀行」など、本人も忘れている財産が見つかることもあります。
心配な場合は、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターなど)に照会して、借入の有無を確認する方法もあります。
STEP2 一覧表に整理する
洗い出した財産を、表形式で一覧化します。ExcelやGoogleスプレッドシートを使うと、後から金額を修正しやすく便利です。
例として、次のような列を用意します。
- 種類
- 内容・名称
- 名義人
- 数量・評価額
- 所在(支店名/口座番号/所在地など)
- 特記事項(共有持分・賃貸中・名義預金など)
財産の種類が少なく、家・預貯金・車程度であれば、簡易的な表でも十分です。
一方、不動産や有価証券が多い場合や借入が複数ある場合には、詳細な書式にしておくほうが、後からの手続きがスムーズになります。
STEP3 名義・評価額・特記事項を確認する
一覧表にまとめたら、名義や評価額、特別な事情の有無を確認します。
- 不動産:登記事項証明書で名義人・持分・地番・家屋番号を確認
- 預貯金:金融機関・支店・口座番号・残高を確認(ネット銀行も忘れずに)
- 株式・投資信託:銘柄名・数量・評価額(評価日も備考欄に)
- 負債:借入先・残高・返済条件・完済予定日など
また、次のような点は特記事項としてメモしておくと安心です。
- 共有名義の不動産(持分割合・他の共有者の氏名)
- 賃貸中の物件(家賃・入居者の有無)
- 名義預金と思われる口座(名義は子や孫だが、実質は本人が管理している場合など)
- 保証人になっている借入の有無
STEP4 証憑をそろえ、最終チェックを行う
最後に、財産目録の内容を裏付ける証憑(エビデンス)をそろえます。
- 通帳のコピー・ネット明細の印刷
- 登記事項証明書・固定資産税納税通知書
- 証券会社の残高報告書
- 保険証券のコピー
- 借入契約書・返済予定表
証憑を見ながら、漏れ・重複・記載ミスがないかをチェックしましょう。
生前に作った財産目録は「定期的な見直し」が大切
生前に財産目録を作成した場合でも、一度作って終わりではありません。
- 定期預金の解約
- 不動産の売却・名義変更
- 新たな借入や完済
- 保険の解約・新規契約
など、財産の内容は年月とともに変化していきます。
目安としては、1年に1回程度、または大きな財産の出入りがあったタイミングで見直しをして、更新日を記録しておくと安心です。
種類別|財産目録の書き方のポイント
不動産
不動産については、次のような点を記載します。
- 所在地(登記簿どおり)
- 地目・地番・家屋番号
- 利用状況(自宅・貸家・空き地など)
- 持分(1/2、2/3など)
- 評価額(固定資産税評価額・路線価など)
- 特記事項(共有者の氏名・賃貸中かどうか など)
預貯金・現金
- 金融機関名・支店名
- 口座種別(普通・定期など)
- 口座番号
- 残高(評価日もあわせて記載)
- ネット銀行の有無
- 現金の保管場所と概算額
株式・投資信託などの有価証券
- 銘柄名・種別(上場株・投資信託など)
- 証券会社名・支店名
- 数量
- 評価額(評価基準日をメモしておく)
負債(借入金・ローンなど)
- 借入先(金融機関名・個人名など)
- 借入総額・債務残高
- 返済方法(毎月○円・ボーナス時○円など)
- 完済予定日
- 保証人の有無
これらを記録しておくことで、相続放棄を検討すべきかどうかの判断材料にもなります。
名義預金・共有財産など、トラブルになりやすいポイント
名義預金に注意
名義預金とは、口座名義は子や孫になっていても、実際には親や祖父母が管理している預金のことです。
通帳や届出印を管理しているのが被相続人であれば、その預金は「名義人の財産」ではなく「被相続人の財産」と判断され、相続税の対象になる可能性があります。
被相続人以外の名義口座でも、実質的に誰の財産なのかを意識して、財産目録に記載・整理しておくことが大切です。
共有財産や賃貸中の不動産
共有名義の不動産については、
- 共有者全員の氏名
- 各人の持分(1/2、1/3など)
を明記しておきましょう。
また、賃貸中の物件は、
- 入居者の有無
- 月額賃料
- 管理会社の有無
なども備考欄に書いておくと、相続人が把握しやすくなります。
自筆証書遺言に添付する財産目録の注意点
財産目録は、自筆証書遺言に添付する書類として使われることも多くあります。この場合には、民法上のルールに注意が必要です。
- 財産目録は手書きでなくてもOK(パソコン作成、通帳や登記事項証明書のコピー添付も可能)
- ただし、自書でない場合は各ページに署名・押印が必要
- 財産目録は遺言本文とは別紙として作成する(同じ用紙に混在させない)
- ページをまたぐ場合、契印は必須ではないが、一体性を確保するためには押しておくと安心
- 訂正する場合は、遺言の本文と同様に訂正箇所を明示し、署名・押印が必要
自分で作る?専門家に頼む?判断の目安

自分で作成してもよいケース
次のような場合は、ご自身で財産目録を作成しても問題ないことが多いでしょう。
- 財産の種類が少なく、内容もシンプル(自宅と預貯金が中心)
- 相続人の数が少なく、関係も良好
- 相続税がかかるほどの財産規模ではない
専門家に相談したほうが安心なケース
一方、次のような場合は、税理士・弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 複数の不動産や賃貸物件がある
- 株式投資・投資信託・会社持分など、評価が難しい財産が多い
- あちこちに預貯金口座があり、全体像がつかみにくい
- 相続税がかかる可能性が高い
- 相続人同士でもめそうな事情がある
相続の争いや余計な税負担を避けるためにも、不安がある部分だけ専門家にピンポイントで相談する方法も有効です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 財産目録は必ず作成しなければなりませんか?
A. 法律上の義務ではありませんが、遺産分割協議や相続税申告でほぼ必須の資料になります。後々の手間やトラブルを減らすためにも、作成しておくことをおすすめします。
Q2. 財産目録は手書きでも構いませんか?
A. はい、手書きでも問題ありません。ただし、書き直しや加筆が多くなりやすいため、ExcelやWordなどで作成しておくと、修正・保存・共有がしやすくなります。
Q3. 評価額は最新のものにする必要がありますか?
A. 相続税や遺産分割の基準となるのは、相続開始時点(死亡時)の評価額です。生前に作る財産目録では「作成時点の概算額」を書き、評価日をメモしておきましょう。相続税が絡む場合は、税理士など専門家の助言を受けると安心です。
Q4. 負債も財産目録に記載する必要がありますか?
A. はい。借入金やローン、未払金などのマイナスの財産も含めて記録することで、正味の遺産額が把握できます。相続放棄や限定承認を検討する際の重要な判断材料にもなります。
Q5. エンディングノートの財産一覧と財産目録は同じものですか?
A. エンディングノートの財産一覧は「備忘録」としては有用ですが、それだけでは正式な相続手続きには不十分なことがあります。相続手続きに使うことを前提に、名義・評価額・所在・特記事項まで整理したものが財産目録とイメージしてください。
Q6. 遺言に添付する財産目録には署名・押印が必要ですか?
A. パソコンで作成した財産目録や通帳・登記事項証明書の写しを自筆証書遺言に添付する場合は、各ページに署名・押印が必要です。
参考:法務省公式サイト
Q7. 財産目録はどのくらいの頻度で見直せばよいですか?
A. 明確な決まりはありませんが、1年に1回程度を目安に、または大きな財産の出入りがあったタイミングで見直すと安心です。見直した日付を記録しておくと、相続人も状況を把握しやすくなります。
まとめ|財産目録は「家族へのわかりやすい引き継ぎメモ」
財産目録は、相続手続きを円滑に進めるための基本資料であり、相続人への大切な「引き継ぎメモ」です。
- プラスの財産だけでなく、負債も含めて整理する
- 名義・評価額・所在・特記事項をセットで記録する
- 生前に作る場合は、定期的に見直しを行う
- 不動産や名義預金など、判断が難しい部分は専門家に相談する
財産目録をきちんと備えておくことは、残される家族の負担を軽くし、相続トラブルを防ぐことにもつながります。
無理のない範囲で、少しずつでも整理を始めてみてください。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。