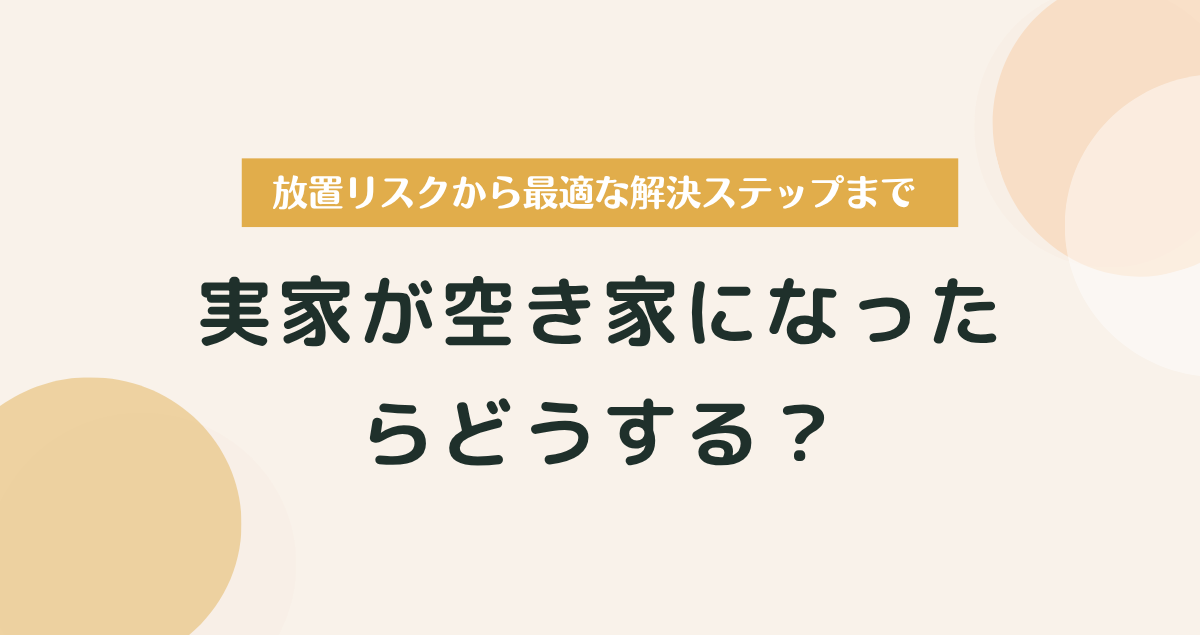親の介護や相続をきっかけに「実家が空き家になった」と悩む人が増えています。
「遠方で管理ができない」「思い出があって手放せない」など、感情と現実の狭間で迷うのは当然です。
しかし、放置は税金・修繕・防犯の負担を大きくする原因になります。
この記事では、最新の統計データをもとに空き家問題の現状を解説しつつ、「実家が空き家になったとき、どう判断し、どう動くべきか」を5つのステップで紹介します。
目次
実家が空き家になる人が急増している理由

背景には人口減少・高齢化・相続未整理といった社会的要因があります。
まずは全体像を数字で把握し、「自分ごと化」して判断材料を揃えましょう。
全国で900万2千戸、空き家率13.8%(いずれも過去最多・過去最高)
総務省の調査によると、全国の空き家は900万2千戸、空き家率は13.8%に達しました。
さらに、賃貸・売却用や二次的住宅を除く空き家は385万6千戸で、2018年比36万9千戸増と報告されています。
出典:令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計
放置するとどうなる?空き家の3つのリスク
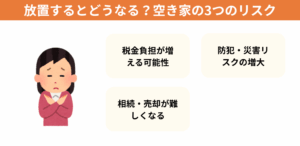
放置は「お金」「安全」「人間関係」の三方面で負担を増やします。
早期対応の必要性を理解するため、代表的なリスクを整理します。
1. 税金負担が増える可能性
老朽化や危険性が高いと判断されると「特定空家」に指定され、住宅用地の特例が外れることがあります。
結果として固定資産税が最大6倍に増えるケースもあり、経済的負担が大きくなります。
2. 防犯・災害リスクの増大
放置された住宅は不法侵入・放火・倒壊などのリスクが高まります。
近隣からの苦情や行政指導の対象になることもあります。
3. 相続・売却が難しくなる
放置期間が長いほど建物の劣化が進み、売却・賃貸の選択肢が狭まります。
また、相続登記が未了だと法的手続きが複雑化します。
実家の空き家、4つの選択肢と特徴
実家が空き家になったときに考えられる選択肢は、大きく4つあります。
それぞれのメリット・デメリット・費用感を理解しておくことが、後悔しない判断につながります。
| 対応策 | メリット | デメリット | 想定コスト |
|---|---|---|---|
| 維持・管理 | 思い出を残せる/将来利用 | 維持費・管理負担 | 年10〜30万円 |
| 賃貸・民泊活用 | 収益化できる | 修繕・法規制の対応 | 初期費用100万円〜 |
| 売却 | 現金化・管理負担ゼロ | 相続人間の調整が必要 | 仲介手数料3〜5% |
| 解体・更地化 | 危険性・税制リスクの回避 | 解体費・固定資産税増の可能性 | 約100〜200万円 |
実家が空き家になったときにやるべき5つのステップ

「何から始めればいいかわからない」という人も、このステップに沿って進めれば整理しやすくなります。
ステップ1:現状を正確に把握する
名義・老朽化・費用の3つを把握し、家の現状を「見える化」しましょう。
- 登記簿で名義確認(相続未登記に注意)
- 築年数・老朽化・耐震状況の確認(写真記録)
- 固定資産税・管理費・修繕費の試算
ステップ2:家族・相続人と方針を共有する
複数の相続人がいる場合、意見が分かれることがあります。
感情ではなくデータで話すことが、スムーズな合意形成の鍵です。
ステップ3:維持・活用・売却・解体を選ぶ
家庭ごとに最適な方法は異なります。
以下の判断チャートを参考にして方向性を整理しましょう。
【判断チャート】
Q1:今後、家族が住む予定はある? → Yes → 維持・管理へ
└ No → Q2へ
Q2:立地・設備に需要がある? → Yes → 賃貸 or 民泊活用へ
└ No → Q3へ
Q3:老朽化や維持費の負担が大きい? → Yes → 売却 or 解体へ
└ No → 維持しつつ様子見
ステップ4:手続きと費用を把握する
方向性が決まったら、次は手続きと費用を整理します。
事前にスケジュールと予算を明確にしておくと、後のトラブルを防げます。
| 項目 | 賃貸化 | 売却 | 解体 |
|---|---|---|---|
| 主な手続き | 修繕・管理契約 | 登記整理・媒介契約 | 解体許可・業者選定 |
| 期間目安 | 1〜3か月 | 2〜6か月 | 約1か月 |
| 費用目安 | 50〜200万円 | 仲介手数料3〜5% | 100〜200万円 |
ステップ5:空き家を維持・管理する具体的な方法を選ぶ
対応が終わっても管理は続きます。遠方からでも管理できる仕組みを整えましょう。
空き家を放置しないためには、定期的な管理が欠かせません。
ただし、選んだ方針によって対応方法は異なります。
ここでは維持・売却・解体の3パターン別に、実際に行うべき管理方法を解説します。
① 維持・再利用する場合:自分または家族で管理する
近距離に住んでいる場合や、将来的に再利用を考えている場合におすすめです。
通風・清掃・通水などを月1回程度行い、劣化を防ぎます。費用は少なく済みますが、時間と手間の確保が必要です。
- 頻度:月1回〜数か月に1回
- 主な内容:通風、掃除、草刈り、水道の通水など
- 費用:交通費+清掃用品など実費
② 遠方の場合:管理代行業者に依頼する
遠方に住んでいて管理が難しい場合は、空き家管理サービスを利用しましょう。
自治体と連携している管理会社も多く、定期点検や報告書送付を行ってくれます。
費用はかかりますが、安全・衛生・トラブル防止の観点からは非常に効果的です。
- 頻度:月1回〜3か月に1回(契約プランによる)
- 主な内容:外観確認、清掃、通風・通水、郵便物処理など
- 費用:月3,000〜10,000円前後が一般的
③ 売却を選ぶ場合:引き渡しまでの「仮管理」を行う
売却を決めた場合でも、契約成立までは空き家の状態を維持する必要があります。
「引き渡し時に劣化している」と査定が下がったり、契約トラブルになることも。
- 契約前:外観や室内の清掃・通風を最低限維持
- 契約後:引き渡しまで雨漏り・設備不具合がないか確認
- 費用目安:清掃・補修など数千円〜数万円
不動産会社が売却を代行する場合は、現地管理も委託できる場合があるため、相談してみましょう。
④ 解体を選ぶ場合:撤去後の土地管理を忘れずに
解体後の更地も放置すると、雑草・不法投棄・固定資産税増額のリスクがあります。
- 雑草対策:防草シートや砂利敷きを施工
- 境界明示:隣地トラブルを防ぐため杭・フェンスを確認
- 定期確認:年2回ほど現地を見回る or 管理代行を委託
将来的に売却や駐車場利用を考える場合は、土地の活用方法もセットで検討しておくのが理想です。
いずれのケースでも、「誰が・いつ・どのように」管理・対応するかを明確に決めることが大切です。
放置による倒壊・雑草・害虫などのトラブルを防ぐためにも、早めの体制づくりを心がけましょう。
行政の支援・補助金制度を活用する

改修・除却(解体)・利活用などに関して、国や自治体が支援メニューを用意しています。
最新の制度を確認し、費用負担の軽減に役立てましょう。
自治体ごとの補助制度をチェック
改修補助、除却補助、空き家バンクなどは自治体ごとに異なります。
「市区町村名+空き家+補助金」で検索し、最新情報を確認しましょう。
最新の補助金・助成金情報を調べる際には、以下の公式ポータルサイトも便利です。
- 空き家改修補助金:最大100万円以上の自治体も
- 除却(解体)補助金:老朽家屋の撤去を支援
- 空き家バンク:移住希望者とのマッチング
放置しないための3つの心得
すぐに結論が出なくても、進め方の「姿勢」を決めておけば迷いにくくなります。
以下の3つを意識するだけで、リスクを大幅に減らせます。
- 先送りしない — 劣化は待ってくれません。
- 感情よりデータで判断 — 維持費・相場・リスクを数値化する。
- 専門家を早めに頼る — 不動産・税務・行政の無料相談を活用。
よくある質問(FAQ)
Q1. 実家が空き家になったら、まず何をすればいいですか?
まずは登記簿で名義を確認し、誰が所有者かを明確にしましょう。
次に、建物の老朽化・耐震状況・税金の負担を整理して現状を把握します。
そのうえで、家族間で「維持・活用・売却・解体」の方針を話し合うのが第一歩です。
Q2. 空き家を放置するとどうなりますか?
放置すると、固定資産税が最大6倍に増える可能性があります。
また、防犯や災害リスクも高まり、倒壊・放火・近隣トラブルの原因になることも。
行政から指導を受けるケースもあるため、早めの対応が必要です。
Q3. 遠方に住んでいて管理できない場合はどうすればいいですか?
空き家管理サービスの利用がおすすめです。
月3,000〜10,000円前後で、通風・清掃・通水・郵便物処理などを代行してくれます。自治体によっては、管理費用の補助制度がある場合もあります。
Q4. 空き家の解体費用はどのくらいかかりますか?
一般的な木造住宅で100〜200万円前後が目安です。
老朽化や立地によって変動しますが、多くの自治体が解体補助金(最大100万円以上)を用意しています。
事前に「市区町村名+空き家+補助金」で検索し、最新情報を確認しましょう。
まとめ:動き出すなら「今」が最善のタイミング
実家の空き家問題は、放置するほど複雑化します。
現状把握→家族合意→方針選択→手続き→管理という流れを押さえ、数字とデータに基づいた判断で前に進みましょう。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。