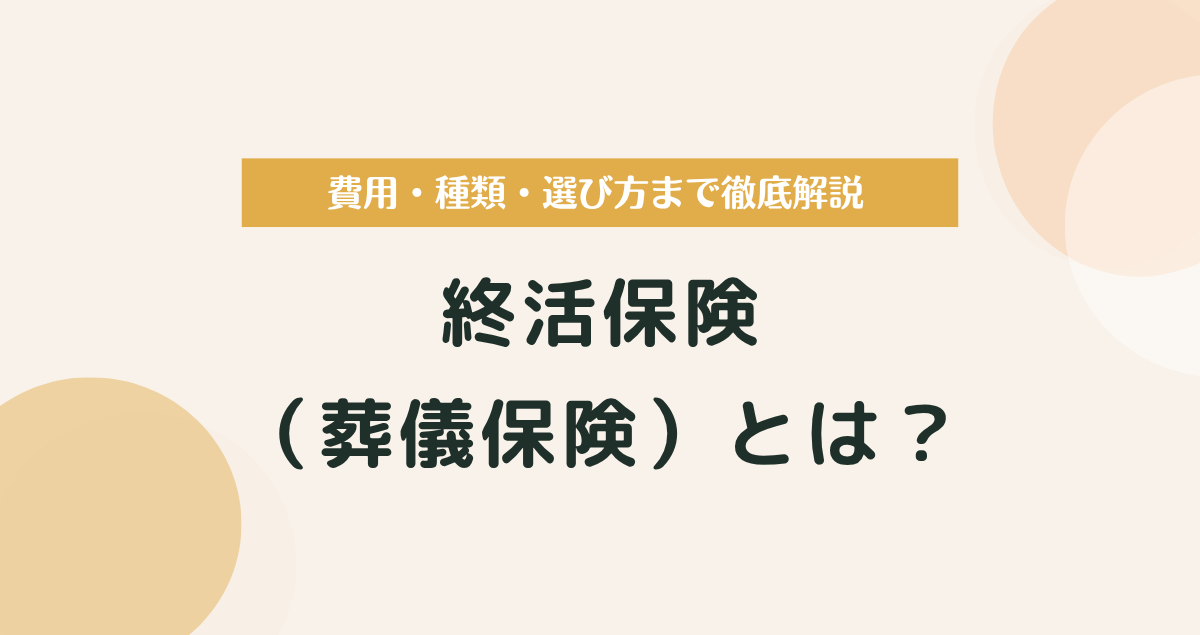人生の最期を迎える際、残された家族に経済的な負担をかけたくないと考える方が増えています。葬儀費用は平均100万円以上かかることも珍しくなく、急な出費に備える「終活保険(葬儀保険)」が注目されています。
本記事では、終活保険の基本的な仕組みから具体的な選び方、他の準備手段との比較まで、専門的な内容を分かりやすく解説します。
目次
終活保険(葬儀保険)とは?

終活保険(葬儀保険)は、主に葬儀費用をカバーするために設計された保険商品です。
一般的な生命保険と異なり、比較的少額で加入しやすく、高齢者でも申し込みやすい設計になっています。
主な特徴
- 保険金額:30万円〜300万円程度
- 保険の種類:少額短期保険が主流
- 保険料:掛け捨て型
- 保障期間:終身または一定期間
- 加入年齢:40歳〜89歳まで(商品により異なる)
少子高齢化の進行、核家族化による準備の個人化、葬儀費用の不透明さ、そして経済的負担を家族にかけたくないという想いから、終活保険のニーズが高まっています。
終活保険のメリット
終活保険の最大の魅力は、「もしものときに家族が困らないように準備できること」です。
葬儀費用の備えを中心に、心の安心を得られる点が多くの人に支持されています。
メリット① 葬儀費用の備えになる
- 突然の出費に備え、あらかじめ葬儀費用を確保できる
- 預金口座が凍結されても、保険金で葬儀を進められる
- 「家族に迷惑をかけたくない」という想いを形にできる
メリット② 高齢でも加入しやすい
- 80代でも申し込み可能な商品が多い
- 持病があっても加入できる「緩和型」「無選択型」プランがある
- 医師の診査が不要な場合もあり、手続きがスムーズ
メリット③ 保険金がすぐに支払われる
- 多くの保険会社で5営業日以内に保険金を支給
- 葬儀社へ直接支払うサービスがあり、家族の手間を軽減
メリット④ 毎月の負担が少なく続けやすい
- 月々1,000〜3,000円程度から加入できる商品が多い
- 必要最低限の保障を選べば、無理なく長く続けられる
終活保険の選び方

終活保険を選ぶ際は、保険金額、告知形式、契約形態など、複数の要素を総合的に検討する必要があります。自分の健康状態、経済状況、希望する葬儀スタイルに合わせて、最適なプランを選択しましょう。
1. 保険金額の設定
最新の全国調査では、葬儀の総額平均は118.5万円と報告されています(対象:喪主経験者2,000名)。
出典:いい葬儀「第6回 お葬式に関する全国調査(2024年)」
自分の希望する葬儀スタイル(家族葬、直葬など)に合わせて保険金額を設定しましょう。
| 葬儀スタイル | 費用目安 | 推奨保険金額 |
|---|---|---|
| 直葬 | 20万円〜40万円 | 50万円程度 |
| 家族葬 | 60万円〜100万円 | 100万円〜150万円 |
| 一般葬 | 100万円〜200万円 | 150万円〜300万円 |
2. 告知形式の選択
終活保険には、健康状態に応じたさまざまな加入方法(告知形式)が用意されています。自分の体調や持病の有無に合わせて、適切なプランを選ぶことがポイントです。
通常タイプ
- 健康状態の告知が必要
- 保険料が比較的安い
- 健康に自信がある方におすすめ
緩和型
- 簡単な健康質問のみ
- 通常タイプより保険料は高め
- 持病があるが軽微な方向け
無選択型
- 健康状態の告知不要
- 保険料が最も高い
- 健康状態に不安がある方向け
3. 契約形態と税務の注意点
終活保険では、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、税金の種類や課税対象が大きく変わります。
契約形態を誤ると、意図しない贈与税や所得税が発生することもあるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
親が被保険者・子が契約者の場合、相続ではなく贈与と見なされることがあり、税金の扱いが変わります。契約前に税務面の確認も忘れずに。
契約パターンと税務上の取扱い
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税務上の取扱い |
|---|---|---|---|
| 本人 | 本人 | 配偶者・子 | 相続税 |
| 子 | 親 | 子 | 所得税(一時所得) |
| 子 | 親 | 配偶者 | 贈与税 |
契約前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
主要保険会社の商品比較
終活保険を提供する主な少額短期保険会社の特徴をまとめました。加入年齢や保険金額、支払いスピード、
付帯サービスなどを比較し、自分のニーズに最も合う商品を選びましょう。
| 保険会社・商品名 | 加入年齢 | 保険金額 | 支払スピード | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|
| アイアル少額短期保険 「終活相談付き みんなの葬儀保険」 |
40〜84歳 | 30万〜200万円(5プラン) | 原則5営業日以内 |
|
| SBIいきいき少額短期保険 「SBIいきいき少短の死亡保険」 |
満84歳まで | 100万〜600万円 | 最短5営業日以内 |
|
| 富士少額短期保険 「できる!死亡保険」 |
満1〜89歳 | 30万〜300万円(12プラン) | 5営業日以内 |
|
| メモリード・ライフ 「はじめやすい葬儀保険」 |
満89歳まで | 30万〜300万円(10万円単位で設定可能) | 最短翌営業日 |
|
他の準備手段との比較
葬儀費用を準備する方法は終活保険だけではありません。終身保険、銀行預金、互助会など、それぞれに特徴があります。各手段のメリット・デメリットを比較検討し、自分に最適な準備方法を選択することが大切です。
| 比較項目 | 終活保険 | 終身保険 | 銀行預金 | 互助会 |
|---|---|---|---|---|
| 主な目的 | 葬儀費用の備え | 相続・貯蓄・死亡保障 | 貯金 | 葬儀サービス利用 |
| 保険料・費用 | 安価、掛け捨て | 高額、貯蓄型 | 任意 | 積立式(月額) |
| 加入しやすさ | 高齢でも可、告知不要あり | 高齢では制限あり | いつでも可 | 加入制限は少ない |
| 受け取り方 | 現金で遺族へ支給 | 現金(返戻金あり) | 引き出しに制限あり | サービス提供(現金支給不可) |
| 自由度 | 葬儀社選択可 | 柔軟だが保険会社による | 自由 | 提携葬儀社のみ |
| その他の注意点 | 解約返戻金なし | 長期間払い続ける必要 | 死亡後に凍結 | 中途解約で返戻金が少ない |
よくある質問(FAQ)
終活保険はどんな人に向いていますか?
終活保険は「葬儀費用をあらかじめ準備しておきたい方」や「家族に経済的な負担をかけたくない方」に向いています。
高齢でも加入しやすい商品が多く、貯蓄よりも確実に資金を残したい方に選ばれています。
家族にはどんな手続きをしてもらう必要がありますか?
保険金を受け取るためには、死亡診断書や保険証券などを提出する必要があります。
事前に契約内容と保険会社の連絡先を家族に共有しておくと、万一の際もスムーズに手続きが進められます。
まとめ
終活保険は葬儀費用の備えとして有効な選択肢の一つです。加入しやすさや迅速な保険金支払いというメリットがある一方で、掛け捨て型で貯蓄性がないというデメリットもあります。
保険金額、告知形式、保険料を総合的に比較し、自分の健康状態や経済状況に合った商品を選ぶことが重要です。契約前には家族と内容を共有し、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。