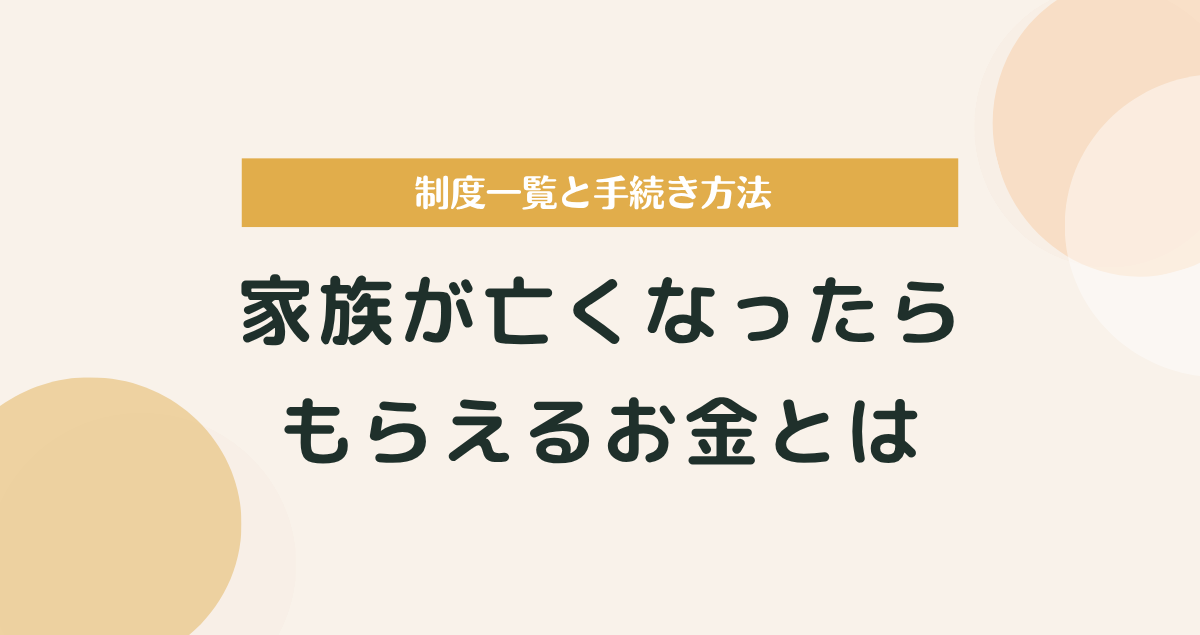家族を亡くした直後は、悲しみの中で多くの手続きや費用負担に追われます。
特に「もらえるお金」があっても制度名や申請方法が分からず、受け取らずに終わってしまうケースは少なくありません。
本記事では、遺族が受け取れる可能性のあるお金を制度別に整理し、申請の流れや期限をわかりやすく解説。
あわせて死亡後に必要な手続き一覧や優先順位、具体的なケーススタディも紹介します。
「知らなかった」で損をしないために、いまから備えておきましょう。
目次
遺族が受け取れるお金の種類とは?
| 制度名 | 対象者 | 支給内容 | 申請期限 | 申請先 | 公式リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者・子 | 年額と子の加算あり | 死亡翌日から5年以内 | 市区町村役場/年金事務所 | 日本年金機構 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金加入者の遺族(配偶者・子等) | 報酬比例部分の4分の3+加算あり | 死亡翌日から5年以内 | 年金事務所 | 日本年金機構 |
| 寡婦年金 | 第1号被保険者の夫に10年以上生計維持されていた妻 | 夫の老齢基礎年金額の4分の3(60~65歳) | 死亡翌日から5年以内 | 市区町村役場 | 厚生労働省(手続きガイドPDF) |
| 死亡一時金 | 国民年金第1号被保険者の遺族 | 12万~32万円(納付月数に応じる) | 死亡翌日から2年以内 | 市区町村役場 | 日本年金機構 |
| 埋葬料(健康保険) | 協会けんぽ・健保組合の被保険者の遺族 | 原則5万円(組合により付加給付あり) | 2年以内 | 健康保険組合/協会けんぽ | 協会けんぽ |
| 葬祭費(国民健康保険) | 国民健康保険の被保険者の葬祭執行者 | 3~7万円(自治体により異なる) | 2年以内 | 市区町村役場 | 各自治体HP例:東京都港区 |
| 遺族補償年金(労災保険) | 業務上の死亡労働者の遺族 | 基礎日額×153~245日分/年+特別支給金300万円 | 5年以内 | 労働基準監督署 | 厚生労働省 |
| 遺族補償一時金(労災保険) | 遺族補償年金を受けられる遺族がいない場合 等 | 基礎日額×1000日分+特別支給金 | 5年以内 | 労働基準監督署 | 厚生労働省 |
| 葬祭料(労災保険) | 労災で亡くなった労働者の葬祭執行者 | 31.5万円+基礎日額×30日(最低60日分) | 2年以内 | 労働基準監督署 | 遺族 補償 等給付 葬祭料等 葬祭給付 の請求手続 |
| 民間生命保険の死亡保険金 | 保険契約で指定された受取人 | 契約額(数百万円~数千万円) | 約款で3年が一般的 | 加入先保険会社 | |
| 個人年金保険の死亡給付金 | 保険契約で指定された受取人 | 払込保険料相当額など(契約内容による) | 約款で3年が一般的 | 加入先保険会社 | |
| 死亡退職金 | 在職中に死亡した従業員の遺族 | 勤続・給与等で算定(会社・公務員規程による) | (目安)5年の時効 | 勤務先 | |
| 弔慰金 | 勤務先が遺族へ支給する見舞金 | 会社規程による(非課税範囲あり) | 規程による | 勤務先 |
※金額や要件は年度や自治体・保険者の規程により異なります。必ず最新の公式ページで確認してください。
年金関連(国の制度)
遺族が生活を維持するための基盤となる公的年金の給付です。加入状況や家族構成により対象や金額が変わります。
- 遺族基礎年金:18歳到達年度末までの子どもがいる配偶者、または子が対象。家計の基礎的な生活費の補填を目的とします。
- 遺族厚生年金:厚生年金加入者が亡くなった場合に支給。配偶者が終身で受け取れるケースもあります。
- 寡婦年金:第1号被保険者だった夫に生計を維持されていた妻が対象となる給付(受給は原則60~65歳の期間)。
- 死亡一時金:国民年金の被保険者が死亡した場合に、納付月数に応じて遺族に一時金が支給される制度。
※いずれも要件・加算・併給調整の有無に注意してください。
健康保険関連(葬祭費・埋葬料)
葬儀にかかる費用の一部を補うための給付です。加入していた医療保険の種類により名称や支給額が異なります。
- 埋葬料(健康保険):協会けんぽや健康保険組合の被保険者が亡くなった場合に支給。原則定額で、組合により付加給付がある場合があります。
- 葬祭費(国民健康保険):国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、葬祭執行者へ支給。金額は自治体により差があります。
※申請期限は概ね2年以内。葬儀の領収書や保険証の返却など、必要書類の不備に注意。
労災保険関連(業務中・通勤中の死亡)
業務上または通勤途上の災害による死亡に対して支給されます。遺族の継続的な生活支援を目的とした年金と、一時金・葬祭料があります。
- 遺族補償年金:基礎日額に所定日数を乗じて年額を算定。遺族の範囲や順位により配分が異なります。
- 遺族補償一時金:年金を受けられる遺族がいない等の場合に支給される一時金。
- 葬祭料:葬祭執行者に対して支給。定額部分と基礎日額連動部分の合算で算定されます。
※請求期限は概ね5年以内。業務・通勤起因性の立証(事実関係の資料)が重要になります。
勤務先からの給付
企業や公務員の就業規則・退職金規程・福利厚生制度に基づき支給されます。規程の有無・内容を早めに確認しましょう。
- 死亡退職金:勤続年数・最終給与・係数などに基づき算定。数百万円規模となることもあります。
- 弔慰金:勤務先からの見舞金。金額や条件は規程次第で、非課税範囲の取り扱いがある場合もあります。
※申請窓口・必要書類・時効は各社規程に従います。人事・総務へ早めに連絡を。
民間保険(生命保険・個人年金)
加入している保険契約に基づき支払われます。契約者・被保険者・受取人の指定、約款の請求期限を必ず確認してください。
- 生命保険の死亡保険金:契約額に応じて支払われます。数百万円~数千万円規模になることもあります。
- 個人年金保険の死亡給付金:払込保険料相当額等、契約内容に応じた給付が行われます。
※請求期限は約款で定められているのが一般的(目安として数年)。保険証券・指定受取人の確認を。
手続きの優先順位|まず何から始めるべきか
以下の図は、死亡後に必要な手続きを大まかな期限ごとに整理したものです。

死亡後に行う主な手続き一覧
こちらの表では、各手続きの「期限」「必要書類」などをより詳しくまとめています。実際に動く際はこちらを参考にしてください。
| 順番 | 手続き | いつまでに | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 1 | 死亡届の提出 | 死亡後7日以内 | ・死亡届 ・死亡診断書 |
| 2 | 火葬許可証の申請・取得 | 死亡後7日以内 | ・死亡届 ・届出人の印鑑 ・届出人の身分証 |
| 3 | 住民票の除票の取得 | できるだけ早期に | ・来庁者の本人確認書類 ・印鑑 |
| 4 | 世帯主の変更 | 死亡後14日以内 | ・来庁者の本人確認書類 |
| 5 | 健康保険・介護保険の資格喪失 | 死亡後14日以内 | ・各種保険証 |
| 6 | 国民年金・厚生年金の資格喪失手続き | できるだけ早期に | ・資格喪失届出 |
| 7 | 雇用保険の資格喪失手続き | 死亡後10日以内 | ・資格喪失届 |
| 8 | 雇用保険受給者資格証の返還 | 死亡後1ヶ月以内 | ・雇用保険受給者資格証 |
| 9 | 公共料金の解約または名義変更 | できるだけ早期に | ・契約会社により異なる |
| 10 | 生命保険の死亡保険金請求 | 死亡後3年以内 | ・所定の請求書 ・死亡診断書 など |
| 11 | 健康保険・葬祭費の請求 | 死亡後2年以内 | ・葬祭費支給申請書、請求書 ・亡くなった人の被保険者証 など |
| 12 | 健康保険・埋葬料の請求 | 死亡後2年以内 | ・亡くなった人の被保険者証 ・死亡診断書 など |
| 13 | 国民年金・死亡一時金の請求 | 死亡後2年以内 | ・亡くなった人の基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) など |
| 14 | 国民年金・遺族基礎年金の請求 | できるだけ早期に(5年以上経過で時効の可能性あり) | ・基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・死亡者の住民票の除票 など |
| 15 | 国民年金・未支給年金の請求 | できるだけ早期に(5年以上経過で時効の可能性あり) | ・亡くなった人の年金証書 ・戸籍謄本 ・受け取りを希望する金融機関の通帳 など |
| 16 | 厚生年金・遺族厚生年金の請求 | できるだけ早期に(5年以上経過で時効の可能性あり/死亡後1年以内が望ましい) | ・基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・死亡者の住民票の除票 など |
| 17 | 遺産分割協議 | 期限なし(できるだけ早期に) | ・被相続人が出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本 など |
| 18 | 相続税の申告・納付 | 死亡後10ヶ月以内 | ・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し ・相続人全員の印鑑証明書 など |
※記載の期限・必要書類は一般的な目安です。自治体や加入制度により異なる場合があります。
解説:
死亡後の手続きは、提出期限が厳格に決められているもの(死亡届や世帯主変更など)から、期限が長いもの(相続税申告・保険金請求など)までさまざまです。特に以下の点に注意しましょう。
- 最優先の手続き:死亡届の提出と火葬許可証の取得は、葬儀や火葬の実施に必須です。必ず期限内に行いましょう。
- 社会保険関連:健康保険・介護保険・雇用保険・年金の資格喪失は、放置すると保険料が二重請求されることもあるため、できるだけ早期に済ませることが大切です。
- 生活費の支援制度:遺族年金や未支給年金は、時効により受給できなくなる可能性があります。5年以内を目安に、早めの申請を心がけましょう。
- 相続関連:相続税の申告・納付は死亡後10か月以内と期限が厳格に決められています。遺産分割協議の進め方によっては期限内に間に合わないこともあるため、早期に専門家へ相談すると安心です。
- 日常生活に直結する手続き:公共料金や契約の名義変更を忘れると、不要な請求が続く可能性があります。死亡後できるだけ早期に整理しましょう。
これらの手続きを一度に行うのは大変ですが、「期限が短いものから優先」「時効があるものは早め」を意識することで、抜け漏れを防げます。
具体的なケーススタディ
ケース1:会社員の夫(45歳)が亡くなった場合
家族構成:妻(43歳)、子ども2人(15歳、12歳)
夫の収入:月給35万円、厚生年金加入20年
受け取れるお金の例:
- 埋葬料:5万円
- 死亡退職金:約200万円(月給の6ヶ月分)
- 団体生命保険:300万円
- 遺族基礎年金:年間約100万円(子が18歳まで)
- 遺族厚生年金:月額約7万円(終身)
- 個人の生命保険:1000万円
合計:約1500万円+継続的な年金給付
ケース2:自営業者の夫(50歳)が亡くなった場合
家族構成:妻(48歳)、子ども1人(16歳)
夫の状況:国民年金加入25年、国民健康保険加入
受け取れるお金の例:
- 葬祭費:5万円
- 遺族基礎年金:年間約80万円(子が18歳まで)
- 寡婦年金:月額約3万円(60歳~65歳)
- 個人の生命保険:800万円
合計:約800万円+限定的な年金給付
自営業者の注意点:厚生年金がないため、遺族厚生年金が受けられません。生命保険による保障を厚くしておくことが重要です。
まとめ|「知らなかった」では損をする、今から準備できることを
家族が亡くなったあとに受け取れるお金には、葬祭費、遺族年金、退職金、保険金など多様な制度があります。しかし、どれも「申請しなければもらえない」ことがほとんどです。
今すぐできる3つの行動
- 現在の加入制度を整理する:年金、健康保険、生命保険の契約内容を確認
- 家族との情報共有:エンディングノートやチェックリストで必要情報を整理
- 手続きの優先順位を把握:いざというときの行動計画を立てる
万が一に備え、今からできる備えを始めておくことが、遺族の負担を軽減し、確実に権利を守ることにつながります。
最後に重要なポイント:制度は変更されることがあるため、定期的な情報更新も忘れずに行いましょう。
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。