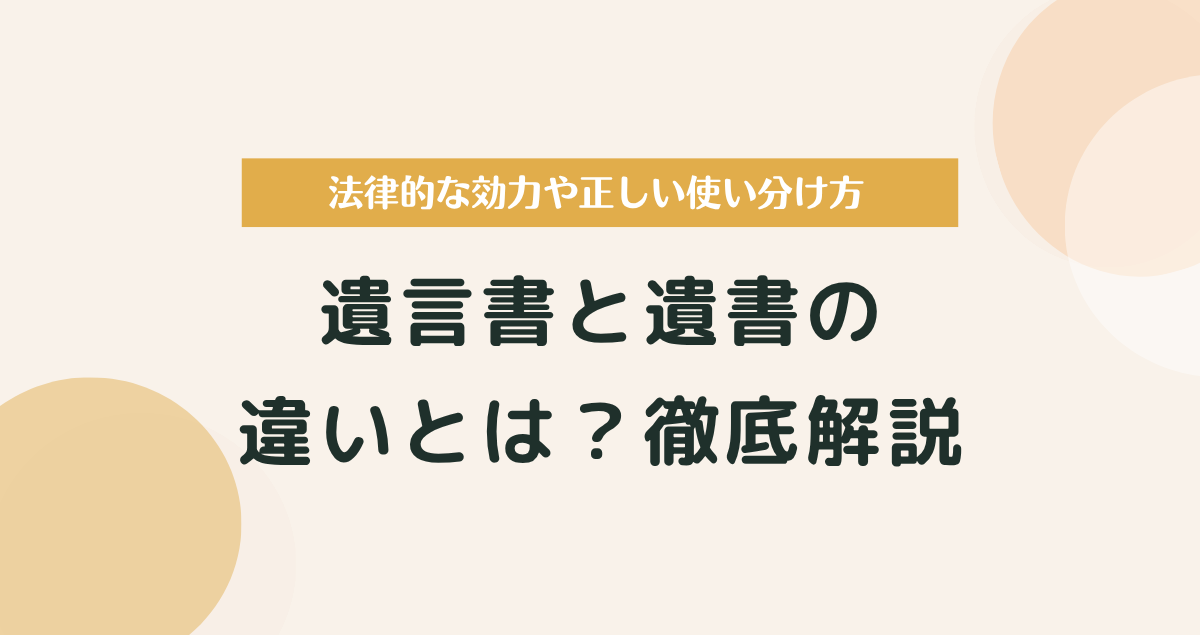「遺言書」と「遺書」。似ている言葉ですが、実はまったく意味が違うのをご存じですか?
「遺書に財産のことを書いておけば大丈夫」と思っていたのに、実は無効で相続トラブルに発展する――こうしたケースは少なくありません。
せっかくの想いが正しく伝わらず、家族に争いを残してしまうのは避けたいところです。
本記事では、遺言書と遺書の違いをわかりやすく解説し、正しい使い分けや注意点を紹介します。さらに、遺言書を安心して作成・保管するためのポイントや相談先もまとめました。
遺言書と遺書の基本的な違い

「遺言書」と「遺書」は似た言葉のため混同されがちですが、法律上の扱いは全く異なります。まずは定義を押さえましょう。
遺言書とは何か
遺言書は、遺産分割や相続に関する本人の意思を、民法第960条以降の規定にのっとって記した文書です。厳格な形式を満たせば法的効力を持ち、財産の分配方法や遺贈などを指定できます。
遺言書の主な機能:
- 財産の分配方法を指定
- 相続人以外への遺贈
- 遺産分割方法の指定
- 遺言執行者の指定
- 認知や後見人の指定
遺書とは何か
遺書は、人生の最後に家族や友人へ思いを伝える手紙のようなものです。原則として法的効力はなく、財産分与などの指示には使えません。ただし感謝や謝罪、人生の教訓を残すなど精神的価値は大きい文書です。
主な違いのまとめ表
| 項目 | 遺言書 | 遺書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | あり(民法第960条以降に基づく) | なし |
| 目的 | 財産の分配、相続の意思表示 | 気持ちや想いを伝える手紙 |
| 書式の制限 | あり(自筆、公正証書など) | 自由形式 |
| 主な内容 | 財産分与・遺贈・付言事項など | 感謝の言葉、謝罪、メッセージなど |
| 作成費用 | 無料〜数万円 | 無料 |
| 保管方法 | 法務局、公証役場、自宅金庫等 | 自由(家族に託すことが多い) |
遺言書の作成方法と種類
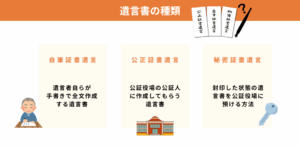
遺言書には3つの方式があり、それぞれメリット・デメリットがあります。特に2020年からは自筆証書遺言の法務局保管制度が始まり、利用しやすくなりました。
3種類の遺言書の比較表
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成者 | 本人が自筆で作成 | 公証人が作成(本人の意思に基づく) | 本人が作成し、公証人が存在を証明 |
| 費用 | 無料 | 約1〜10万円(財産額により変動) | 約1.1万円+証人謝礼 |
| 形式要件 | 全文自筆・日付・署名押印(民法第960条) | 公証人の面前で口述し、公証人が記録 | 本人が作成したものを封印し、公証人に提出 |
| 法的効力 | あり(形式が整えば有効) | あり(無効リスクが最も低い) | あり(ただし形式不備で無効になりやすい) |
| 保管方法 | 自宅・法務局保管制度(3,900円) | 公証役場で自動保管 | 本人・公証人いずれも保管可 |
| 検認手続き | 必要(法務局保管分は不要) | 不要 | 必要 |
| メリット |
|
|
|
| デメリット |
|
|
|
| おすすめ度 | ◎(費用を抑えたい方) | ◎(確実に残したい方) | △(特殊な事情がある方のみ) |
遺書の正しい役割と注意点

遺書は法的効力こそありませんが、心情面で大きな意味を持つ文書です。誤解やトラブルを避けるため、適切な書き方を理解しておきましょう。
遺書の適切な役割
- 感謝の気持ちや思いを伝える
家族へ
長い間、本当にありがとうございました。
特に○○さんには、病気の時に献身的に看病していただき、心から感謝しています。私の人生は、皆さんのおかげで幸せなものでした。
これからも家族仲良く過ごしてください。令和○年○月○日
- 人生の振り返りと教訓
- 心の整理と癒し
法的効力がないことの理解
重要な注意点:遺書に「○○に財産を渡したい」「借金は○○に負担してもらいたい」と書いても、法的な効力は基本的に発生しません。
実際のトラブル例:
- 遺書に「長男に全財産を」とあったが、無効扱いとなり法定相続どおりに分割
- 遺書の内容と遺言書の内容が矛盾し、家族が混乱
実際の相続に影響を与えるには、遺言書としての形式が必要です。
遺書に書いてはいけないこと
- 財産の分配に関する指示:期待を持たせるだけで後のトラブルに
- 特定の人への非難や批判:遺族の関係悪化の火種に
- 遺言書と矛盾する内容:相続人間の混乱を招く
遺言書と遺書の効果的な併用方法
遺言書と遺書は、併用するのが理想です。
- 遺言書:財産分割や相続手続きを明確に(法的効力)
- 遺書:家族への感謝や想いを伝える(心情面のケア)
さらに、遺言書には付言事項として想いを記すことができます。たとえば「なぜこの財産を特定の相続人に託したのか」を説明すれば、相続人の納得感が高まり、争いの予防に役立ちます。
【良い例】
遺言書:「A土地は長男に相続させる」
遺書(または付言):「A土地は長男が幼い頃から大切にしてくれたので、託したいと思います」
【悪い例】
遺言書:「A土地は長男に相続させる」
遺書:「本当は次男にA土地を渡したかった」
無効になりやすい遺言書の特徴
よくある無効事例
- 形式的要件の不備:日付が「○月吉日」など不明確/署名・押印の欠落/代筆・PC作成(財産目録以外)
- 内容の不備:相続人や財産の特定が不十分/法的に不可能な内容/遺留分を完全に無視
- 能力の問題:判断能力の著しい低下時に作成/第三者による強制・詐欺
無効を避けるためのチェックリスト
作成前の確認事項:
- [ ] 財産の詳細な把握
- [ ] 相続人の確認
- [ ] 遺留分の計算
- [ ] 税務上の検討
作成時の確認事項:
- [ ] 日付の正確な記載
- [ ] 署名・押印の確認
- [ ] 内容の明確性
- [ ] 法的要件の遵守
専門家への相談のメリットと相談先

相談を検討すべきケース
- 財産が複雑:不動産が複数/事業を営む/株式・投資信託を保有
- 家族関係が複雑:再婚/子どもがいない/相続人同士の不仲
- 税務対策:相続税の可能性/贈与との最適化
相談先と費用の目安
- 行政書士:遺言書作成・相続手続き/目安3〜10万円
- 司法書士:不動産登記・相続手続き/目安5〜15万円
- 弁護士:相続争い・複雑案件/目安10〜30万円
- 税理士:相続税対策/目安10〜20万円
よくある質問(FAQ)
Q1. 遺書に財産のことを書いても有効ですか?
いいえ、遺書に財産分配を書いても法的効力はありません。 遺書は感謝や思いを伝えるための手紙であり、財産を誰に渡すかを指定するには、定められた方式に従った「遺言書」を作成する必要があります。
Q2. 遺言書は何歳から作成できますか?
民法第961条によって、15歳に達した者は遺言をすることができます。 未成年でも15歳以上であれば、自分の意思で有効な遺言書を作成できます。
Q3. 自筆証書遺言はパソコンで作っても大丈夫?
本文はすべて自筆で書く必要があります。ただし、2019年の法改正により財産目録のみパソコンやワープロで作成可能になりました。目録のすべてのページに署名押印が必要です。
Q4. 遺言書の内容を変えたいときはどうすればいいですか?
新しい遺言書を作成すれば、最新の日付のものが有効になります。古いものを破棄しても構いませんが、「前の遺言書を撤回する」と明記しておくとより確実です。
まとめ
重要なポイント:
- 遺言書=法的効力あり(民法第960条以降)/遺書=想いを伝える文書(法的効力なし)
- 両方を適切に使い分けることで、家族の安心と納得が得られる
- 無効を防ぐには、形式の遵守と専門家のチェックが有効
okusokuでは、終活や相続、デジタル遺品整理に関する情報を、正確でわかりやすくまとめています。読者の方が「迷わず次のステップに進める」「家族と安心して話し合える」ように、実用的で保存して役立つコンテンツづくりを心がけています。